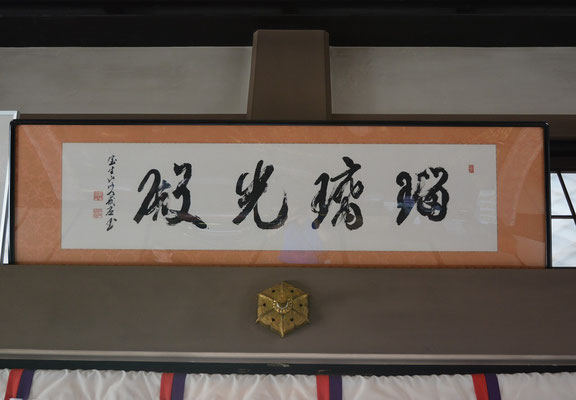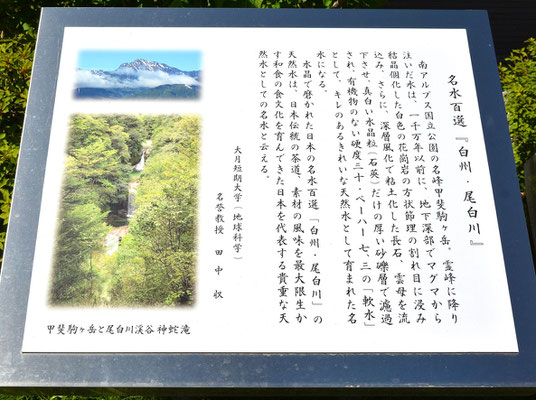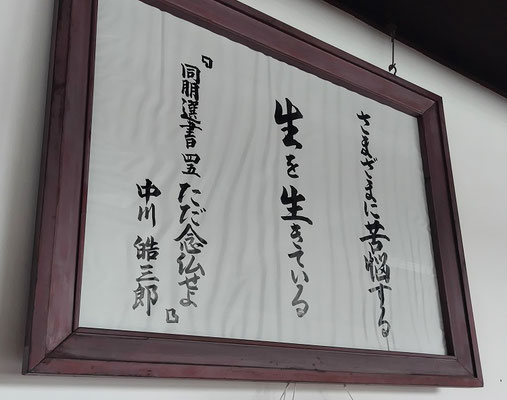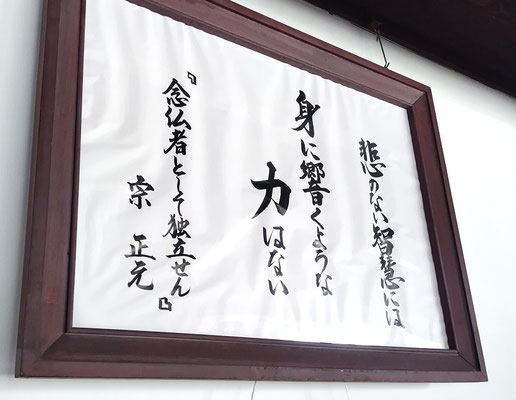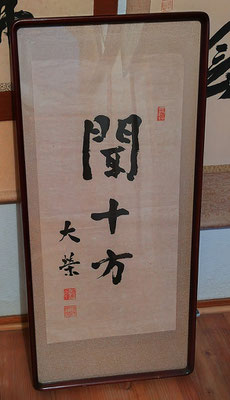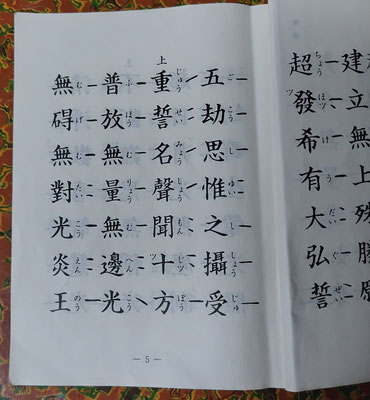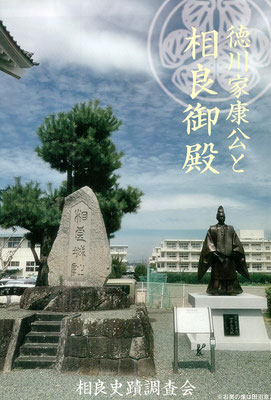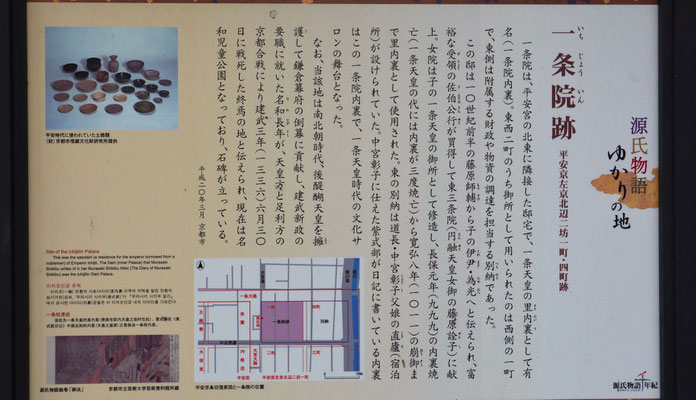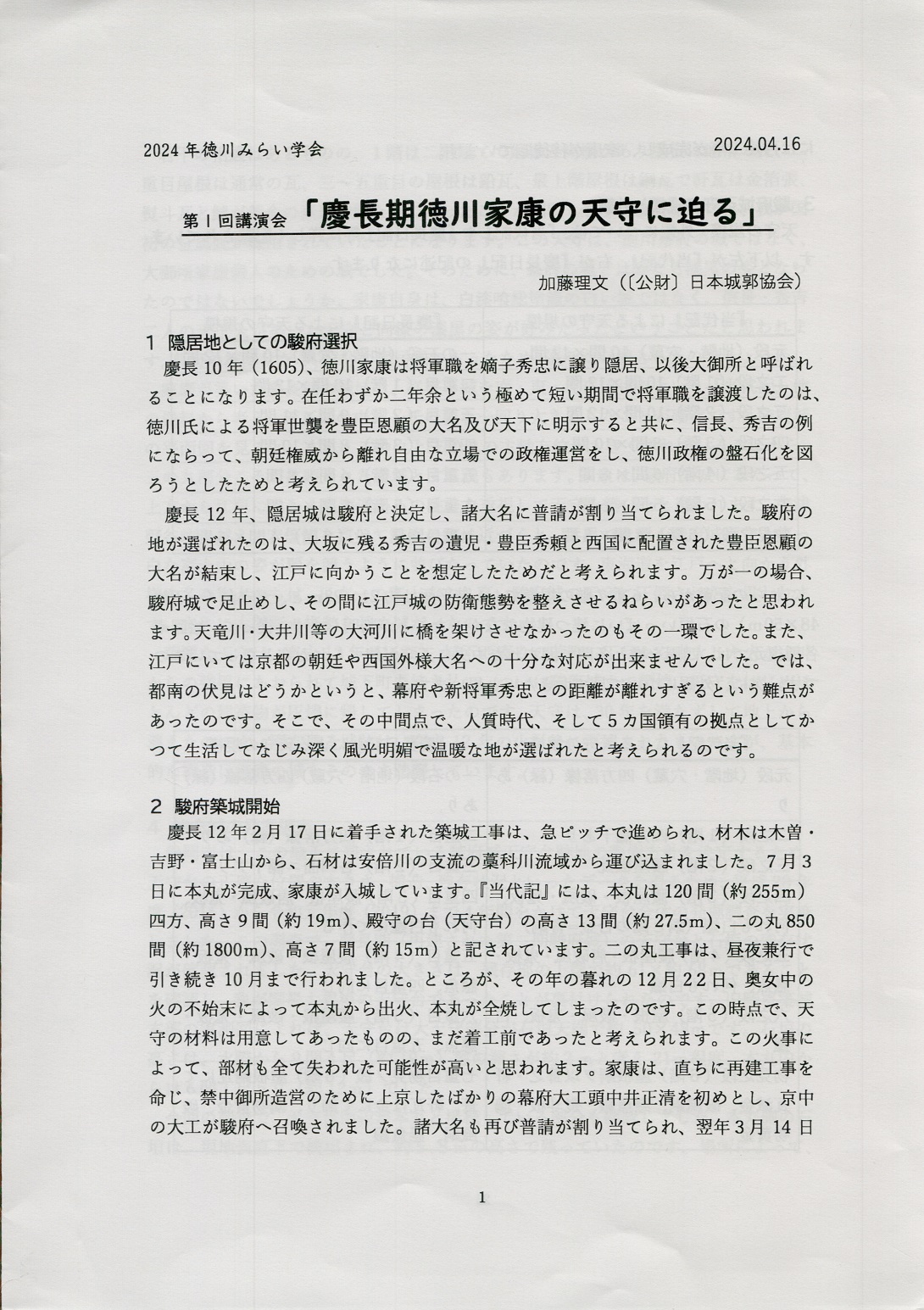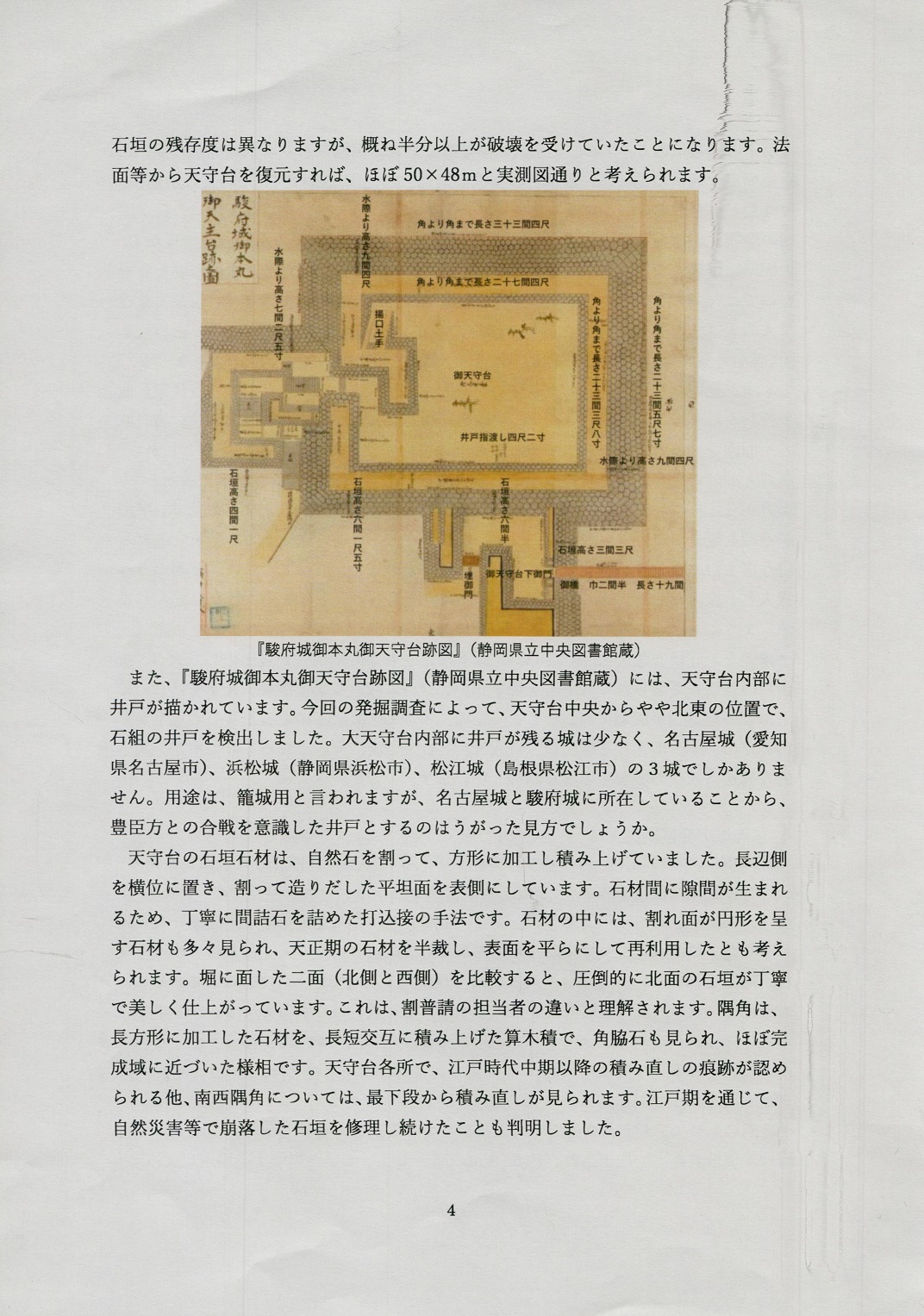2024年
7月
27日
土
白羽神社 横須賀街道と武田朱印状 簡易オービス
一昨日の夕刻は当地でもポツポツ。
携帯には「牧之原市に雨雲がせまっています」の情報があって、それなら水やりは不要とばかりに雨を待ちましたが、一向に夕立風情景は見えずそのポツポツにて御終いでした。
東北地方は前線の通り道となっているようで豪雨と河川氾濫の報が流れていました。
何事も「平均的」というものは有りえず偏りすぎが顕著。
ヤラれる時は徹底的にヤラれる・・・それが自然、人心あれこれについての配慮など自然界にとってまったくお構いなし。
ある意味それもそこに生きる人の有り様といってもいいのでしょう。
安心安全安定を期待してもそもそも人というものは死から逃れることはできませんからね。
対自然も当たり前の事。生きるために振り回されている私たち。
まぁそれが生きている証であって、「いま居る」(私の姓は今井)という現実に喜怒哀楽しながら感謝感激の日々を送ります。
先日は誕生日というものを迎えましたがいよいよ「明日死ぬ、今死ぬ・・・」を思い描くようになりました。
いずれ死ぬ・・・ではなく「今去(イ)ぬ」です。もっともそれは「齢だから」思うものではありませんが。
もっとも若い頃は「ダイ・ハード」(絶対死なない)の勢い(高慢)が強くありました。それが「いずれ死ぬ」の「いずれ・・・」の発想。その件理解はしているが「今ではなく・・・ずっと後」といったもの。それが深層「私は死なない」の心でしょうか。
それを「強い人物」の仮面とすりかえているのがトランプ(昨日)でしょうね。銃弾も耳をかすっただけでしたし。
仏教的に言ってそのような人間には慈悲(仏教の主眼)というものが欠落する傾向があると思います。
そして慈悲の心が芽生えるそのベースとは「己の反省」(懺悔さんげ)からと考えるからですね。
自己の為すことがすべて正義であるとそれを振りかざす・・・そこには他を承認しない毒舌が生まれますから。
自己中というヤツです。
まぁ、私のその考えは親鸞さんの善知識、善導さんからの少々かいつまんだところからですが。
そうは言っても私も内心「今スグ、明日には・・・」のところ了解しているものの「まさか私が・・・」なのですからしょうもない。
その「まさか」の坂はあるとは言っても理論上・・・と誤魔化す我が身。やはり「ダイ・ハード」なのでした。
私だけが味わえる「その時」、その直前にまた考えましょう。
良き人生だったと。
扨、先日オービス(速度取締り装置)が小型化して簡易型、移動設置型のそれが世に溢れ出し当県も各所でその目撃談を聞くようになりました。
「どこでもオービス」という取締り方の新戦力ですね。
それは幹線道路というよりも住宅地、学区の生活道路、抜け道といわれる道路での取締りに威力を発揮します。
30キロ道路などですね。
これまでそのような場所でその戦術が展開されたことのないような場所になりますので、ドライバーとしては意表を突かれてしまいます。当局お役人から御用、ご指導の頂戴。そして減点、過酷な罰則金の支払いとあいなります。
もしその30キロ道路を60キロ以上で走った場合、30キロオーバーで、一発免停、罰金は簡易裁判所に出廷し決定されるもの。25000円以上になるでしょうね。
私も吉田の初倉の東名吉田インターから島田方面に北上する道の裏道、初倉保育園のある住宅地の道で見かけました。
奥方と第一声「なんでこんなところで・・・」でした。
私は前走車があったためセーフでしたが気が小さいものですから、心拍数アップ。
そして、先日御前崎の方が「これまた驚いた」とその体験談をお話しされていました。
場所が御前崎白羽(しろわ)小学校前の道。
「初めて見た」と驚きの声。
そういえば県内通学路の生徒を撒きこむ事故が増えているよう。
おそらく学区通学路での取締りが重点的に行われるようになっているのでしょう。まぁその件ドライバーにとって大いに警告となるでしょうね。
いずれの道ものんびり行くとしましょう。
自分も死ぬが何時人を殺めるかもわからない。
その白羽小学校の先に武田の陣となった白羽神社があります。
武田家安堵状が三通残ることで当相良史蹟調査会の皆さんでお伺いさせていただこうという企画がありましたが、コロナ禍によって消滅。
以後田沼大河が持ち上がって現状その件棚上げされています。
元亀三(1572)の信玄発給文書。
そして天正二(1574) 天正五(1577)と勝頼が出したものですが、いずれも高天神城の包囲の際の地元対応ですね。
やはり武田は相当「海」を意識していたのでしょう。
遠州灘まで目と鼻の先(場所はこちら)。
また境内には横須賀街道についての記述が。堀野新田の了見寺の名が見えます。
2024年
7月
26日
金
蒲郡塩津中学校グラウンド横の墓地 竹谷松平四代
バイデン大統領歩行その他の動きを拝見してこれはフレイルの始まりでは・・・と感じたのは私だけ?。
ベタ足歩行にゆっくりとした動作、飛行機のタラップから降りる際の様など、もし私が近くにいたとしたら思わず手を差し出したくなるような躰。
スピーチの中での言い間違いに関しては誰にでもあることですが、ポイントとなる人の名の間違いの数々、あまりにも人々にネガティブインパクトを与えてしまいました。
そしてコロナ罹患の療養がきっかけとなって、大統領選継続不可との判断、ハリス副大統領がここで名乗りをあげたというのがこの一週間のできごとです。
銃撃事件を機に流れはその幸運を得たトランプへの票が流れるとしての意見が多くありました。
日本の政界のおエライさん方も「ハリスではトランプに勝てない」などとおべっかの類なのでしょう、トランプヨイショのコメントしていましたが、その時私は「状況を読めない御仁がいるものだ」と感じましたね。
現状両者の支持率は拮抗していますので。
その大統領のフレイル?を感じさせる態様はお相手のトランプの口汚い強い罵声の根拠となったのでしょうが、それは「老衰」の道を辿る「自然」に対して今のところ健常者風が罵っているが如くの様。
私は78歳の彼が81歳のその件を強く指摘されてもねぇ・・・と呆れかえっていました。
その「健常」(強い私)というものはしばしば錯覚に陥るところで、いつ何時に病に罹ったり老化が進んだりの「自然」が訪れることを忘れている、気づいていない・・・の高慢を感じたものでした。「お前も老いる・・・」です。たまたま今元気を装っていても・・・
そこに来て59歳ハリス氏の登場。
相手の「爺々度」をネタにバッシングすることはもはや無理、自分自身がそれを十分に醸し出していますからね。あの手の感情的な言い回ししかできないところを見て老化の一種を思います。老い方にも色々あるのだなぁ~。
年齢の事を考えれば心身の強弱という意味で勝負がついている感。78対59ですからね。彼の四年後は82ですよ。
投票まで約3カ月。
今後若者と黒人層、無党派層を取り込んでじわじわとハリス氏がリードしていく・・・の予想に一票。
私もジジイといわれるでしょうがかつてのテレビアニメの「ハリスの旋風(かぜ)」のタイトルを思い起こします。
まさにその風か吹いていくことを願いますね。
アフリカ系+アジア系の非白人の女性大統領というのもイイ。
何よりもその笑顔がすばらしいですね。
相手を叩きのめそうと強圧強権を振りかざそうとする大統領殿というのは見ていて不快にさせられます。
「気候変動など無い」と主張しながらの自国第一主義は「自分さえ良ければ相手のことはどうでもいい」という発想に繋がっり、他の国々と軋轢を生みます。まして人心は荒みますからね。
私にその選択に参加する権利などこれっぽっちもありませんがハリス大統領の実現を待ちたいものです。
扨、画像は蒲郡、塩津中学校裏にある竹谷松平家四代の墓域。
中学校の教頭先生に案内していただいた墓地です(場所はこちら)。
最後の画像⑫が大きな二車線幹線道路「市役所通り」から見た墓地へ上がる道ですが⑪画像奥の道と繋がります。右側にはアパートが。
⑫の道には市役所通りにも駐車スぺースは無く掲示板等の設置はありません。
余程の地元通でなければその学校で聞きたくなるのはやむを得ないところでしょう。
尚、五輪塔は妙に細長い。
風雨経年によるものでしょうが四基とも同じようなカタチになるということは、石材の産出地が同じでしかも同時期の製作であると推測します。
2024年
7月
25日
木
本堂障子とりあえず 法名をもらう・・・
朝4時50分頃に鳴きだすクマゼミが目覚ましとなり、うつらうつら布団の中。ヤマバトの鳴き声も聞こえだしてしばらく(約1時間後)朝刊の配達のバイクの音を機にようやく立ち上がってそれを取りに境内へ。
ヤマバトが「いつものヤツを」と言わんばかりに待機しています。
クマゼミの声はそこから6時間、強烈な勢いでその空間に響き渡ります。そして1~1.5時間ほどのお昼休みを経て再び大音声。
あと1カ月が勝負でしょうが以後命を終えていく彼らです。
まさにその一所懸命(昨日)というものを思いますね。
果たして彼らは自らの死というものを承知しているのでしょうかね。
もう少しくらい手を抜いた方が長生きができそう、小賢しい思考が私に。彼らは懸命ですからね。
「余計な世話をやくな」と怒られそう。
やはり昨日、御前崎の気温は静岡より数度低い・・・と記しましたが、昨日の静岡市内は38.8℃で御前崎は30.6℃。8.2℃の差が顕わになりました。ちなみに当相良は34.6℃でした。
海岸端は静岡市内より断然すごしやすいということか・・・
昨日夕刻前に唐津のご門徒様がお参りに来られましたが(門司に出てフェリーで神戸 そちらから高速道路と)久しぶりの「相良は暑い」と。
私はそれよりもその長距離行脚の御苦労の様にただただ驚くだけでした。嬉しかったのは「何も変わってないね~」の言葉をいただいたこと。
扨、先日市内在住の方が「ちょっと相談に・・・」と拙寺に。
夫とは離縁しているとのことでしたがその息子さんがこのほど遠隔地で亡くなったとのこと。その方の息子でもありますね。
息子さんは独り身で簡易的な葬送がその地で行われ、遺骨を引き取って自宅に安置しているとのことでした。
そもそもその夫の宗旨は大谷派、本山系の某墓地にお墓があるそうですが納骨には法名が必要であるとの指摘を受けたそう。
私はその件よく存じ上げませんがあの大谷祖廟の分骨の際の書面の欄に「所属寺院」と「法名」がありますので、きっとその件もその「所属寺院」のことからなのでしょう。
所属寺院があって法名の命名がありますので、法名がナイということからその葬儀というものが真宗大谷派の流儀で執り行われていないこともわかりました。
よって私に「何とかならないものか」とのことでした。
要は私に法名の命名をタノムということですね。
そして世間でよく言う「戒名料」というものが気になったようです。
そこで「当流には戒名料の項目は無いしそもそも戒名ではなくて法名だよ・・・」
拙寺ご門徒様の場合、通夜の帰敬式で命名披露がされることが多いですが、それについて料金の設定はありません。
尚、事前に(生前に)法名を命名する時はご依頼金が発生しますが。
その方は「息子の四十九日法要と来年に初盆法要を」拙寺で執り行ったあとに納骨に向かいたいとのことも。
よって私はその場で息子さんの法名をリクエストを聞きながら決定。
「法名料はナシ。四十九日法要までに法名板を作っておきま~す」と。
すると「有難い、きっと息子がめぐり合わせてくれたのだろう」と、ここでも嬉しい言葉をいただきました。
80歳を過ぎて一人で生活。子供を亡くしその遺骨の行方について困惑されている方です。
そんな方の満足というものに対応できなくては寺としてもまた私の存在意味が問われるところですね。
画像は右側二枚に続いて正面二枚が仕上がった障子。
あらためて気持ちがイイ。
これまでのボロ寺雰囲気を大に醸し出していた穴だらけ継ぎはぎ補修だらけのそれを改めたのでした。とりあえずですが。
しかしあのバカでかい障子へは大型の障子紙一枚ではムリ。
それを重ねて貼ることが超面倒。
頼むからもう穴を空けないで~
とはいいながらもその1/3以上、やらかしているのは私か野良猫。
子供は障子というものに興味を示して穴を開けまくります。
今の在家ご自宅には大抵の場合、障子などありませんからね。
仕方ないといえば仕方ないのですが、その時・・・私の心臓の方が破れる思い。
③は本山での帰敬式のPR。
QRコードは現状まだアップされていないようですが、サイトの他のリンク先もあります。眺めてみてください。
また東本願寺の帰敬式サイトもどうぞ。
2024年
7月
24日
水
蒲郡塩津中学校教頭さんの案内 一所懸命生きる
昨日は御前崎の墓地にて墓石撤去(墓じまい)の立ち合いに。
元々拙寺のご門徒様ではなく昨年からその相談を受けていました。
その日は石屋さんをその墓地への案内することとご施主とのセッティングがありました。
石屋さんも「(暑すぎて)この天気では、今日一日で仕上げる自信がない」とのこと①②。
私は簡衣輪袈裟のスタイルでしたが、私のこの地の朝の第一印象は「風が通って涼しい!!」でした。
そういえば天気予報の気温の表示は最近やたらと「暑い」といわれようになった静岡市内よりも御前崎は2~3℃低めですからね。
墓石のトップ(竿)部分がユニックの荷台に収まった段階で失礼させていただきました。
帰宅後は障子はりの続き。
2枚完成しセット、そして中央の2枚に取り掛かりました。
天気良好につき乾燥も早く頗る捗ります。
最近の首都圏は「暑い」に+土砂降りタイムがあるようですが当地にはそれがありません。
夕刻の植物たちへの水やりがサボれることは有難いのですが。その時間帯といえば100%あ奴らとの闘いに敗北します。
炎天下では姿を見せないクセに・・・。
今、小学校の先生たちは子供たちに「外に出ないように!!」の如く指導されているようです。
テレビからは熱中症なんたらの声ばかり、要は暑いから外で遊ぶな・・・ということなのでしょう。
要は「何かあったら・・・」の責任回避の風も。
保護者もどうかしている・・・すべて教師のせいにする風潮。
一昔前より気温が上昇しているので仕方ないのでしょうが20年ほど前にから私の職場ではその夏の作業をサボるための言い訳の詞「危険だから~」とよく聞こえていました。
どいつもこいつも「蚊と同じ」なのかも。
扨、昨日の墓碑は「先祖代々」でしたが、ご門徒の墓塔としては珍しいタイプ。
拙寺、代々住職はまず推奨しない文字列です。
「骨塔」か「六字(南無阿弥陀仏)」か「倶会一処」、最近では「無量寿」というのがお決まりですね。
しかし以前行った墓地に思わずニヤリとする墓碑銘とお目にかかったことを。
最後の画像⑧ですが「一所懸命」の文字が私を喜ばせました。
「一生」でなく「一所」という文字への施主の拘りというものが窺えます。
お会いしてお話ししたくなったくらいです。墓地は私の仕事と趣味のフィールドではありますが、その墓碑は初めて見ました。
この墓地には先日竹谷城に向かうにあたって記した蒲郡の塩津中学校の教頭先生に連れられて訪れたのでした。
私が墓地の在処を伺いに学校の職員室にづかづかと入り込んだ挙句、他の先生方はそれを知らず、教頭さんの出場と相成ったわけですね。
それなら・・・と教頭先生の親身に付いてしばらく歩いてそちらに。
話が大きくなって恐縮したこと、とんだ不躾者への親切さに頭が下がります。大切な時間を頂戴してしまいました。
アポなし、特に部外者の学校等への立ち入りはホントは遠慮しなくてはならないところでしょうね。わかっていても何か私の背中を押すものがあるのです。
各事件が発生していることもありますし学校側としても部外者の突撃訪問はカンベンしてもらいたいところでしょう。
根っからの私の図々しさの件、申し訳ないことでしたが、楽しい出会いがありました。ありがとうございました。
数年前の真冬の図ですが遠くに三河湾が見えます。
墓地には地蔵堂が・・・
青い空は夏でも冬でも爽快です。家に籠っていたら何もナイ。
寒いだ暑いだの自然環境の件、動かないでイイ理由にするべからず。
2024年
7月
23日
火
蒲郡竹谷城直近全保寺 観音堂石仏 竹谷松平菩提寺
週明け昨日の法要は・・・。
外陣には大型扇風機ほか中型・小型計4台で堂内空気をかき回していますが終了後参列者皆さんの顔色を窺えば・・・ハンカチで顔の汗を拭いながらの「サウナです」の様。
申し訳なく思いますが、おゆるしいただくほかありません。
これまで厳冬期1~2月の法事は「繰り延べした方がイイかも」などのアドバイスをしたことがありますが、7~8月といえばは盂蘭盆、初盆がありますからそれはムリ。
空調の効いた本堂も世に溢れるほどありますが拙寺の如く隙間だらけのうえ障子と板戸の囲いですからね。お話になりません。
今後道内40℃近くなったとしたら今一つ空調を効かせたガラス張りの別空間でも作ればいいのかも。バカバカしい。
午後は先日古紙を引っ剥がした障子の次行程。軽トラの荷台で防虫塗装を。
扨、昨日朝から「蒲郡」の地がテレビで連呼されていました。
そちらで早朝に新幹線の線路上で起こった保線車両脱線事故の件ですが、在来線浜松・静岡駅の大混雑状況を報じていました。
あの混雑の中に自分がいたとしたら・・・くわばらくわばら。
最近はその蒲郡について記していますが、私が訪れるのは自家用車。以前はお寺のバス遠足もありましたがね。
昨日は竹谷松平の本拠について記しましたがそのスグ北側に竹谷松平の菩提寺といわれる全保寺があります。
墓域にはそれと思しき墓塔の存在は見受けられません。それらはこれより少々離れた地にあります。
ざっと観音堂の中を覗き見するなど墓域をブラつきました。
中でも印象に残ったのは板碑の集合に見える、画像②の五輪塔改の墓塔。
宝篋印塔の笠とその胴らしき材がベースとなっているのでしょう、その上に一石五輪塔、そのトップには後補でしょうやはり五輪塔の材が。
複数の墓塔がバラバラに逸失した時期があったのでしょうね。
それらを纏め集めて一つに重ねたというところか。
しかしあの宝篋印塔の部材、一石五輪塔は室町期を連想しますが。
2024年
7月
22日
月
民間所有地と民家に囲まれた竹谷松平氏の竹谷城
智曜日(勝手な造語)、やはり午前は法要。
行僧原の先ずご自宅ご仏前にご挨拶してから墓参し本堂での本法要という段取り。
原の墓地の上空は薄曇り、テレビで大騒ぎするほどの暑さは感じませんでした。拙寺境内とは違って蝉の声は遠く、鶯の声が長閑に響いていました。
「時間をかけてゆっくり・・・」ペース。法要終了後、庫裏で掛け時計に目をやれば13時前になっていました。
庫裏の居間の時計は気温を示していますが29℃。
その部屋には当然の如くエアコンを稼働させていますが設定は25℃にしても、指示通りの温度にはなりません。
好天が続く時の仕事はいくらでもありますが、直近の課題、本堂正面の北側障子2枚の張替えです。そけらは破けまくってボロ寺の有様を醸し出していますので。参拝者の子たちとネコによるものですからどちらも文句は言えません。
まぁネコならばまだしも、子供が面白がってそれを破く様を目の当たりにするのは少々心臓に悪い。
我が子ならぶん殴ってそのやってはイケない事を知らしめるワケですが、怒りというかどちらかといえば悲しい感覚を堪え、自ら言い聞かせます。「そろそろ張り替えろ」とのお達しだ・・・
ということで一番に酷いその2枚を取り外して水洗いしながら古い紙を除去。この天気ですからスグに乾燥してくれますので次の行程に入りやすい。桟の破損個所を補強するなどして25日の取材までにそれを仕上げようと思っています。
尚、その取材は例によって田沼関連です。
扨、蒲郡市内で蒲形城に続き、あの城郭大系本編で記されている城、竹谷(たけのや)城があります。
竹谷城 蒲郡市竹谷町 天文十七年(1548) 松平守家
「竹谷松平は氏は、信光の長男、守家を始祖とし、天文十七年竹谷の住人牧山喜三郎から七百貫の土地を買って竹谷に築城したという(天桂院文書)。
永禄三年(1560)五月の桶狭間の合戦以後、三河の諸将は今川氏と別れ、徳川家康に従った。竹谷松平氏も同様でこのために今川に人質として出していた四代清善の女(むすめ)は他の諸将の人質とともに吉田城外龍拈寺口で殺害されている。
清善はこののち元亀三年(1572)から遠江宇津山城を守り、孫の家清は徳川氏の関東移封後、武蔵国八幡山一万石に移封、関ケ原の役を経て慶長六年(1601)には三河吉田三万石の城主となったが、その子忠清が同年十七年に没し、無嗣除封となった。
しかし、同年、弟清昌に西ノ郡五千石が与えられ、帝鑑の間詰め・交代寄合として代々居住したのち明治維新を迎えた。
現在、城址一帯はみかん畑となり、本郭・二の曲輪が残るが形状は台地である。当時の曲輪もこの二曲輪からなり、居館は他の場所に置かれていたいたものであろう。
創築当時においては土塁を巡らし、小規模ながら建物もあったと推察され、当時の面積は現在でも残されているが、後世に土塁は壊され井戸の場所も明らかではない。」
竹谷城の目標は蒲郡市立塩津中学校。そちらの少々東側に②のような丘が。そちらが竹谷城址になります(場所はこちら)。
③ミカン畑側から回り込んで畑を突っ切り竹藪の手前に石標が。そこからさらに南側の斜面を降りると⑤⑥⑦。どうやら私は正攻法でない逆から上がってしまったようです。
しかしその「正攻法」は民家の路地の奥という感じで、わかりにくいものがあります。
城郭大系には土塁は失われているといった記述がありますが、南西側には空堀土塁と切岸を推定できる遺構が見受けられました。ただしこちらは民家の裏側ですので了承を得てから入らないと反則になります。
勿論、私はその無理な要望について民家の奥様に快諾いただいたことを覚えています。
まぁ何時警察を呼ばれたとしても仕方ない人相、恰好とは思いますが。
できるだけ怪しさを醸しださないよう明るく接することを心がけています。
⑨から三河湾方面を。イオン蒲郡店が見えます。
2024年
7月
21日
日
地表にはいられない? 生き物スゴイ 上へ上へ
午前中は法要。
お内陣の空気は「タダでサウナ風呂 アリガトウ・・・」の感じ。
きっと健康にイイはず・・・と思い、声をふり絞りますが。
西からの風は少々ありましたが、堂内の空気を清浄新鮮に回転できるものではありませんね。本堂は東に開口していますので。
またクマゼミシャワーの件、例年9時30分には朝の大合唱は一旦やんで静寂を取り戻すものですが最近はそれが1時間ほど延長されるようになったよう。
ここぞとばかりの大音声、少しでも・・・と、この盛夏を謳歌しているようです。
彼らは木々の上でお気楽にしていられるとは限りません。
地表の温度が絶えられず、涼を求めての行動か、それとも「食」の願望なのかわかりませんが、画像の物体が本堂前のメタセコイアに登攀開始。
私がちょくちょく遊ばせていただいている木ですが彼が上で待ち構え、下にいる人間どもの動きを鳥瞰していると思うと嫌な感じ。また手を掛けた枝にそれがいればズルっという具合に握り損ねそう。
それにしても驚かされるのは垂直の物体にあの棒の如く細長い体で登ること。その技を拝見しました。
体を恰も梯子の如くカギ型に変形して登るというもの②。
縦方向に樹皮が成長する木には体を横に接着して抵抗面を増やそうという作戦ですね。ストレスなく上へ上への姿は「なかなか ヤルじゃん」と感心しきり。スゴイ技です。
先日もコレより小さめの個体が出現、藪の中に消えましたが、結構にあ奴ら、境内に生息しています。
昨日はオリンピック代表を降ろされた女子体操選手の例を出し人間の「道具理論」についてその代替要員の存在と「私の死」の示唆について記しました。
彼女は当然に「道具」として機能していたわけですが、今回はそのチームに交換要員は用意されていたものの、その事案での交代は却下されたとのこと。
要は他の選手やらスタッフ、それらの成果を期待していた国民庶民に対して多大な困惑を惹起させてしまったのでした。
「タバコや飲酒くらいで 何が悪い」といった彼女を養護したい旨の意見もあれば「とんでもない」の不出場肯定派の声までいろいろありましたが一番に首を傾げたのは、養護の意見のうち、あのレベルにあるスポーツ選手(アスリートというそうです)はストレス、重圧との闘いでもあるのだから・・・というものです。
それは強烈なるストレスの捌け口として(禁止されている)喫煙と飲酒もやむを得ない・・・という主張。
それは甚だしい間違いかと思います。きまりごとの反則行為は別にしてそもそも飲酒と喫煙がそういったストレスというものから解放される一手になるものでしょうかねぇ。
19歳の未成年でそれらにそういった効果があるというのであればむしろその効果を期待しての常習性を推測、それに驚きます。また、そうであるならば医学的に証明していただければ有難いものです。
また一つ。
「ストレスがあったから仕方ない・・・」とはいってもその件メダル争いをするような選手たちに限ったことではありませんよ。
サラリーマンも学生もフツーの人達も坊さんも神主も、時に超絶ストレスに見舞われることだってありますから。
先般も記しましたが、やはり「お寺の子」の息子の友人も、神主になりたてのある方の息子もそのストレスで自死に至りましたからね。
強いストレスは「酒とたばこと女」に逃避する?
冗談じゃあない、甘い甘い・・・ただの増長思い上がりの部類でしょう。ストレスは最悪「自らの死」をもっての逃避を思考するものなのですから。
まぁアスリートの皆さんの「ハメを外すこと」がストレスからの逃避だったとして、結果ある意味その圧力からは開放されたワケで。
真に自身体調の事を考えてあげるのなら今回の結果はそれでよかったのかも知れません。
ストレスを理由とするならば死に至る前にヤメること。
それ肝要かと。
2024年
7月
20日
土
蒲郡上本町旧字「西廓」蒲形 五濁悪世の世だねぇ
昨日は本堂で新会館施工に携わる業者さんたちが集まり図面を広げて何やら懇談。私はノータッチ。
これによって初めて見積もりが出てくるのでしょうが、それはそれで恐ろしいことです。
オリンピックの会式間近というのに首根っこを摘ままれた如く日本に送り返された女子体操選手(19)とサッカーの日本代表の若者(23歳)の逮捕の件(ドイツ1部リーグ移籍もパー)、そして政治家に転身した元スケートの花形選手の話題が俄かにスポーツ界の話題になっています。
つい「五濁悪世の世だねぇ~」と呟いていました。
その世界にいて、これまであまり貶されることなくどちらかといえばちやほやと、「素晴らしい」的形容など多く散りばめられた環境で成長してきた人たちの件ですね。最近では「アスリート」などいう特別と思わす人たちの部類。
まぁこれまでホントの実力相応の評価がされてきたわけで当人の並々ならぬ努力もあったこととは思います。
引退後政治屋さん世界へ居所を変えてのその野心家と変わった方、それはつまるところ忘れかけていた「政治とカネ」のお話に戻りますので、いつものこととはいいながらアホらしさ溢れるところ。
アホ政治屋のオヤジの話はどうでもいいことですが前2者の若者たちは見ていて痛いものがありました。復活は並大抵ではないでしょうね。
一言で、月並みな言葉ですが「天狗になっていた」ということでしょう。社会が自身実力を承認してくれたということから「何をやってもイイ」という変ちくりんな錯覚が起こったのか・・・
承認してくれたその社会には実は厳密な決まりごと(ただし極、簡単で基本的な)があって自分がその大神輿に担がれていたことを忘れてついつい浮かれてしまったのだろうと思いますが、そういった知識、智慧を得ていなかったことにひどく勿体なさを感じます。
育てる側としても指導が行き届かなかったことを反省していただかなくてはね。親たちも自慢だった子の今回の不始末にガッカリのことでしょう。
そういったスポーツ選手の陥りやすい「天狗化」現象は今に始まったことではありませんが彼らの脳内には私ども宗旨の中心思想「他力」だとか「慈悲」についての感覚とは少々違ったところがあるのかも知れません。
今の地位こそ自分自身の類まれな運動能力と努力の賜物であって、「他に代わる者がいない」という自尊自負の血が溢れていたのでしょう。
そういう意味からすれば何とか一人前といえるまで成長した当家息子もどうお調子をこいて失敗するかわかりません。
若さ故、その思考はある程度は許容されるべきですが、結局はそれは大いに間違うのでは・・・と思うところ。
各その結果を招いてしまったのは一言で「自業自得」ではあります。
某哲学者の「道具理論」を拝借すれば、人間は他者その他諸物を道具として見るものであり、当然に自分以上に多くある他者の目からは「私も道具」であるということ。
先日は、私のヘマばかりの件をブログにて記したのでしたが、それなら「若さん(息子)に自分の葬儀を頼もうか」という私への叱咤激励と確実に成長してきた息子への期待、そして御当人の健康長寿について喜ぶべき言葉を頂戴しました。まさにそれなのです。
要は「スペア」が控えている・・・ということ。
何にでも誰にでも、血縁非血縁関わらず。
(私が消えても)どうにでもなってしまうというところです。
拙寺でいえば息子の代わりには従兄がいますし従妹の子供たちも控えています。いくらでも・・・
道具は使えなくなったら捨てられ・・・人間でいえば死のイメージもあり・・・新しいものに交換されるということですね。人で言えば「人材」などともいうではありませんか。
組織運営の「材」ですね。
代表の栄誉を得たそのアスリートの皆さんがよく「日本の為、応援してくれる皆さんのた為に」との弁を耳にします。
それはそのための「道具になりましょう」と言っているのと同じですね。
しかしそれはやはり詭弁であって「自分の為」以外の何物でもなかったことが大バレとなってしまったのが今回のこと。
「やりたいことをヤル それは自身勝手自由・・・」。
他力に生きた人はその道具理論についてある程度は「なるほど」と承ることがありましょう。
それは極論のスペア論である「我が死」を見据えて今を一所懸命に生きるということでしょうか。
法然さん、御開祖親鸞さん他、善知識、先達の皆々さんがそうですが念仏を通してそれら「まことのこころ」が蓄積できればうれしい価値ある人生だったと思えるでしょうね。
それは親鸞さんがおそらく唯円に託したであろうその思想の継承について歎異抄を拝読していて思います。
他力本願による称名念仏という「行」により「慈悲」(上記)の心が少~しづつ心の中に、自身気づかぬうちに蓄積されていくこと(金剛の信心を得る)について「阿満利麿」氏が仰っていました。
そこには(私のような)凡夫であっても特に2つの智慧が生まれてくるのだと。
①自他を平等に観る 自分中心の度合いが緩まって相手への
関心へと心が働くようになる
②人それぞれの違いがわかってくる 他者を尊重する
②の場合は他者を道具として見ることは否定(自分の思い通りに動かす)されますのでここですべてにおいての道具理論は通用しないことになります。
要は道具であるのは「私」であって他者に使われ利用されることを楽とし逆に他者は尊重するべきというのが本質的生き方なのかと。
尚、「道具」といえば清沢満之が「念仏は阿弥陀仏の慈悲を伝える導きの器(導器)でる」と述べたことを阿満氏は紹介していました。
(故人は仏弟子となって)「あとにのこれる人々を導く・・・」という拙寺盂蘭盆会法要の表白の件、まさに合致しています。
扨、図は蒲郡市の中心ストリート「上本町」(場所はこちら) 交差点。あの上ノ郷城の真南、不相城との中間地点に位置します。
例によって日本城郭大系から。
こちらの城は本編での記述があります。
蒲形城 蒲郡市上本町 永正年間(1504~21)
鵜殿又三郎長存(ながあり)
「鵜殿氏は長将(ながまさ)の時に上ノ郷鵜殿氏と下ノ郷鵜殿氏とに分かれ、永正末年に下ノ郷鵜殿氏は又三郎長将を祖としてこの城を構えた。
宗家上ノ郷城の落城後も松平(徳川)氏に属して勢力を保っていたが、又三郎長龍の時に下総国相馬に移った。
その後一時、深溝松平忠利が入ったこともあったが、慶長十七年(1612)に竹谷松平清昌が五千石で入封し、以後明治まで存続した。
城址一帯は学校や住宅地となり、わずかに残る土塁が往時をしのばせるのみである。
しかし、その土塁から考察して、比較的大きな居館城であったものと思われる。」
その記述の如く、道路と住宅地となった城址、特に中心地と指摘されている上本町交差点付近にはそれを窺わせるものは確認できませんでした。
ただ2件の「西廓」の字面は目にしました。
通りに面したNTT電柱標識⑤と近くの公民館の名称⑥です。
その二つのアイテムは案外と古い地名を知るにそのヒントとなります。また橋の名などもそうでした。
➆は⑥の近く。勿論住宅街です。
2024年
7月
19日
金
六栗陣屋址外観 石積みと門を拝見
梅雨明け宣言がされた昨日、雨天で先延べになっていた作業いろいろの件、大いに捗りました。
1週間ほど前から毎年恒例の「クマゼミシャワー」も始まっていますのでその応援団のもと・・・。
7月の盂蘭盆法要が終了したこともあって、溜まりにたまった花ガラ3袋を地頭方の処理場へ持ち込みました。
その日の一番の課題は庫裏のちょっとした大工仕事。
まぁうまいこと納得できる仕事が出来ましたがこれも天候が安定していなくては出来ないですからね。
まだまだ宿題は残っていますので~というかそれは永遠に・・・といった感じ~この季節の天気を楽しみながらすごさせていただきます。
扨、先日は六栗城その他の記載があった幸田町の広報誌を送付いただいたこともあり、以前ブラついた六栗陣屋について。
こちらについては不確かということもあって外観のみ。また現在、民家となっていますのでズケズケと中に入ることはできません。
ということで門前までと外周の雰囲気を楽しませていただきました(場所はこちら)。
門は私が訪れた際は改修工事中。こちらの門は移築されたとも聞きますが立派な門構え。地所は少々の高台にあって何より周辺の石積みと外構、敷地の広さにも圧倒されます。
地名としては「山屋敷」なる名称で、何やらかつての遺構を物語っていてやはり木々に囲まれている様子が窺えます。
最後の2つは西側裏手側からの図。
内部には円墳らしきボタ山も窺えました。
自宅敷地内に古墳があったとしたら楽しいかも・・・
元は夏目一統の屋敷があったと推測しますが・・・
2024年
7月
18日
木
南御堂(難波別院)と実如展 竹箒に刺される?
当方奥方は気が向くと竹箒を持ち出して落葉を集めています。
先日はその作業中の奥方に見送られ外出。雑務をこなして寺に帰ると玄関前にその竹箒が「ブン投げられた」が如く放置されていました。
「無作法者め」とその様を訝しく思いつつそれを片づけてから庫裏に入ると・・・
奥方は「ヤラれた」と言いながら痛いだの痺れるだのと掌へのアルコール消毒の真っ最中。黒い毒針も抜いたと主張。
もう掃除はヤラない宣言まで。
竹箒に「穴が」開いていたというので私はピンときましたが、本来それ(タイワンタケクマバチ)は刺さないはず・・・。
余程腹が立ったのかそれともその穴に別の生き物が生息していたのか・・・1日経って痛みも腫れも消えたようですから勉強勉強・・・。
竹帚の握り部分には注意が必要ですね。
画像は先般送られてきた大阪は南御堂(難波別院)の紹介冊子の表紙と実如展のパンフ。
後者は名古屋の期限がある展示会ですから、私は既に諦めムード。実如さん(→Wikipedia)は蓮如さんの子でパンフにあるように顕如さんに繋がる本願寺の戦国期ドサクサを過ごした人ですね。
南後堂はご存知「御堂筋」名称の発祥の東本願寺真宗大谷派難波別院(→Wikipedia →サイト)。
こちらは期限がありませんのでいつかまた大阪主体のバス遠足で皆さんをお連れしようかと。
大阪の夜をほっつき歩くのも悪くない・・・
2024年
7月
17日
水
不相城址には「城」が建つ 蒲郡クラシックホテル
今、左腕、肘の擦り傷と腰の打撲の痛みが少々。
いつものパターンですが玄関でサンダルで躓いてぶっ飛んだからです。
家の中は素足ではありません。
スリッパでなくサンダル履きですがその「玄関+サンダル」の構成は私にとって鬼門となっているようです。
そしてそれはまず両手が塞がっている時ですね。
数ミリの段差に蹴躓いて宙を飛んだワケですが、その数秒の間
①このまま着地したら「ヤバいことになる・・・」ということ(頭の辺りに棚がありその上には色々な物が載っている)
②そして了見寺のご住職の災難の件(同じような状況)が同時に頭をよぎりました。
後頭部、首の部分からその棚の角に当たりましたが腰→腕→首の順番で倒れたため、肝心なその首の負傷に関してはセーフでした。
手に持っていたドライバードリル等も無事。
今回は・・・、イヤ「今回も」ツイていた・・・おかげさま。
今度転んだら・・・サンダル履き、やめよう・・・
それにしても風呂、トイレ、階段、玄関、庭・・・ヤバい場所とは・・・
まさに「自宅」。
何気ない日々の連続にリスクがありますね。
私など演台に上がって演説するワケでもありませんし。
扨、昨日の蒲郡の竹島の海岸を見下ろす山は地元では城山。
かつて不相城なる城があった場所ですね(場所はこちら)。
今は蒲郡クラシックホテルの敷地ですが、上がってみました。
まぁ、開削によってそれらしき遺構を想像できるものは・・・よくわかりません。
イメージとしては天守閣?を連想する建物はありますが。
この城址ホテルの概略はこちらのブログに詳しく記されていますのでご確認を。
尚、いつもの日本城郭大系には「蒲郡市竹島 不相鵜殿氏の居城。現蒲郡ホテル一帯が城址」と。
2024年
7月
16日
火
幸田町広報誌をいただく 六栗城址と明善寺 蒲郡
さすがに「天気 良くな~れ」は図々しいことかと思っていましたが昨日の法要もうまい具合に予想が外れて雨はまったくなし。それも陽射し付き。
この三連休の法要のうち雨傘が必要だったのは土曜の19時からの盂蘭盆会法要パート2のみでした。
昨日午前の法要はご納骨がありましたので、やきもきさせられましたが終わってみれば万事OK。
何せ事前の予報では「連休は大荒れ・・・」でしたからね。
例年は本堂正面左右にコンパクトな扇風機を置いていましたが「まだ大丈夫だろう」とその設置を怠っていたところ、昨日の法要で堂の中央近くに着座した施主が「汗が止まらなかった!!」とのご指摘。
大変申し訳なく思いました。反省。
お昼は直前にお斎のお誘いを受けましたのでマスクで隠れていた無精髭を慌てて剃ってからその会場に向かいました。
最近では滅多になくなった縁者多数集まる法要でした。
「お斎に同座するならマスクは初めから不要でした」とその言い訳をした次第。
扨、先日は二村氏よりお便りが。
抜粋して転記させていただくと・・・
「六栗城址の石碑は、岡崎市岩戸町の東照寺の栗木慶子住職が 夏目家の子孫の後裔という名目で出資されました。
石碑の周辺に芝生や草花を植えて、看板を作る作業が終わった後幸田町に史跡公園として寄付することに・・・」
また明善寺にいても宗教法人解散の件が追記されていました。
「夏目氏の一族で明善寺を知っている人には酷ですが時代に取り残されて再建は不可能」・・・
その件は私も代務寺院の件まで承知していました。そうなるといよいよあの本堂が解体されるのかと思いますがそれを想像するのは辛いことです。
そして「広報幸田」と三遠研機関紙「さんえん」86号を添付いただきました。
その幸田町発行の広報誌を眺めていると、幸田の立ち位置というものを再確認。
岡崎市と蒲郡市の間にあってどちらかといえば蒲郡との関係性を深く思いました。
私ども遠州人にとっては岡崎から南下するというのが幸田であり、どちらかというと蒲郡は行き易くないというイメージがありましたからその広報誌の内容は少々意外。
なによりも三河湾からの恩恵が期待できますから岡崎より蒲郡といった雰囲気が漂っていました。
とはいえ蒲郡にはかつて拙寺のバス遠足(藤原俊成像)にも訪れたり、上ノ郷城(またはこちら こちら こちら こちら こちら)などブラついたことを記していました。
かねてよりぼちぼちあの辺りにはお邪魔させていただいています。
画像は藤原俊成像と竹島の図。蒲郡クラシックホテルからの図
も。
2024年
7月
15日
月
相良灯ろう流しは今年8.15でお終い 富士市須津より
朝は雨。
午前10時からの法要でしたがしはらくして雨は完全に止んで、それだけでなく晴れ間まで広がりました。
とにかく墓参タイミングでの晴れは嬉しいことです。
午後からは富士市須津からのお客様。
午前中から平田寺→般若寺と廻ってから拙寺に立ち寄るというもので、史料館の長谷川氏がその三寺の案内人でした。
事前にその予定を聞いていたため、私は史跡研究会に新しく入会していただいたお二人に今後のこと(来年の繁忙?対応と会の存続)のために「研修と称して」同行させていただければ・・・と提案させていただいていました。
長谷川氏も了解していただいて当日を迎えたわけですが、お二人に加えて藤枝から会の先達、増田氏もいらしていました。
ただし増田氏は「こんなに暑いならもうムリ・・・」と。
相良はそれだけ晴れて陽射しが強かったということです。
来年は田沼意次の退場(大河ドラマ 失脚と城の廃却)が5~6月として・・・
「7月~8月の案内は(依頼は無いかも・・・)キツイのでヤメにしたい」という本音が出ていました。
さすがにツアーの依頼は先方次第ですからね。
番組の脚本もあってどこまで相良が引っ張られるかにもよります。よってどうなるかなど予想もできません。
あの元の神奈川県民としてとても懐かしいバスの装飾デザインを見て遠方からの来訪がわかるというもの。
こんなことが続くとすれば有難いことです。
墓参の御門徒さんから「一体何が始まったのだ・・・」と問われましたが。
尚、私は午前の法要の「声出し」でいっぱいいっぱい。
ということで午後の案内同座はパスさせていただきました。
そもそも私の口出しなどは不要ですし・・・
扨、恒例相良灯ろう流しの案内ポスターが届けられました。
その件、さすがに驚かされましたが「今年で最後になる」とのことでした。
ここ数年、雨にたたられるなどその苦労話は耳にしていましたが~準備と撤収は当然ながら降雨増水につき灯ろうの川面の設置や回収・・・~それは少々命がけチックであって「若さ」がなければできないこと。そして何より頭数が揃わなくなったといいます。
それらすべてが減り続けもはや継続困難と判断となったようです。先般相良高校生のボランティアが出ていてすこぶるその継続性に期待を持たせたのでしたが。
何事も衰微に抗いたくとも「人がいない」では仕方がないのでしょうね。
その「人がいない」という語を聞くと蓮如さんの御文を思い出します。
大経の「易往而無人」(往き易くして、人無し)」からですね。
御文は二帖七
「大経には易往而無人とこれを説かれたり
この文の意は 安心を取りて弥陀を一向にたのめば 浄土へは参り易けれども 信心をとる人稀なれば 浄土へは往き易くして人なしと言えるは この経文の意なり」
信心・・・とは私の「まことのこころ」ですが、あくまでも「私の・・・」である必要があります。
要は他者・・・教祖、エライ人、時に両親・兄弟縁者に強要されるものではないということ。
そしてそれは「(私自身がその思想、教義に) 納得できるかどうか」です。
よって、納得していないレベルで安楽浄土ばかりに目が向いている人が多いということを嘆いている段です。
今の変てこ集金宗教による各家庭崩壊の例はその個人を無視した「強制」(カネ出さないと地獄に堕ちる・・・みたいな)に問題があるのですが。
霊だなんだのの自分でも知るはずがないようなバカバカしいとしか思えない大層なヨタ話を並べ立てて老人や子供等気弱な立場の者を脅したてるところ、傍観しているだけで不快にさせます。それに納得できない方たちは早々にその件の悪だくみに気付いていただきたい・・・
私は実際にその不快を親戚から受けて縁を切らせていただきましたがね。関わるとロクなことがないので。
昨日は例の一本足のヤマバトがやってきました④。
きっと樹上から私の動向を監視しているのでしょうね。
ハトも昨日の陽射しは有難かったでしょう。
片足で立つのは疲労が激しいのか虫干しを兼ねてコンクリートの上にベタっと。
史跡研究会の皆さんが帰られたあと、彼のために準備してあるコーン主体の穀類を「お待たせ~」といいながら・・・
片足のハトなど自然界では淘汰される運命にあるのでしょうが、私は今のところ彼のスポンサーとして名乗りをあげています。
2024年
7月
14日
日
弥勒寺後堂 聖観音菩薩 平安後期 偏旁冠脚
午前10時からの盂蘭盆会法要の時間は予報通りの雨天にはならず、お日様まで顔を出してくれました。
雨傘ではなく日傘をさして来た方もいらしたほど。
しかし昼以降にはまとまった雨があり夜19時からの法要が終了するまで降り続いていました。
とにかく7月の盂蘭盆は無事終了です。今後8月の法要までは各家単発のご縁が土日中心に。
来週には梅雨明けといいますから気合を入れていきます。
昨日の私のお話は年々増えている認知症について。
テーマは「生老病死」の四苦のうち基本「おまかせ」することにはなりますが「老」についてだけ少々抗おうというものです。
認知症予備軍の軽度認知症がその後ろに控え、さらにその予備の予備として私が並ぶ図です。
寿命と健康寿命のギャップ~約10年~をゼロに近づけようとの試行、寝たきり状態にならずに寿命を全うするための方策を、昨日記した映画「ものすごくうるさくて、ありえないほど近い」の主人公の少年が発した
「何もしないでいるよりも(動いて) 失望した方がマシ」の
台詞を交えて話を進めました。
寝たきりになったり介護者の手が必要になってしまうには色々な原因があります。
脳溢血や大病を患ってのそれにはどうにもその事前対応は難しいでしょうがその他の主な要因といわれる①骨粗しょう症②筋力低下③認知症についてはそれは個人差というものがありましょうが、事前にその対策について念頭に生活すれば「健康」(ゼロに近づける)の維持は可能であると。
その①②③は関連していて後期高齢者ともなればその全部を患うなどの頻度は高くなります。そして①②は軽度であっても③認知症が主たる理由というものが多いということで、「認知症にならないために」頭と体のすべて、使わない部位がないよう心掛けた生活の推奨。
外を歩いて(筋肉を落とさない)会話(口を動かす)、食べる(栄養維持)、唾を飲み込む(誤嚥性肺炎対策)といったカンタンな習慣とそれらができないときはお内仏に向かい正信偈を声を出して拝読しよう、の推奨(口周りの筋肉鍛錬と唾の飲み込み訓練)でした。
扨、大盤振る舞い、重文系仏像接写OKの弥勒寺について記してきましたが一度は行って損がナイお寺。
これからそういうお寺が増えれば嬉しい限り。
ネット口コミ等全盛の時代そのお寺のやり方は方向性としては悪くないですね。
何人も警備員を配し撮影禁止という旧態依然の寺の考えを掲げ続けることが正解なのか考えさせられるところ大です。
昨日に続き弥勒寺後堂には今一つ平安後期作といわれる聖観音菩薩の立像があります。
無指定の様ですが、検証が進めば他の仏像たち同様にもっと陽の目を見るかも知れません。
私は次回訪問する際は重文の十一面観音の天冠の諸仏の一つづつを近接してみようかと。
また後堂の聖観音像の近くには別の十一面観音の諸仏だろうと思われる仏たちが並んでいました。
最後の画像は堂内に掛けられた画。
年号の安政の「政」について左右が上下に。
叔父の談、偏旁冠脚(へんぼうかんきゃく)の組み合わせの異体字とのこと。
「裡」→「裏」等もそれでむしろこちらは「裏」の方がメジャー立って使われるようになったもの。
2024年
7月
13日
土
弥勒寺後堂 釈迦涅槃図 理源大師 倶利伽羅龍王 三鈷
時折激しい雨。
湿気と蚊の襲来の中、奥方は本堂で盂蘭盆会の準備。
私は庫裏にてやるべきことを淡々と。
雨予報の盂蘭盆会法要となるようですが、お手柔らかにお願いしたいところです。
先日、映画「ものすごくうるさくて、ありえないほど近い」を視聴しました。
アスペルガー症候群の検査をし「不確実」と判定されたことがあるニューヨークの男の子があの9.11のビル崩壊で大好きだった父親を亡くすことをきっかけに多くの人たちとの出遭いと変化していく彼の思いについて綴られた小説が元ですね。
父の遺品の中から彼が偶然見つけた「鍵」がその映画のまさにkeyとなるアイテムになりますが彼は少しの手がかりを見つけてニューヨーク中をその開けるべき何かを求めて探し回ります。
結局その目的はやはり偶然に行き当たりますが自身の希望していた結末とは違いました。
映画のラストに彼が語った言葉に「何もしないでいるよりも(動いて) 失望した方がマシ」という言葉に私は合点しました。
私の目的や希望というものは叶えられるとは限らないし、むしろ挫折する方が多いでしょう。
しかし何も動くこともなく、手をこまねいて考えているだけならば時間が無駄。
スグにでも何かに着手し喩え目的の結果が失望に終わったとしても必ず得るものは有る・・・ということでしょうね。
彼にはたくさんの経験とたくさんの人々との出遭いと交流がありましたし儚くとも希望を持つことの大切さを示唆しているその言葉。特に母親との絆も・・・
しかしまた、何故にしてあのようなタイトルにしたのか・・・
扨、弥勒寺の堂内の諸仏(昨日)について記してきましたが、あの後堂~薬師如来の裏側~です。
あの寺は全部見せてくれて、すべて撮影可能というところがスゴイのです。
まず釈迦涅槃図の軸にどこから見ても睨まれている感漂う理源大師の軸に倶利伽羅龍王。
そして三鈷杵は真言の寺らしいグッズ。
子供のオモチャの如く見えます(失礼!!)が、その系統の寺などでは普通にお目にかかれるもの。
ただそのカタチの山だったからと三鈷寺などの名称もありました。
元は護身用の武器と聞きますが、今それは仏具。
自身の煩悩から護るという意味の様。
それでしたら私には無縁でしょう。
煩悩を抱えたまま念仏して往生すること・・・ただそれだけ。
2024年
7月
12日
金
ブラタモリ登場 弥勒寺の役行者+不動明王と曼荼羅
「降る降る予想」に反して当地は殆ど降らず。
一昨日の夕刻、カラカラに乾いた植木鉢の植物たちに「もうしばらく待って」と予報の雨を待ちました。
それが朝になっても降雨はナシで結局昨日の朝一番の仕事は水やりから。その後、多少のお湿りはありましたが、どちらかで言われているようなまとまった雨はありませんでした。
夕刻17時から開式の法要がありましたが、当初の「覚悟」はまったく不要。ただ堂内は暑いだけです。
うまいこと蚊の襲来もありませんでしたので終わってみれば良き7月の良き一日。
昨日来訪された方は元の牧之原市民。家伝来の茶畑を手放すことが決まってその所有権移転の下準備に来られたそう。
その金額を聞けばひっくり返りますよ。
素人には考えつかない数字。
「600~700坪ある」とその方が仰っていましたが金額は「1万円」ポッキリとのこと。
今、住宅地で5000円/坪を切るといわれていますが、茶畑だとその有様です。
農業委員会が転用について管理・監視してますから、特にその売買などうまいこといかないよう。
茶畑は茶畑・・・そんな面倒なことを言っているから放置茶畑の森ができるのです。
行政でも国でもその辺りのところ何とかできないものでしょうかね。
農家以外の一般市民が畑を開墾したり市が買い取って市民農園を作って区画を販売するなり・・・旧態依然の感覚、本当に腹が立つ。
扨、昨日記した弥勒寺の十一面観音の奥にあるのが役行者像。
私はあまり御縁のないものとして興味を向けないものではありますが、こちらを撮影させていただいたのは、こちらの堂内の諸仏数ある中、唯一NHK総合地上波に登場したことがあるからです。
それがブラタモリ(伊賀の地形と伊賀忍者の回)です。
要は伊賀忍者のルーツがこの像、役行者(役小角)-山岳修行者(修験道)-だったという推測からです。この像は古さ大きさとも周辺随一のものだからでしょうね。
山間部を我が庭の如く熟知し、またそのグループの情報伝達力に長けていそうなところ、まさしく忍びのルーツだったかも知れません。
その役行者像のお隣には不動明王とそのバックには曼荼羅が。
2024年
7月
11日
木
十一面観音の天冠台 + 持国天像 弥勒寺
朝の一瞬の間はお日さまの姿がありましたがしばらくして雲が張り出して以後ずっと怪しげな天気。
予報によれば15時には降りそうな感じ。よって14時目標で地頭方処理場に向かうことにしました。
満杯の花ガラ袋に雨水が溜まることは避けたいところですからね。
酷暑続きだったせいか墓参の方は少なかったようで、前回の雨続き以前のものも袋の底に「堆積」していました。
雨水にも浸ったようで腐食が進んでいて、もっと早く処理しなければならないレベルでした。
サボっていたことは反省しますが・・・地頭方まで行くのはなかなか面倒。ドラム缶に放り込んで燃やしてしまえばカンタンなのですが。
そして先般中日新聞にて牧之原市の宣伝紙面が登場したことについて記しましたが、数日前にはお世話になっている東京の代々木上原在住、富谷国民学校(学童集団疎開)の桑野龍輝氏より電話が。東京新聞を「見たよ~」と。
例の牧之原市り宣伝紙面は中日新聞と東京新聞の二社に入っていたことがわかりました。そちらにも驚かされましたが、ハリのある声の桑野氏は90歳、お元気そのものでした。
「今度また顔を出しま~す」には圧倒されました。
すると静岡の秋野氏からも同様の電話がありましたが、静波の笠原氏はその東京新聞を持参くださいました。
「何だってそれを?」と聞けば「うちはずっと東京新聞」と。
てっきりその新聞は東京だけと思いきや・・・
牧之原市、というか今回のそれにはスポンサー各ありますが、そういった新聞紙面に拙寺が登場させていただくこと、これまた僭越至極。
扨、先日の弥勒寺の重要文化財指定の聖観音菩薩に続いてもう一体の重文を。
聖観音菩薩の対にある感がありますがやはりそのお隣にはあの増長天に変わって持国天が侍ります。
高さ174cm。かつては彩色されていたという十一面観音菩薩でやはり平安時代後期の造立といいます。
船形光背も台座も例に漏れず後補です。
欲を言えば後ろからのそれを拝見したいものでしたが、天冠台の小仏を近接して拝めたことは嬉しい限り。
最後の画像は7月5日の東京新聞から。
2024年
7月
10日
水
新札拝見と散策相良海岸 海開きは7月12日
盂蘭盆会のこのシーズンは平日にも法要がぽつぽつ入ります。
昨日午前も法要がありました。
墓参のあと境内にはハイビスカスが咲きまくっていましたのでついつい花談義となりました。奥方から「ハイビスカスの先生」とバカにされているわけですが、それに気を良くしてのこと。
ちなみにハイビスカスは冬期の養生が大変ですから、そのバカバカしいほどの労力について指摘しているのでしょう。
ハイビスカスの生産農家としては今が売り時、そして適当に冬場に枯らしてもらってまた翌夏に購入してもらおうとの流れがあるとは思いますが、私は出来る限り彼らには生きてもらおうと腐心します。
花を咲かせたときの美しさに力強さそして彼らが夏を好むところがまたイイ。
何より彼らの良きところは生命の更新が挿し木でできるというところでしょうか。
冬の苦労ついでに今年は少し増やしてみようか・・・その辺りの増やし方講釈もそちらで。
施主が帰り際、1000円札を取り出して「記念にどうぞ~」と。
見ると先般発行された新札でした。テレビで見ることはあっても実物は初めて拝見しました。
戴くのでは申し訳ないので両替を・・・と申し出るとそれには及ばないとのことでした。
その方はこちらには5000円と1万円札があるとさらにその2枚を提示されました。
これから皆に「見せびらかすのだ」と仰っていましたので、それなら1000円札が無ければ不完全・・・。
私は3枚勢揃いを見せてあげてください・・・と携帯撮影のみということになりました。
昼食後は一昨日同様、昼寝。
一昨日はエアコンの部屋で寝たためか体調不全に陥ったため昨日はノーエアコンで。
やはり暑すぎたのか脳内も体も強烈なだるさ。
日没前に水やりをしますが、酷暑と言ってもやはり蚊の来襲がありました。あの羽音を聞くだけで刺されていなくとも体中が痒くなりますから、不快な連中です。
そして体調不良の際は海を見に行くに限ると相良海岸に向かいました。
一昨日の海難供養の法要に続いて連日になります。
久々歩いて気づいたこと。
1 砂浜はかなりキレイ。石ころゴロゴロも見られません。
2 風は涼しく昼寝をするならココ。デッキチェアーが欲しい。3 境内の超絶不快な思い(蚊)は絶対にありません。
②は日没の様。相良だとお日さまは海に沈みません。
海に沈む様は御前崎へ。③は樋尻川の河口。昨日はひょいっとばかりに飛び越えることができますが、日によっては川幅が広がっています。④たった1件となった海の家が見えます。
⑤は御前崎方向。まだ陽が差している場所がありました。
⑥は監視員待機所。今年は海難供養と海開きの日にちにタイムラグがあるのでした。
その事情については不詳です。
2024年
7月
09日
火
重文聖観音菩薩 +増長天 弥勒寺 はつかつを
7月8日は当家勝手に「那覇の日」。
語呂合わせですがハッピーディ、心身とも前向きとなる日。
昨日は朝から相良海岸の海の家へ。
昨日の法縁は相良仏教会御一同が揃う海難供養の日でそれ一つきりでした。
気楽なものですがさらに気分を良くしたのは、天気良好、静かにそして青く広がる駿河湾と微風。
思わず「サイコー サイコー」と沖縄の若者たちがはしゃぐように心の中で・・・
帰宅してしばらく御門徒さまより鰹の差し入れが。
勿論「はつがつを」。奥方と1本まるごとにも関わらず例の台詞「鰹は半分もらったよ」。
先般、「道の駅はくしゅう」の山口素堂の歌碑を記しましたが
これで本年の「初夏」の代表が揃いました。今といえば殆ど盛夏の感がありますが・・・
尚、ホトトギスは夜更かしして外で耳を澄ませば聞こえてきますし、朝の境内でその青葉は目に入ります。
そして夜間のテレビ番組、『大追跡グローバルヒストリー』は初見の事で楽しく視聴。少々お笑いを混ぜ込んでうざったいところがありますが。
ガスパル・フェルナンデスと福地蔵人(ルイス・デ・エンシオ)
ハンデ・パエスなるメキシコの人の名を知りましたが、前2者は日本人です。
特にフェルナンデスについては驚きでした。
彼のことを記す文書がメキシコに残っているということ。
そもそも彼は豊後生まれだったそう。
天正10年(信長の死)以降、一時的に戦乱状態に陥ったその地で村が襲われ、幼少の彼は誘拐され長崎の奴隷市場で売られたと。
それを仲介したのがイエズス会の神父だったというからこれまた驚きでした。
洗礼を受けさせスペイン系の名前に変更、彼を買った主とメキシコへ行ったというところまで。
彼がメキシコでどういう暮らしをしたかは不詳ですが、イエズス会はやはりヤバかった。
信長はその宗教を優遇しましたが、秀吉は毛嫌いし、家康は完全排除。
政治家が自らの利権の為にそれを活用すれば庶民が酷い目に堕ちることになりますね。
明智光秀、そして殿(家康)、感謝しても感謝しきれない。
日本人はバラバラになって世界中に散っていったかも。
もし信長が生き続けていれば、日本の農村、弱者は奴隷貿易の商材として海外に送られたことが継続していたかも知れません。
キリスト教を拒絶(禁教令)した江戸期の政策は一部に悲劇の歴史をもたらしましたが、ここで改めてそれに感謝しなくてはなりません。悪くなかったと。
イエズス会は洗礼とはいいながら人身売買によっての収益と彼らの国益に絡んでいたということ。おそろしや・・・
尚、福地蔵人は支倉常長の使節団の一員でメキシコで船を降りた
とのこと。
扨、昨日の弥勒寺の弥勒如来。その手前には重文指定の聖観音菩薩像があります。
高さは180㎝でスリム。平安後期の作と。
衣の彫りもリアルですが額の白毫は水晶が嵌め込まれています。やはり台座は後補です。
そのお隣が無指定ながら増長天像。
この大きいとはいえない堂内に大き目仏像が「一堂に会する」図は見事。
2024年
7月
08日
月
弥勒寺本来の本尊 弥勒如来 三重県指定文化財
午前の法要。昨日同様お内陣でのお勤めは体力を消耗しました。外陣で参拝着座の皆さんもさぞかしの苦痛を味わったことでしょう。
障子を開けて空気の流れを作っていましたが、内陣は燈明の関係で、閉鎖空間になります。
法要が終わってしばらくすると、静岡でまた新記録。40℃超えといいます。
一昨年だったかと思いますが、私は浜松でその数字に遭遇していますが、一言この地球はぶっ壊れはじめた感。
もう止まらないのでしょうね。
個人レベルではどうにもならない、後戻り不可に思える世界に突入してしまったのかも知れません。
仏たちも「しょうがないねぇ~」と腕組みしながらため息をついているところかも。
要は人間の「自業自得」。
やりたいことを自由にやってきたそのツケを未来の子供たちが支払っていく構図かもね。
一昔前には聞いたことも無かった「熱中症」の語が日々飛び交うようになり昨日も午後、境内で植木仕事をしていればお参りの方からその語をもって「お気をつけて・・・」と声を掛けられるようになりました。
私の場合は片手間お気楽仕事ですからそれに関しては別段大したことはありませんが・・・
冷蔵庫の冷茶をがぶのみして「平チャラだよ」などとニヤけていれば「お前が熱中症で死んだとしたら・・・みんなであざ笑う」(熱中症で倒れてみろ・・・)とのこと。
アレばっかりは自己の体調管理、人の忠告もありますがクールダウンする方法はいくらでもあるはず。
年配者と子供はその自己判断がしにくいのでケアは必須ですがね。
一昨日は法要不参加の方について伺いましたがやはり熱中症だといいます。その方は若い男性でバイクのライダーですが、炎天下に(鎧の如く)ライダースーツにヘルメットで身を固めてのツーリング。体調異常に陥って家族にヘルプの電話を入れたそう。
バイクは近くのバイクショップに預かって頂いて帰宅、回復を待ったそうですが、今時バイク乗りもまた厳しいでしょうね。
私はどんなに蚊にヤラれようが半袖仕事ですが、昨日は蚊の襲来は軽微。思わず仕事が捗りました。
蚊奴らは酷暑が3日も続くと産卵と羽化の環境が急激に悪化するのでしょう。ざまぁみやがれ。花入れの水は熱湯化。
尚生花は1日もちません。奥方はそれに悲鳴をあげていました。
扨、弥勒寺の本来の寺の名の旧本尊という「弥勒如来」が昨日の薬師如来の脇にありました。
弥勒といえば兜率天とか弥勒浄土等本山御影堂門ほか他所いろいろな出会いを記していますが(最近では室生寺弥勒菩薩)、今度バス遠足で行く興福寺北円堂にも弥勒如来(鎌倉期140㎝)がありました。そちらは国宝指定です。
私も成瀬藤蔵正義の妻の名が「勒」さんだったこともあり親しみというものは湧きますが、その弥勒には一つ疑問が残ります。
散々私が出会ってきた弥勒菩薩、こちらでは「弥勒如来」となっています。
一説に違う仏であるとも言われますが、弥勒菩薩といえば半跏思惟像の姿が御馴染みですが製作年代が奈良時代以前と、いい時代が下って「如来」に昇格しているといった感じ。
弥勒信仰者にとって菩薩→如来は大いにその思入れから名称変更の件、「あとちょっと」・・・大いにわかるような気がします。
詳細は弥勒菩薩でググっていただければ。
昨日の薬師如来といいこの弥勒如来といいそもそも台座が後補であり、慌てて移動した感が残ります。
正式に移設するとなれば、以前の須弥壇等、付属物一色を伴うものです。
やはり、信長勢襲来の際、慌てて仏像を逃がしたのかも。
こちらも127㎝と旧本尊だった威容を感じます。
仏像の身長の件多少の違いはあるものの今まで馴染んでいて寺の名にもなっている弥勒を脇にし、薬師如来を中央にして本尊とする意味も今一つわからないところ。
大概の弥勒のイメージは菩薩であること、格上の如来の登場で脇に追いやられた・・・などとも考えてしまいます。
また建立は平安後期から鎌倉初期ということですが、やはり三重県指定文化財になっています。背後には曼荼羅が掛けられています。
薬師如来も弥勒如来も台座や光背の不完全が国の指定にまでに至らない理由になっているのでしょうか。
2024年
7月
07日
日
弥勒寺という名でありながら本尊は薬師如来坐像
午前・午後のダブルヘッダーそして+お寺関係のネット会談。
息子はもっと大変、神奈川県中部+西部の法要のダブルに加えて横浜で通夜というから移動距離もさながら若くなければやっていけない。よくやるよって感じ。
最近、彼は仕事がナイということ、体が鈍るからということで夜間の仕分けのアルバイトに出向いていましたが、昨日に限っては本来の仕事が大忙しの様。
前向きに依頼された法要をこなして行く姿はまぁ天晴れということで。
ちなみに映画ミッション・インポッシブルの新しいバージョン(クリミア半島の地名セバストポリの名を覚えさせていただきました)の中でCIAのエージェントが上役から「郵便の仕分場に仕事を変えてやる」のような台詞がありましたが、彼は私と同じ、どんな仕事でも平チャラでやるようです。
プライドなど何の役にも立たないことを知っています。
その手の肉体単純労働系のお仕事の件、父も祖父も絶対にやらなかったものでした。
まぁこの仕分けの仕事が彼の初めて「人に使われる」仕事。
それにしても持つべきものは友(京都時代の学友)です。
その友人の超繁忙のお寺のお手伝いに出向いているワケですが(勿論先方のお寺の名前で)何事も経験です、先方から「もう結構です・・・」の宣告を受けていないということは今のところデカいポカはやらかしいていないということで。
扨、昨日の弥勒寺、私が来年のバス遠足の立ち寄り候補地に挙げる理由は、お堂内部の仏たちに驚かされたからですが、ただの
1コイン拝観料のお寺ではないということ。
何より堂内は写真撮影OKというところが驚き。
ありがちな権威あるお寺とは違うところですね。私が遠慮がちに遠目から撮影していると、「さぁさぁもっと前に」という具合に背中を押されます。
こういう機会に画像付きで宣伝されれば、お寺の存在が広がりますからね。カタいことばかり言っていてはダメです。
それにしても何故にしてこちらに、どちらの寺でも本尊クラスの仏像が見えるところは不思議です。
①信長の蹂躙に見舞われた地であって如何にして仏像たちが無
事だったのか。
②そもそも彼らはどこから来たのか(当初からのものではない?)
ですね。
信長との戦闘ではある程度の準備期間がありましたから事前に山の中に隠したことも考えられます。また仏像が元あった場所についてあの毛原廃寺(またはこちら)からという説がありますね。
それならば毛原廃寺が何故にして取り壊されたことなども疑問には残りますが、一応の説得力はあります。
画像は本尊の薬師如来坐像。
寺の名が弥勒寺なのに・・・の今一つの不思議があります。
台座と光背は後補とのことですがこれだけの大きさ(143㎝)の仏像で製作年代が平安後期、それでいて三重県指定文化財止まりの不可解。
当然に重文扱いとされてもいいような仏像ですからね。不思議だらけ。
薬壺に菊の紋、通常はここまで近づいての撮影はできませんからね。緊張してうまく撮れなかったことは反省点。
2024年
7月
06日
土
天正伊賀の乱 蹂躙された伊賀名張 再び弥勒寺
蚊対策をして境内作業少々。継続的にはヤル気がおきないような空気と蚊。
対策と言っても蚊取線香と防虫スプレーの塗布くらいで服装は半袖軽装。長袖など着る気にはなれません。
蚊どもから絶対に逃れることはできませんね。結構ヤラれました。靴下をもう少し長めのものにすれば良かったか、反省点。
奥方は法事用の生花のセッティングを本堂脇の水場で汗だくになって苦闘していたようですが、一時気が付けば10匹近い蚊が手足に取っついていたと。
蚊への耐性は結構強いようで天晴、文句を言うことは暑さのことだけ。
一番イラつくのは「生花のもちが悪い」ことだそうです。
スグしおれる・・・と。
私は境内で本堂正面左のメタセコイアの枝払い。数年ぶりの仕事でした。
本堂側に突出して屋根に接触している枝葉を取り除きました。
風が吹けば本堂の雨どいを壊しそうでした。
メタセは材が柔らかく伐りやすいこと、幹からの枝が段々と生えるためハシゴ要らずというのがイイですね。
私の腰ほどの高さで植木鉢にあったのが20年ほど前、成長が早いのもスゴイ。
午後、メールにて「中日新聞見た~」と。
息子が横浜にて法事があるとのことで寺に立ち寄ることになっていましたのでそれを購入してくるよう頼みました。
そこで初めてあの取材撮影がコレだったということを気が付いた次第。
2023ミスユニバースの宮崎莉緒氏が牧之原市を案内するという企画でした。滅多にないことですので寺の掲示板にしばらくの間、貼り付けておきます。
扨、先日記した名張の弥勒寺。
実は気の早い話ですが、その寺には友人の「奥の墓道」氏だけでなく来年のお寺の遠足のメインイベントにしたらどうかと検討しているところです。
ちなみに今年の目玉は奈良興福寺の南円堂の不空羂索観音ですが。
そこで、寺の近隣見回して「これじゃあ境内の駐車場まで観光バスが入れない・・・」と奥方が。
私は「適当に降りてあのくらい歩いてもらおう」と①。どうにかなりそう。
名張周辺には無数の城址があるというのが知られていますが、ツアーでそういった城を紹介することは絶対パス。
これまで戦国系の城・・・安土城・一乗谷・大坂城などの有名どころを回っていますが御一同の反応はイマイチで「むしろ辛い」の声もちらほら。
南禅寺の山門も、東本願寺の御影堂門も「下で待ってます」という声があがるほど。
しかしこのお寺なら歩いたとしても大した距離も高低差もなし。問題は堂内に興味を持っていただけるかですね。
名張に戦国期の城塞が比較的多いのは伊勢特有の群雄割拠の時代を経ていたからで、大きな大名の支配がなく、それでいて大小国人領主による均衡支配があったからなのでしょうが、その平穏は信長の台頭によって崩れ去る事になります。
われら真宗門徒たちの伊勢長島はじめ本願寺の対信長抗戦と同様でその支配を嫌った伊勢の旧領主と農民が反信長の旗印を掲げ立ち上がったのでした。
それを時期によって第一次から第三次の「天正伊賀の乱」と呼ばれているのですが、その当時の人々にとって伊勢そして名張は大層な悲惨な目に遭っていたのでした。
よってこの地区では信長を討ち取ってくれた明智光秀を讃えるという風習があったというくらいです。
そういうところからも私がこの地に興味を魅かれる理由になっていますが・・・。
再び弥勒寺本堂の外からの図。
②の概略図「西田原イラストマップ」には前回記したように春日神社の中心上から墓域を東西に分けていることがわかります。
⑦⑧は春日神社神殿になりますが、⑦の大きな石は古墳の天井を連想します。
古墳の材を神社に持ち込む例は散見できますからね。
⑩り石塔は新しめ、オリジナルでしょう。
⑪おそらくカヤの木か。堂前中央に屹立しています。
2024年
7月
05日
金
沖縄より暑い静岡 藤枝で沖縄を楽しむ
7月4日の昨日は完全オフ。
沖縄を彷彿させるような天気、空の青さはイマイチですが気温だけは彼の地をオーバー。
当初は大雨連続による排水溝詰まり箇所の対応と、本堂前に置いた石臼の掃除を。
その石臼はヒヨドリがやって来て水を飲んだり水浴びをしますので彼らのために清潔な水を・・・と。よく眺めると水面にボウフラの生息を確認しました。
夏場の水たまりの件改めてケアの必要を感じたところ。
やっつけてやりました(水を入れ替えるだけ)が、しばらくして強烈な蚊の襲来が。
ここに「敵がいる」のスイッチが入ったのでしょう。
彼ら(否 すべてメス)は炎天下でも平チャラの様。
それによってすべてのヤル気が失せました。
外仕事は念入りに蚊対策を行ってから・・・が鉄則ですね。
今年の蚊は例年より手強いように感じます。量が違うような。
沖縄チックな天候に気分が高揚、昼前に記録的な暑さ(39度超え)となった静岡(全国一位)ではなく、その快挙、フェーン現象の要因となった高草山の手前、藤枝へ向かいました。
そちらにあるS.Cのアーモンドとクルミの各大容量商品を仕入れるためです。
それらを食べ過ぎるとカロリー過多となりますが、最近は朝食後にそれぞれ10粒程度を食することを心がけています。
それら+魚油のカプセルというのが私のサプリメント。
偶然かもわかりませんがこの1年その習慣を続けたせいか、肝臓の数値が改善されたことに気を良くしています。
帰りに藤枝法務局裏の沖縄ショップに立ち寄ってソーキ蕎麦&タコライスを注文、奥方と半々で。グァバジュースも付けました。
メニューにタコスがあれば更にgoodなのですが久々沖縄の味、懐かしさを憶え満足。
またサーターアンダギーを購入。
それはどちらかの店の催事などで販売されることがありますが、大抵は外す品になります。
しかしこちらの店のそれは絶品です。
ちょうど出来立ての品だったこともあり、サックリふわっとした感触が最高。
土日には黒糖バージョンもあるそうですが、私どもはそれは無理。
「奥の墓道」氏はそういった沖縄ならではの品には興味がないそう。藤枝で合流しそちらに・・・と誘うも当地に来たら掛川の道の駅のラーメンととろろ飯を所望と。
尚、コロナ回復中にある彼はコンビニに行ってついついあれこれ商品を触っては戻し触っては戻し・・・したことを懺悔していました。
ああ恐ろしや。
そんなところなのでしょうね、感染源は・・・
④は私の特製ナッツセット。
開封の際、袋のアルコール消毒は必須事項。
2024年
7月
04日
木
ここまでくると殆ど奈良 名張西田原 弥勒寺
盂蘭盆シーズン突入で昨日も法要がありました。
午後になってから気温上昇、奥方が「気分が悪い」と言い出しました。
拙寺の庫裏は午後から夕方にかけて直射を浴びますので家の中が30℃を超えることはいつものこと。
退避所として居間のエアコンをオンにしていますが、本堂やら家の中を忙しく動いていれば脳みそが沸騰することもあるでしょう。頭痛の痛み止めを飲んでぶっ倒れていました。
熱中症になった?のは、私が寒いから、と言いながらエアコンのスイッチをOFFにしたことが原因とのこと。
私は午後は境内に出て、松の剪定をしていましたが・・・暑さよりも痒さが耐えきれない・・・
昨日はいいニュースがありました。
旧優生保護法のもと不妊手術を強制された方たちの救済の手が確定したこと。
被害者認定がされたということでしょう、憲法違反として最高裁大法廷が国に賠償を命じたというニュース。
あれは無茶苦茶でひど過ぎるデタラメ人権無視の法で、どちらの国から見ても後進国のイメージと大恥を曝すものでしたが、ようやくこれで一件落着。
とはいえ、その法により強制施術された方たちの権利や希望というものは元には戻せません。本当に恥ずかしい法でした。
国会のお偉いさんの声、「老人は早く死んでくれ」の如くの弁があったことを適宜拙ブログで記していますが、基本的にそれと同じ発想でしょう。
その法の大義とは
「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ですからね、ふざけた法律ですよ。決めたヤツは何様だよ・・・と思いますがそれは議員立法ですから国会議員の発想なのでした。
現状の国会議員こそ「不良な子孫」の方々勢ぞろいがあるのでは・・・
よって国会議員どもは自分らの責任を認めるワケにいかないというプライドからこれまで難癖(時効・・・除斥期間)を付けて被害者救済を拒絶してきたのでした。
一番の問題(恥)はその失策について早々に認めて、謝罪し、補償に対して時効を理由に手をこまねいていたこと。要は政治なのですね。
判決によって首相がここぞとばかりに出てきて謝罪の弁を述べていましたが、腹が立ちますね。「私が主導して・・・」の様でしたし。真面目にやって欲しいものです。
ギインさんたちは裏金と機密費とやらで左うちわの様を謳歌していたのですから。
いずれも「どうせ自分の腹は痛まない・・・」ということ、こうなったら国からしっかりと賠償請求してくださいな。
あと、お国が時効を振りかざしたことに思うこと。
バレたらそれなりの咎(税務署からの指摘、刑事告発)の件覚悟が必要ですが、相続税も贈与税も時効があったはず。各お調べください。
こっそりうまくやり遂げることはできるでしょう。
バレたら「知りませんでした~」でごめんなさい。
川崎重工の脱税についてやはりその発覚のニュースがありましたが、国税庁の追い込みの成果と聞きます。
まぁそちらにターゲットとされればおしまいです。
個人のそれとはスケールがちがいますがね。川重は十数億円。
ただし一応記しますが脱法行為はイケません。
それをヤレとは言っていませんからね。
お国の脱法行為や大企業のインチキに対して「それなら」と物を申しただけでございます。
扨、三河の地について多くの素材(画像)を抱えていますが少々そちらから離れることにします。案外と一般的興味から外れることもありましょう。
もっともこのブログは「フツーで一般的である」とはいえないでしょうが。
基本「ハカ、テラ、シロ」に着目してそれもいわゆる観光的華やかなものを期待するには及びません。
そして今、コロナ療養中の「奥の墓道」氏を次回連れて紹介したいと考えている場があります。
彼ほどになると、フツーのハカ・テラ・シロでは喜んでくれませんので、私の抽斗の中から毎回、コレならばというものを選択するわけです。
あくまでも私のスケジュール重視での計画、時間がとれない場合は毎度「高天神城と小笠山砦」というのはお決まりコースではありますが。
その第一候補が名張の西田原の弥勒寺。奈良方向に向かうならこちらに寄ってから・・・というのも絶妙な場所になります。
彼に以前その「名張」と言えば「あの、毒ブドウ酒事件の?」と返ってきましたがビンゴ!!です。
あの事件も極めて冤罪がプンプン漂うものでした。
それはともかくとして、その弥勒寺は極めて奈良に近い三重県というところ、あまりお気軽な地ではないというところが難点。日帰りとなると勿体ない。
そのまま奈良方向へ・・・という欲も出てくる地ですからね。
決して大きくない真言のお寺ですが彼を連れ出して後悔はさせないに決まっているお楽しみがあります(場所はこちら)。
以前、当家奥方に同行してもらったことがありましたが、あの色々小言の多い奥方からもその印象について〇印を戴いているほどです。
シロとハカとは違ってテラについては「後学心」が働くこともありましょうが。
あの時は朝8時頃の到着で、まだお寺の本堂は閉まっていました。
そもそもこのお寺は「田原氏城」(日本城郭大系 「丘端に見張り台・切込平地が残る」)と同地になりますので、田原氏城館址と言われる③背後の竹藪は「帯同者」の顔色をうかがいながらパス。詰めの城を推測できる寺の背後の山、西田原ふるさと公園を散策することにしました⑥⑦⑧。 ⑥は本堂背後より。
大した高さはありませんが、遠く名張中心部をうかがうことができました。
きっとどちらかに城として機能したであろう遺構があるに違いないとは思いましたが、見たものすべて「こじつけ」に近そうな起伏の数々、確信には至りませんでした。
⑤は本堂に隣接する秋葉神社。
この神社への地元崇敬は厚く、社殿から見た平地を中心に墓地は存在しないとのこと。「穢れ」としたそれを左右の山地に配したといいます。神殿から墓が見えてはイケないというものか。
しかしそれが強く求められた時代以前の墓石たちは境内に集められています。背後の田原氏城址に関わる人たちの墓塔でしょうか。
①は本堂開扉後、拝観料500円を受付にした際、頂戴したもの。
私には不要のものではありますが、拝観者への配慮は満点。
お菓子も頂きました。
2024年
7月
03日
水
深溝松平家東御廟 墓塔内部図 本光寺
「コロナになった」と連絡してきた友人「奥の墓道」氏は熱も下がり気味(37℃代)で「ラーメンを喰いに行きたい」と。
私はニヤッとして「元気になったということで目出度し・・・」
「ラーメン屋で感染させられたのだから・・・いいんじゃね」。
それよりその塩分の多そうなものを毎度食する方が体に悪そうですがね。
今やコロナは殆ど風邪と変わらない軽度な病と化したよう。
ヒトにそのウィルスに対する「抗う力」が培われたということですね。
しかしながら、私はそれを他者に感染させたり、自身その辛い思いをするのはイヤです。
人混みは避けアルコールと手洗いの習慣は継続します。
今回の彼のラーメン屋での感染(まず確定的)、その環境からある意味それは分かるような気がします。
また、そこいらじゅうに未だウィルスが浮遊していること、大いに教わった次第。
1週間も自宅でじっとしていられるか・・・無理も無いことでしょう。
扨、深溝の本光寺墓所のあの荒れた図(昨日)はおそらく現在は復活している可能性が高いでしょうね。いやそうあって欲しい。
あの時以来それを確認のために歩いていませんから不詳です。
各地を襲っている天変地異の報ですが、昨日は米原伊吹地区の土砂崩れについてありましたね。あの辺りには地理的に伊吹山の麓とあって崩壊がありうる場。土砂に揉まれる遺構があっても不思議ではありません。
金沢から能登半島にかけての地震被災地もそうですが、墓域に石垣の類、特に私の歩いた地域のそれらの「安否」について気持ちが動きます。当然ながらその手の情報は殆ど入ってきませんからむね。
人の命が最優先であるがため、かつ依然崩壊した街区の残材ガラがそのままになっているくらいで地元にはそれらに気を配る余裕など無いでしょうし、むしろ「そっちかよぉ~」と怒られそうな題材ですからね。
しかし、半年経ってあの様は「いったい何?」を感じます。
まったくといって撤去が進んでいない状況・・・国のヤル気の無さを感じます。台湾は1週間余りで撤去完了といいます。
僻地だから・・・という理由がありますが、それなら私どもも住まう場所は僻地のうち。
いわゆる見殺しの様。
国の助けはナイとみておいた方がいいようです。ある意味そこに今後住むことなくどこか集団移住を促しているようにも感じます。
画像は昨日同様本光寺東御廟から。
たくさんの同じような墓塔が並びますが割愛。まったく同じような社殿型石塔でした。
石塔の墓塔構造図等は近くの資料館にて。
2024年
7月
02日
火
深溝松平家墓所崩壊の現場 本光寺東御廟
「ツイてない」連発の6月が終わってひと安心。昨日からうれしい7月入りです。あとは梅雨明けを待つのみですね。
月曜でしたが法要がありました。
ご納骨がありましたから、前夜からの降雨には閉口させられました。特に開式時には雷まで。
「おいおい、7月だぞ」と呟きながら本堂へ入ったほどでした。
7月は私にとって一言「ハッピー」連続の月であると以前から脳内刷り込んでいますからね。ちなみに私は当月生まれです。
その「ツイてない」はかなり以前テレビ放映で視聴した映画「デリンジャー」の最期の台詞「今日はツイてねぇぜ」の場面を脳裏に浮かべながら・・・というのが流儀。
「奥の墓道」氏とともに、その件、事あるごとに面白がって吐き散らかしたことを思い出します。
銃弾を受けて殺される直前の言葉でしたが、ツキ・・・自分の死を運・不運の偶然の事で茶化したことを面白がったわけです。
よ~く考えれば私どもも死んで行く身であることは同じこと。
ちょっとした自然現象に運だ不運だボヤくだけノー天気のお花畑といったところ、それはデリンジャーと殆ど同じ。
ところが法要が終了したころは何故か、雨は止み、納骨の時間には僅かながら陽光が差すほど。参列者一同大歓びの様。
施主の奥さんは納骨時の為に合羽を用意するか悩んだほどで、施主は「眠れなかった」と仰っていました。
法要終了後しばらくして再び雨が降りだしました。
なんとナイスなタイミング、奥方には「7月だからね」とニッコリ。
私にとって7月こそポジティブに動く月なのです。嬉しい事楽しい事溢れる月と・・・
ところが8月生まれの「奥の墓道」氏は「ツイてない」ようでした。
前日に友人とラーメン屋に立ち寄っていたそうですが、夜間、窓を開けたまま寝込んだところ朝、頭痛と熱、風邪の症状が出たと。
近くの医院に駆け込むと鼻の穴に検査用綿棒を突っ込まれてグリグリ、数分待つと「ハイ、コロナね~」との診断結果。
一週間の自宅待機だそうですが、案外と初診料は安く、処方薬込みで3630円。まぁ余計な出費ですがね。
何より頭痛・熱・のどの痛みと咳と付き合わなくてはなりませんし自宅軟禁は辛い。
誕生月の前の月は心身機会とも不調を来す・・・これは我らのジンクス。
またそのコロナ繁盛の現実を身近な人の罹患を耳にして今後とも外出と法事はマスク必携、を確認した次第です。
折角のラッキーJulyが台無しになりますからね。
そして彼とラーメン屋に行った友人とやら、「レンゲ」を共有したことからか気の毒にも今「頭痛が・・・」と言っているそう。
コロナウィルスがまだまだ市中にウヨウヨしている感じがしますね。
彼の弁「眠りが浅く睡眠不足が続いていたため免疫、抵抗力が低下していた」と。なるほど・・・
「食べて充分眠る」健康の秘訣。
ただし運不運はありますがね。
要はタイミング、チャンスといった部類です。
扨、昨日の深溝松平西御廟は数年前の図ですが本日も続けて。
あの時の墓域の荒れ具合は目を覆わんばかりでしたね。
スポンサーが居ないとこうにもなるものか・・・まぁお国の支援の目もありそうですから、ゆっくりと復元していただきたいものです。本堂にも修繕の職人が入っていました。
寺の維持に経費がかかることは承知していますが私どもとは「スケールが違う」という感。
昨日は本光寺の駐車場の画像を入れましたが、駐車スペースの脇に駐車代金徴収依頼の掲示がありました。
観光のお寺ではない宗旨の寺で「そこまで・・・」とため息をつきましたがやはり微々たるものでもその積み重ねと大変の告知はすべきですね。
勿論協力しましたが。
最期の2つは深溝松平六代の松平忠房とその正室永春院殿(鍋島勝茂の娘)の墓。
また参道等、三河で散見される石材が敷き詰められています。
2024年
7月
01日
月
島原藩主深溝松平家墓所 本光寺東御廟
先週末の土曜日に史跡研究会の会合がありました。
史料館2階のホールで「静波太鼓」なる披露があったようで、いつもとは全く違う空気が漂っていました。
聞けば恒例の中国国際交流、100人弱のそちらからのお客さんがいるとのこと。その書道作品の展示会があったよう。
それだけの人達を中国発の飛行機で捌けなかったのか、数人のお偉いさん方は静岡空港、残りの大部分はセントレアだといいますから、結構な不便を思います。
まぁそれとは別に、歓迎会、お土産屋(ドラッグストアは欠かせないそう)宿泊先、その大挙によって潤う企業があったようです。
牧之原市にカネを落してもらう、大いに結構ですが、殆どの市民には関係なし。
まぁ大河ドラマで田沼がクローズアップされたとしても「どうでもイイ」・・・なる方々、大勢の如く、何事も「無関心」はつきものです。
以前から言われていますが旧榛原町と旧相良町の方たちの思考濃淡の件もしかり。その田沼の件、旧榛原町の人達は「まったく関係なし」のスタンスであること微妙に感じますね。
10万人の受入れ(市長)を目論む役所上層部の思い入れとは裏腹に末端職員には伝わっていないよう。職員とはいっても派遣の方もたくさんいるようで。
観光客受け入れのために役所の駐車場を空けさせるため頭を痛めていることは聞いています。
退去したスルガ銀行の跡地を代替地に・・・という案もあったそうですが「遠すぎる」との役場職員の反対の声が出たと。
そりゃそうでしょう遅刻ギリ、1分2分を争ってすっ飛んで来る輩(昨日)からすればたまったものではないでしょうね。
そういう皆さんからは「大河大迷惑、イラネ!!」の心境も少なからずあるようで。
そういうこともあって前哨戦ながら今一つ盛り上がりに欠けると感じさせるのですね。
まぁ、折角のチャンスなのですから、あとから後悔しないよう楽しみたいものです。一部の人達を除いて・・・ですが。
扨、本光寺には西御廟と東御廟との2カ所に墓域がありますが、これまで拙ブログにて記してきたのが西御廟。
そしてその東御廟には他の島原藩主深溝松平家代々藩主たちの墓が揃います。
数基のそのタイプの墓標が西御廟にも見られましたが東御廟はまさに特異なあのカタチが勢ぞろい。
そしてまた島原、江戸で没した藩主を船で三河湾経由で搬送、こちらの先祖同族の集まる地に埋葬したという代々固く守られていた掟の如く決まり事は天晴。
仕事量かつ、経費莫大出費の歴史を感じます。現在であってもそれはできないことですからね。
墓域前には何故かオーソドックスな五輪塔が。
天妙院殿十三代夫人に俊光院殿十五代夫人とあります。
こちらへの途上、山門が設けられていますが曹洞宗のお寺らしく毎度恒例、結界の石標(不許葷酒入山門)が「お前は入るな!!」を主張していました。
2024年
6月
30日
日
漢方医→蘭方医 新宮凉庭(鬼國)十五則 成瀬大域
一昨晩の横殴りの雨(雷鳴付き)には本堂と雨漏りの常習箇所見回りチェックに向ったほど。
翌日は何事もなかったように静かな朝を迎えました。
私は本堂で法要、息子は葬儀式と法務の分担。
彼は朝7時には庫裏を出ていました。
私どもは以前の寝坊して遅刻ギリギリで校門を潜っていた姿が頭にありますので信じられない、奇跡でも起こったような衝撃を感じます。
それにしても早すぎやしないかとも思いますが、余裕を以て事に当たる・・・など良き心構えで感心。
「遅刻寸前」といえば役場職員の自家用車運行のマナーたるや「最低」だといいます。朝のその時間は「とまれ」を無視したり交通違反の連続「危なっかしくて仕方ない・・・」とのこと。
榛原系の通勤は150号線を嫌うため原超え平田寺コースを使うためそのコース上に住まう人たちはその辺りの件、承知しているとのこと。
私どもの住まう場所は役場が近くともその逆側ですから「それ」を感じた事はありませんでした。
もっともその時間帯に車でうろつくことはまずないですからね。
まずは役場のお偉いさん方に忠告すべきですね。
それでもダメなら警察のご指導。しかしその時間は取り締まらないのでしょう。嫌な世の中。
普段は一般市民をバシバシ取り締まるクセに。
扨、当家に関わりのあった成瀬大域の書があります。
漢方医から蘭方医となった新宮凉庭(鬼國)の「医」の心得を記したもので、江戸期の医師ではあるものの現在にも通じるところがありました。またその頃の医者という者の気概を感じます。
書としては「以(って)」の韻を15回、要は4文字熟語的語彙の連続で面白味のあるものです。成瀬はその「心得」になるほど・・・を思ったからこそそれを記したのでしょう。
その「以って」の次の語を深く読み込めばだいたいのところは了解できますが、最後の「富人以方」の「方」については叔父と
解釈が分かれました。
私は江戸期の医師-小島蕉園の如く貧者からおカネを取らない「善なる医」というものを連想しますので金持ちは「放」、いわゆる片手間に置いておけ・・・の感じ。
お金持ちは自身で対応できる・・・というところ。
叔父はその「方」の件「処方」の意が近いと。
医師だけにそれは当然にありうるところですがその「処方」に関しては5つ目に登場していますからね。
こういった文言並べで同じ字、意を同居させることはあまりないでしょうから私は「放」と考えたのですが。
そうであった方が江戸時代ならではの医師のあり方らしくて嬉しく思います。
またその直前の「貧人以恵」に対しての語としても・・・
切脈以静 望色以明 聴問以詳 繹因以遠 處方以簡
製薬以潔 行術以捷 飯食以節 説諭以和 容貌以荘
婦女以禮 貴人以恭 愚人以訓 貧人以恵 富人以方
右新宮鬼國先生語為醫十五則 賜硯堂温 書
③画像。
昨日は健康のための医と食を旗印に業績を伸ばしてきた小林製薬の暗部露呈のニュースの件について触れました。
こちらの軸には「製薬以潔」「行術以捷」とありました。
彼の社は「不潔」と「遅滞」(捷とは逆)でしたね。
2024年
6月
29日
土
本光寺西御廟所 その他の墓塔累々
梅雨らしい一日。
雨の激しく降る場面もあってまたテレビから浜松から始まって駿遠各所の河川増水について報じられていました。
拙寺には2件ほど「相良はどうよ」とご心配いただく連絡がありましたが、拙寺限定ですが雨漏りもなく、安泰ではありました。
土曜日の葬儀は副住職に導師を頼んでいます。
勿論先方ご家族には了解済みです。
以前から承っていた法要と重なってしまったためですが、通夜式とセットにした方が良策と思い彼には昨日の夕刻から先方の会場へ向かってもらいました。私は自宅待機です。
奥方は、先方から連絡が来ないということは「ちゃんと時間には現場には到着しているんだろ」と。
私の心配はそこではないのですがねぇ。
これまで私のスケジュールによって先方には先のべを了承していただいていたのですが彼の登場により先方の希望が通りやすくなったということです。
夏場の繰り延べの場合、余計な管理経費が跳ね上がりますからそれを考えれば早い対応は悪くないことかと。
彼には彼のヤリ方がありますので私がとやかく言うことはできませんが、聞けば時間は60分かけたとのこと。
私の場合は「35分」というのが目安ですが、「どうするとそうなる?」と問えば「+阿弥陀経も」と小経の早読みを加えたとのことでした。
阿弥陀経の間にご焼香いただくパターンですね。
最近はとかく坊さんの「手抜き?」を思わせる場面を指摘されることが多くなっているご時節だけに、それなら素晴らしい~と安心させられた次第。
先代住職も私も正信偈1本でしたから。
これからは「若い方がイイ」との声があがりそう。
そうあればまた嬉しい限りですね。
彼が拙寺の代表として地元の葬儀式に出仕するのは本年三回目となりました。
中学の部活のあとに通夜に私の脇僧として出仕させ、居眠りの様を後ろから施主に見破られて苦言を呈されたことなどが思いだされますがその件時間の経過もそうですがウソのようでもあります。
肝が据わっているというか本来のバカなのか・・・驚かされます。
ただし浮かれるのはまだ早い。後から施主に「実は・・・」などとぶっちゃけられることもあり得ますからね。おかげさまで前二回は何事もありませんでしたが。
そもそも通夜も葬儀も「いつもの住職でなくて若いのが来る・・・」ともなれば「そんなら、いっちょ 見てこよう」という興味津々も出てくるかも。
人の、まだ見ぬ新たなものを見届けようといった好奇心、注目のプレッシャーもあること不思議ではないのですが・・・。
昨日は早い時間に出立し、のほほんとした顔で帰宅していました。
尚、最近は当流坊さんの正信偈「5倍速10倍速」などと揶揄(特に正信偈を熟知している方から )する声が聞こえてくることがある中、各通夜式付随+阿弥陀経+正信偈1倍速+法話で60分みっちりの時間は、あまりないような。
10分・15分の通夜などもあるようですから。
いつも驚かされている私ですが、昨日は息子のそれよりも、気象のことよりもより驚かされたのが例の小林製薬の不祥事の件。
3月頃に発覚した紅麴サプリメント製品に青かびが混入し死者が出たというそれですが、「実は・・・」とい具合に死者は当初の5人ではなくてあらたに「79人いました」正信偈(因果関係確定が76人)との報道があったこと。
どう考えても、その加害について会社としては表に出したくなかったというところが見えてきますが、「そんなんでいいのかよ」と感じさせられます。
だいたい製品に青かびが混ざるなどということは普通に考えてもあり得ないことです。管理が杜撰でいい加減、当初は「なんて汚ねぇ環境だったろう」と感じるばかりでしたが、企業としても失格の烙印を押すことになりそうです。
あまりにもお粗末な製造ラインであったことが推測できましたが、1度の失策は許されても失策を秘匿しようという意図が発覚したとなればその行く末は退場しかありませんね。
あれだけの企業(「大手」を錯覚していたのですが)がその劣悪製品を製造しその失敗への対応がその隠蔽体質であるならば日本の他の企業のいろいろも信用の失墜をさせることになります。
私はあの会社の商品を購入、使用したことはありませんが(どうも胡散臭い!! ) 、この様を見させられていると危なっかしくてサプリメントというもの全体についてリスクを思いました。
私はただ一つ、魚油のカプセルは毎日飲んでいますが、ちょっとばかり不安にさせられますね。数年続けていて特に悪い状態にはありませんが。
80人近くの人たちの命を奪っておいて、「健康産業」を標することはもはやできないでしょうね。言い換えればそれを「殺人」というのかも。
今後の補償とペナルティはどうなるのでしょう。
ご遺族には申し訳ありませんがそちらの方に興味が移ってしまいます。
まぁ会社の信用が丸潰れということは確かですね。
商社に買収されたあのビックリモーターと同様の途を辿るのでしょうがリスク管理とその対応がまるでなっていませんでした。去るべくして去る。
厳しいですがそこまで考えてしまいます。
扨、本光寺墓域のいろいろ(昨日)を記しましたがこれまでの墓域は境内の西側の墓域(西御廟所)です。
そちらには掲示板のない、深溝松平一統のものと思われる墓塔がたくさん建ちます。
卵塔の数々から各時代寺院主催者(坊さん)たちの墓も同座しているのでしょう。
2024年
6月
28日
金
21歳逝去松平好房 孔子廟 接道義務の不可解ボヤキ
またもや好天。
午前は庫裏にて事務仕事の日。
盂蘭盆法要も近いですからね。
そして会館新築工事の件、最新の図面をお持ちいただいて最終吟味。変更した建築士の方です。
これから業者選定を行って見積額を算出するとのこと。
贅沢品の使用は無いので見積もりで予算オーバーとなったら「面積縮小」で対応するしかないとのことでした。
それもこれも材料費高騰の今までまともに工事進捗がなかったためですからね。腹も立ってきます。
それでいてまともな活動をしていなかった前任の建築士からの請求が大枚であったとしたら・・・ゴネる・・・腹を決めています。
この建設に関しては私はあまり口を出さないようにしていますが、一応この敷地の管理者として解決していかなければならない数々の問題がありました。
まだまだこれからもあるでしょうが。
特に今回の件、ボヤきたくなるほど不満はたくさんありますが、その中で一番にこの世の中のバカバカしくなるほど「無力」を感じずにはいられない事を少々。
それが家屋の新築工事でどなたもがその法令について耳にする「接道義務」(建築基準法)についてです。
コレは建築物には当たり前のことで宅建主任者である私も「そんなことは百も承知」といったところ。
それは「建物は道路に2m以上接していなければならない」という法律です。元は消防車が入れないと困ることからですね。
前任の建築士からも大工さんからもそんな話はまったく指摘はありませんでした(第42条第2項道路のセットバック要件)が今回の会館新築工事はあらためて「できません」とのお達しがありました。
「念のため」と建築士が牧之原市の都市住宅課(住宅政策係長)と静岡県島田土木事務所(建築住宅課)にあたったことから判明したのでした。
「まさか」と愕然とさせられましたが要は拙寺門前の道路は法令上の「道路ではない」ということです(④画像赤い部分)。
その「道路」に門の間口は2m以上接続していますが。
「道路に接していない」を理由に家は建てられないというのがその法令ですが、その道路として認められない主たる理由は、その道は寺と墓地の間の通路であって一般的家屋が不在ということが主たる理由。
それでいて北側斜線規制では墓地であっても考慮しなくてはなりませんからね。
それより幅員狭小の元の樋尻川を覆った北東側の道が「道路」認定されていました。尚、市の避難経路としてその「道路」ではないその赤い道が経路指定されているという変てこな現実もあります。
祖父の代の会館建築の際にラクに通っていたはずのその法令が今回はダメの判断。
古い寺社であり文化財という切り口もそれは本堂が指定されているだけで「境内全体ではない」を理由に却下されました。
奥方は来年の大河ドラマを視た観光客が「大挙する」(市長さん談・・・)ということからその客用外トイレの建築を急がせています。よって「無茶いいやがる!!」と憤懣やるかたなし。
先般も外用トイレが間に合わないことを考えて・・・庫裏の客用トイレを改修したばかりでした。
市のあれこれ協力することなど「ヤル気ナシ」のどうにでもなれ~(ケツをまくってやれ~)の感情も湧きあがりましたが、まぁ史料館教育関係部署と道路都市計画関係者ではそもそも畑違いですからね。
お役人の「ただの嫌がらせ」と解釈し、解決策の採用を受諾しました。
解決策の選択肢2題。
①会館に隣接する他家所有地を一時的に借地登記して道路隣接の件をカムフラージュ。検査通過で元に戻す。
②南西側の道路(緑色)をみなし採用し(そこならできるらしい)
尚且つ土手を50㎝ほど崩す。
両方とも便宜上の「なんちゃって」であってバカらしいことです。
当初②は有り得ない話でした。
土塁上部には大木が林立していますから、それをやったら木が倒れるにきまっています。
するとその土塁は崩さなくてもOKとなりました。理由はわかりません。
しかし石垣を撤去しなくてはならないとのこと。構造物があってはイケないとのことでしたがその面の石垣は約50個。ある方が言うには石は構造物ではないだろうとの指摘がありましたが何を言っても「どうにもならない」を早々に察して一家動員して一旦撤去することで了解しました。
今一つボヤかせていただければその図面緑色の道はそもそも拙寺の敷地であって時効によって相良町に接収されたものです。
とことん矛盾と無茶なる諸所事案に翻弄させられています。
色々な方にその「赤い道」の件問い合わせさせていただきましたが役所は頑として「『道』ではない」とのこと。
それにしても寺に無理難癖をつけるとは。
都市ができる前、田んぼと畑しかない古~い時代からあるものに対して・・・という意味です。
ここにボヤくことで気が済みました。考えると心身に良くないですから忘れましょう。先に進むことにします。
次に頭を抱えるのは金額提示されたとき・・・おそらく卒倒することになるのでしょう。
そんなもの、建てないでうまいこと老後資金に廻せば・・・それも選択肢でした。6月はツイてない(昨日)、その一連のことか。
もう少し辛抱します。
扨、深溝松平には昨日の「島原大変」の松平忠恕以前にも「ツイてない」というような天災その他に祟られた人はいました。
松平忠雄(肥前島原藩の第2代藩主で深溝松平家7代当主)などもそうでしょうね。
そもそも深溝松平家は代数を重ねて家そのものは続きますが、色々頭を悩ませていたようです。
家というものの継続には男子に恵まれることと長生きしてもらうことが肝要ですがそれに恵まれなければ人を「工面」しなくてはなりません。
その件何事もなく順調に進まなければ「天変地異」以上に災いへと繋がる事は必至です。
家が消えることになりますからね。
松平忠利の息、松平忠房に急遽養子入りして家督を相続した松平忠雄は領内の飢饉凶作で藩中経済困難に陥って借金金策。
領主殿様は大変です。
挙句に世継ぎ相続予定の男子が亡くなってヤル気もなくなります。
続いて百姓の逃散、虫害による田畑疲弊、疫癘流行続きで散々な世継ぎだったと。
その急遽婿入りした経緯も松平忠房の長男松平好房が21歳で亡くなりそのまた弟の忠倫は不行跡が元で廃嫡されたといいます。やたらと面倒が重なってしまっていた時期ですね。
その本来の跡継ぎとして熱望されて若くして亡くなった松平好房の廟が本光寺にあります。
「孔子廟」なる名称がありますがそれだけ「礼と孝」の子であってきっと周囲から惜しまれて亡くなったのでしょう。
その彼の弟が「不行状」というのも人間世界いろいろの件わからないところでもあります。
私は礼でも孝にも非ず。やはり後者の方でしょうね。
2024年
6月
27日
木
引っ越し貧乏 重ねての災難 島原大変 松平忠恕
昨日もいいお天気。梅雨など無くて結構。
朝から御門徒様宅にお邪魔して御一同と仏間で正信偈。
帰宅してから役場の住民課へ。
数日前に東京の方よりメールで問い合わせがあり、それには当家の除籍謄本が添付してありました。
当家11代目の祐曜の二女の嫁ぎ先の子孫からでしたが、そもそもその謄本のその二女の名には斜線があり赤丸があって別の名が。過去帳は「きく」で赤字で「きし」と改めてありました。
意味不明に陥りましたが、単純に先方のただの誤りだろうと叔父に問い合わせると「まぁこっちで除籍謄本確認すれば・・・」という結論でした。
その書面には文政七年生まれの祐曜に妻滝江(清水専念寺曽我家から)が天保三年生まれ。
文政三年生まれで祐曜の姉、あの波さんの名まで記されているもので、私も一つ取っておこうという気持ちがありました。
カウンターで、もしかしてそれ以前のものは「ないよね~」と聞けば「コレが一番古いモノです」と。
当たり前のこと、野暮なことを・・・。
尚、この謄本は「直系の者」のみしか取れませんね。
きくさんが直系となる子孫ならばOKですが、嫁として転出された方はその実家の直系の私でもムリ。
私にはこれ以上の探索はできません。
また、古い謄本を出力してもらう手数料も結構お高く750円也。
その後、居間で久々に豪快な転びをやらかしました。
雑に配線されているパソコンやら扇風機のコードに躓いたのでしたが、両手で持っていた書類箱は投げ出すもパソコンデスクの上に、体は宙を飛んでのその時間は記憶から飛んでいましたが、気がつけば扇風機の乗っていたカメラ用の大き目プラケースの上に座るように着地していました。
壊したものもまた怪我もなく、一件落着の事案でしたが一部始終を目撃していたネコ共はその大音響に一目散、奥方は台所から「何やってんだか・・・」の呆れ声。
そして奥方は「6月だからね~」。
コレは先般からやらかし、うっかりのおバカミス連発から「6月はどうもいけない!!」などとオオタニサンの6月絶好調のニュースに対して私のその凡ミスと不運連続についてボヤいていたからです。
早くこの時節から脱したい。
扨、昨日の本光寺の深溝松平の墓域の続き。
また一つ結界のある墓石があります。
このカタチは当家が島原藩主となったあたりから踏襲するものでしょうね。
以前、結城松平家の松平直矩(なおのり)をモデルにした「引っ越し大名」という映画がありましたが、彼は何故か7回の国替えによって経済困窮に陥ったいわゆる引っ越し貧乏大名。
大名行列もおカネがかかりますが、国替えはより莫大な費用が必要になりますね。
こちら深溝松平11代忠恕(ただひろ)の廟ですが、彼の国替え経費が嵩んだ貧乏度合いに加えた困窮と追い詰められた心境はやはり数ある大名中ベストにはいるほどにツイてなかった方。
財政難=年貢引き上げという構図はどちらの世界でも同様のことでそうなれば反発(一揆-兄忠祇 ただまさ 時代ー の籾摺騒動・・・)が起こる事も必至。一件落着後藩中は大洪水に見舞われ、借金を重ねてたところにさらに大洪水。
そして挙句の果てに藩内大火災と天変地異に翻弄されつづけた人(下野宇都宮藩時代)。
そもそも深溝松平家は肥前島原藩にあって訳あって宇都宮にいたわけですがその災難続きから逃れられると喜んだかは知りませんが、旧領島原に移封を命じられます。安永三1774年です。
きっとこちらでも引っ越しに経費が膨らんだとは思いますが、忠恕がその災難を過去の事と忘れつつあったころ寛政四1792年に日本史上大層な火山災害として記録に残る「島原大変(普賢岳大崩落)」に見舞われます。
その発生から4週間も経たないうちに彼は亡くなっていますが きっと「なんで自分の時ばかり(酷い天変地異が)・・・ツイてない」と失意と空しさに見舞われたことでしょう。生きていく気力も失われるでしょう。
被災地に対して「再建」への希望を・・・などとよく言われますが、一度の災害で失意心身喪失により命を落としてしまう例はよく聞きますからね。
それが幾度も幾度も重ねて襲ってきたら・・・
希望も未来も描くことなどできないでしょうね。
忠恕はそれでも頑張った、人生五十年。
2024年
6月
26日
水
深溝松平 五代忠利 肖影堂 願掛け 亀に何をタノム?
梅雨入りとのことですが、昨日も晴れ。
素直に嬉しい。
しかし昨日は市外で雑用があったために寺を不在にしていました。奥方も同様です。
ご門徒様のお参りも多く、住職不在に「何やってんだ~」との声にはありませんが(心底プレッシャーに感じました)携帯電話やら転送電話で多様な問い合わせがあった一日でした。
大変申し訳なし。
扨、再び本光寺の墓域に戻ります。
昨日は深溝松平初代と二代の首塚(二本松 元本光寺跡)、一昨日は初代から四代の本光寺墓域を記しました。
本光寺のその四代墓域結界入口には「御先祖堂」とあり「数々の戦いで功を立て、子孫繁栄の~」とありましたが、まさにその通りというか端的にその人たちの存在を表していました。
そしてまた五代目の忠利への崇敬は高く冠衣像が安置される肖影堂があります。
彼の代から扇紋に変更したのですね。
「願掛け亀」覆堂の石扉にもそれが。
本多家系でよく見た墓碑のタイプと思いきや・・・
ちなみに私がその手のモノと遭遇した場合、折角だからの粋狂は「悪辣政治屋が消え去りますよう・・・」でしょうね。
私利私欲の「お願い」ではなく、私利私欲の為に暗躍し、政を詐術を以て操る輩へのそうあるべき結末について「頼みますよ~」。
それは庶民の当然なる願いです。
それはたれ ?・・・御判断はおまかせしますよぉ~と、またねぇ。
2024年
6月
25日
火
向野首塚 初代忠定 二代好景の二本松 元の本光寺址
晴れたので宿題の一つ、先日伐った立ち枯れ槙を土手から引きづ出してそれを5分割にカットしました。強烈に重い・・・。
横になっている材ですから楽に・・・と思いきや、乾燥しきっていてカチカチ。チェーンソーの歯から煙がでてくるほど。
折角の替えたばかりのソーチェーンでしたが、交換の刃の用意が必要になりました。
まぁ一番悪かったのは先日、静波墓園の古い物置を切断したことですね。勿論、砥いでから仕事に入りましたが。
人の作った工作物はイケません。
どちらか釘などの金物が隠れていますからね。
何度か「やっちゃった」ことから大分刃を欠いてしまいました。私がやったことですから文句なし。
しかし最近やたらと失敗が多すぎます・・・「うっかり」というヤツ・・・軽度認知症が始まったか・・・
お昼のニュースでは熱中症についてやたらと警鐘警告していましたが(静岡で35℃超え)この日は風もあって私の感覚では大したことはありませんでした。
やはり沖縄で遮蔽物の無い場所に長居した経験があるからでしょうかね。
ただし、チェーンソー仕事はへろへろに疲労、片付けはまた、ということで丸太は墓地に放置したままです。
その仕事は少なからずキックバック等うっかり自傷事故がつきものですから、それも酷くやかましい機械音の中での神経は結構にピリピリ。
木くずだらけになった服を脱ぎ捨ててシャワーを浴び、昼食後 ネコと仏間で昼寝。
まぁ気楽な半日仕事、「熱中症」などまったく縁がなし。
さあ、あの丸太・・・どうしてやろうか。
持ち上げられる重さになったので(処理場に)「搬出しろ」との指示がありますが。
扨、昨日は本光寺の深溝松平四代の墓域について記しましたが、そのうちの初代松平忠定、二代好景の「首」に因んだ験・・・二本松の塚があります。別名向野塚、向野首塚です(場所はこちら)。
拙ブログでも度々記していますが松は墓の験、標としてあることが多くいわゆる墓と同等。
杉ほどの寿命がないことが残念ですが・・・。
こちらの掲示板によれば昭和25年に伐採とあります。
立ち枯れしたのでしょうかね・・・2本いっぺんに?
そうでないとすれば近隣住宅地と化していますので開発に伴う伐採か・・・などとも思い浮かぶところ。
それは墓を荒らすことと同等・・・開発(金儲け)の為に木を伐ったりして・・・いいのかなぁ~の思い。
トーキョーのお偉いさん筆頭に神宮外苑の木々の伐採の件、あれこれが伝わってきますが、私の個人的意見を殴り書きすれば私利私欲で木を伐る者に「大バチが当たれや~!!」ですね。
阿弥陀さんは苦虫を潰しましょうが「呪い殺してやろうか~・・・」現代にあって「呪詛」を勝手にやるのは犯罪行為ではありませんし。
尚、私は大木好き、ついつい言葉が過ぎました、失礼。
そして私のチェーンソー仕事は・・・「管理上」という言い訳をさせていただきます、はい。
2024年
6月
24日
月
深溝松平4名の結界 幸田本光寺
昨日は降雨でやきもき。
先方ご自宅へ「さぁ、出立」とばかりに玄関で草履を履いていると外から黒い影がこちらに。
私は完全にボケまくっていました。
先般「法要は本堂で」と窺っていたことを思い出しました。
大慌てで本堂の用意に取りかかりましたが、その法要ではいろいろ間違いが露呈。
間違いと言っても私の全ミスですからね。いやはや・・・終わっている・・・
施主から「ボケるにはまだ早い!!」と尻を叩かれましたが。
何を言っても言い訳にしか聞こえないとは思いますが、つべこべと色々お話だけはさせていただきました。
真宗の流儀、悪人正機だとかありのまま、おまかせ・・・などの語彙をちりばめて。
都合イイこと、言ってやがる・・・
扨、昨日は「幸田のいろいろ」と称して二村氏からの資料を記させていただきましたが、深溝松平家の3代目の松平伊忠(またはこちら)に4代家忠の墓域があります。
厳密には初代忠定・二代好景と4人勢ぞろいの場ですがこちらは
幸田の本光寺(場所はこちら)。
初代忠定の創建で松平として圧倒的に多い浄土宗ではなく曹洞宗。忠定の夫人は三光院という寺を建てていましたが、大名家夫婦ではありがちなところ。
夫婦別姓が言われるようになりましたが、その当時は夫婦で別々の宗旨、家の宗旨を継承したものですが、このクラスとなるとそれぞれ違う寺を建てる・・・面白い。
夫と同じ墓、義母義父たちと同じ葉かな入りたくないという声が聞こえてくることがありましたがスケールが少々違う。
画像はPCに埋もれていたもの。
鮮度という点では古いのでしょうが墓石はそうは変わりませんからね。
2024年
6月
23日
日
幸田のいろいろ 二村氏から
当分は雨・・・との覚悟はありましたが、昨日は晴れ。
午前の法事は東京からの御門徒様の来訪でしたからこの好天は有難い。
親類には相良在住の方々がいらっしゃいました。
そこで拙寺関係の相良の最近の傾向ということで昨日の「いわた浜松信用金庫」の「夢風便り」を紹介しました。
会社経営をされている方がいて、さすがにこの発行者は西部すぎて日ごろのお付き合いはない・・・といいつつその出来の良さと比較的地縁的に近くない相良の歴史、話題を取り上げてくれたことに感服していました。
地元の企業、「何やってんだ~」。
そして午後からは婦人部の会合と世話人会。
聞いている方も大変だとは思いますが、私は一日中のおしゃべりに喉がかすれ気味。
梅雨の晴れ間の休日、折角の時間を取らせてしまって申し訳なし。しかし降雨ならばそれはそれで申し訳なし。
私が「物を言う」こと、それも何卒と申し訳ないことばかり。
扨、先日は「さんえん」の「夏目氏と明善寺」を送付いただきました二村氏の封書に同封されていましたのが表記画像たち。
これらを拝見して、最近離れていた幸田と三河のいろいろに拙ブログも戻ろうか・・・と思った次第。
散らかった雑多な画像が我がPCに滞留していますので。
しかし、奈良周辺の画像もゴチャゴチャになって積みあがっていますからね。
時間を経て、私の記憶から消えつつあるような古い画像の存在はまた残念。
まぁあちこち彷徨っての忘却の残骸について、「どうってことはない」というところでもあります。
そんなとき私はいつもこう思います。「また出あえれば それでヨシ」。
とはいいながら、昨日の沖縄と同様、体も心も衰えて、家の中でボーっとしている我が身を想像するのでした。
10月19日はスケジュール的に無理でした。
幸田を訪れる理由になったのですが。
2024年
6月
22日
土
浜松いわた信金「夢風便り」 田沼意次とその時代
朝から雨も15時頃に晴れて変な天気。そして梅雨入りとの事。
沖縄は梅雨明け。毎年この時期になるとそちらへの想いが増幅して「今年こそは・・・」などと憧れを胸に抱いていたものでしたが、今年になって何故か、それは殆ど喪失していました。
完全な諦めムード。
体の方もきっとついて行けないでしょう。
日焼けは当初真っ赤になってヒリヒリ。それが過ぎて真っ黒になった頃にこちらに帰ってくると、超が付くほどの違和感の目で見られる・・・すべてが過去の思い出ですが気持ちとしては「いつかまた・・・」。
昔の友人たちは単独でも沖縄に向かう勇気があること敬服しますよ。
奥方との共通の友「女墓場」は・・・オバさんになりましたが(失礼!!)機会があればいまだ平チャラ、独りで沖縄を彷徨っていますからね。
仕事の歯科学校講師が夏休みで暇になる頃、私と同様、その思いが・・・しかし肌の劣化、老化の現実を思い知るのでしょう。
ジジイもババアも沖縄の日差しは刺激が強すぎるはず。
何度も「今日来た!!」という観光客が救急車で搬送されるシーンを見てきました。ビーチで日焼け数時間で救急搬送。
昔は笑いながら(これも失礼)見送っていましたが。
私たちがいた頃より断然キツそうな気がします。
イスラム教徒が聖地メッカへの巡礼(ハッジ)で、1000人以上亡くなっったと報じられていましたが51℃超えの酷暑が原因だそう。
辛いことはわかっていても絶対行く、それは「聖地だから」ですが、我らが憧れる沖縄の太陽と青い海と風への夢こそ聖地巡礼の如くなのですね。
扨、先般取材協力した「浜松いわた信用金庫」の年2回発行の機関誌「夢風便り」が手元にありますので紹介させていただきます。
来年の田沼意次登場の大河ドラマ先取りと思われますが、今後それが本格化することも予想されるところ。
だとしたら楽しいことです。NHKの脚本次第ですが・・・たくさんヨイショしてもらえば・・・相良も聖地化するかも。
今回のそのタイトルが「相良の名君 田沼意次とその時代」でした。
史料館の長谷川氏経由でその件の話がすすめられますが、相良城、田沼意次関連の紹介はまず平田寺―般若寺―そして拙寺というパターンが出来上がっています。
3ケ寺の住職がチラチラっと登場しています。これまた失礼。
2024年
6月
21日
金
二村氏「夏目氏と明善寺」 知事選に隠れた茶業衰退
昨日は挿木で成長したハイビスカスたちの植替えと途中で放置されたままになっていた松の剪定を。
松のトップ部分はこれまた脚立のトップに上がっての仕事になりますが、それは一応反則。そして両手を使っての仕事はさすがに度胸が要ります。
毎度のこととはいえ、途中で相当嫌気がさして愈々ブン投げてしまおうかとも思う年頃。
それでも最後は上部を大雑把に剪定、いやカットして仕事を終えました。
奥方はそんな私の松管理を、アレ(息子)は「絶対にやらない」いや「やるわけがナイ」と断言。
仕舞にはチェーンソーを持ち出して「根元からだろうよ・・・」の憎まれ口。
死した後(あとに残れるものは)勝手自由というのは了解していますが、心残りは案外たくさんありますね。世を去った者のいろいろを考えていたら、大変でしょうから致し方はないでしょうが。やはり生きている方が大事ですからね。
また同じ趣味を強制はできないですね。
ハイビスカスもブーゲンも南洋系の植物たち、配慮を欠けばその命すべてが消え去ります。それを考えると残念無念。
自分が死ぬこととは・・・そういうことか。
死すると言えば昨日画像で示しましたよう、当地の茶産業は衰退の一途。一部既に「死んで」います。
それは大手の茶メーカーの叩き売りにも似た価格となる3番茶以降の茶葉で食い繋いでいる農家もありますが、あの原の茶畑の各惨状を目にすれば、素人でもその無慈悲は察知できるところでしょう。
ところが先般の静岡県知事選での争点はボケまくり。お茶農家救済の声など聞こえてきません。
双方ともリニア、リニアと○○の一つ覚えの如くの連呼。
将来の「水争い」に及ぶことの危惧があるそれ、その水という生活に肝心なものを「このままでは静岡県民が日本国中から恨まれる」なる理由で「早期解決」したいの主張は、私からすれば問題の根本を見誤っているように感じました。
何故にして、リニア関係者とその果実を期待している人たちに対してゴマをすらねばならないのか。
静岡県民の私はリニアなんて知ったこっちゃない・・・です。
まずは完成したとしても乗る人不在の大赤字路線になるのでしょうから。それも国民にツケが廻るのでしょう。
そのリニア・リニアの連呼の頃、牧之原台地、菊川のご門徒さんの法要があり生産されたばかりの新茶~あの菊川の茶娘がプリントされたパッケージ~をいただきました。
まだまだお茶の生産に希望があった頃、逝去された故人は周辺茶畑を購入し続けて大きくその業を広げたといいます。
ところがご主人が病によって倒れ、なお最近の茶葉価格下落傾向に陥り継続困難の現状について奥さんが吐露されていました。
それでもご主人の妹さんたち80歳近い皆さんのヘルプによって今年は何とか新茶を摘むことはできたとのことでした。
乗用摘採機の有無を聞けば維持管理に費用がかかるのでその使用はナシ。本体は普通自動車一台分。替え刃やらメンテ管理の費用が膨大になるといいます。
畝を跨がせて両脇二人で摘採するタイプの茶摘み機を使用する
そうですが、あと一人、摘採袋の持ち手がいれば「乗用がなくて
もOKだよ~」と。
とはいえ、それは古い農業のカタチ。
三人工の人件費を考えればどうなんだろう・・・と感じます。
皆さん殆ど親類のボランティア感覚だからこそできることでしょうね。
息子さんがいますが、実家農家は継がないと。
サラリーマンで外から確実におカネを稼ぐこと、それ以外考えられないのでしょうね。
今年はこれまた茶葉の価格が酷く一番茶は何とか出せたが「ニ番茶の価格が怖い」と。
「400円(㎏)割れたら捨てた方がマシ」といいます。価格は納入後しばらくして決まりますのでどうにもならないでしょうね。
まずはその価格を割っていることは確実。
肥料代、農薬代で大赤字になっている模様。
茶農家の高齢化と人手不足に後継者不在そして追い打ちが茶葉価格低迷。
これだけ値上げ値上げと騒がしい世の中で何故に茶農家だけがイジメられるのか。
静岡の農といえばやはりお茶でしょうよ。
その惨状について触れず、リニア業界への忖度の弁、腹が立つ。
見殺しにしているようにしか見えません。現場の窮状を知らないのでしょう。本当の死活問題を。
扨、画像は三河地区歴史冊子「さんえん」のNo.85より。
厳密にその発行者を記せば「三遠地方民族と歴史研究会」ですが、その研究会の二村順二氏による論文の掲載がありました。
タイトルが「夏目氏と明善寺」です。
そのタイトルといえば拙ブログで何度か記していましたので興味深くその内容を拝見すれば、何と拙寺の名まで。
有難くも唐突すぎで仰天させられました。
私の明善寺といえば住職を亡くされた坊守さん、息子さん、岡崎の寺に嫁に出た娘さんと僅かな時間ながらお付き合いをさせていただいたことの思い出。
岡崎法蔵寺の成瀬藤蔵正義の墓の発見に至ったのもこの明善寺からでした。
その後のご無沙汰失礼について日々もやもや感が滞留するばかり。
堂内阿弥陀さんの前で今一度経典拝読をしたいものです。
2024年
6月
20日
木
叔母の希望は鰻 「田沼意次物語」オーディション
早朝は依然龍神さん(昨日)が去ったあとのおどろおどろしい空気が流れていましたがしばらくしてお日様と青空が顔を出してくれました。その件は予想通りでした。
伊豆方面ではその豪雨で大層ヤラれたとニュースがありましたが当地は、少なくとも私の周辺での被害はなかったよう。
3月以来「鰻喰わせろ」と、ことあるごとに叔母の伝言を聞かされていた私どもでしたが、月曜日に火曜の土砂降りが明けるとの予報を信じ翌水曜の叔母の外出を施設に予約していました。
毎度記せば叔母(父の妹)は本年90歳。
軍医・皇宮警察だった夫の遺族年金+自らの年金によってその施設に入所しています。
永田町の大層なオエライ議員さんから「早く死んでくれ」風の嫌味を言われているその世代一員ですが、ぱっと見、なかなか元気でしぶとさ強烈。
一時酷かった痴呆の症状も完全に一掃されています。
信じられないことばかり。
鰻など高価かつカロリーのある食べ物は控えたいというのが最近の私どもの心情です。
「次回、お誕生日にはハンバーグか別のお肉などにしよう?」と奥方が打診しました。
ファミレスで誤魔化す作戦を進めようという魂胆ですが「誕生日(9月)までには時間が空きすぎ」という指摘とその際は必ず鰻でなくてはダメとの注文でした。奥方と苦笑いするだけ。
鰻はその店の普通サイズを注文し、あっという間に平らげていました。
お隣には3人組の年配者(明らかに叔母より年少)が自家用車で訪れていましたが、叔母の所望したものと同様のサイズながらいずれも「ご飯は少なめにして・・・」と店員さんに。
叔母はメニューを見回してから「肝焼きも食べたい~」と言い出しましたがいくら何でも・・・と心配になりそれを制止したくらいです。
当人は「100まで生きる」と相変わらずの化け物的弁舌。
このような高カロリーのものを毎度食するのを付き合っていたらこっちが先に逝っちまう。
ちなみに「奥の墓道」氏は「鰻はここ数年食べてない」と。
尚、施設からは入所者から「何を食べて来た?」と聞かれたとき「鰻」といわないよう釘を刺されているとのこと。
私に「何といえば・・・」と叔母が問うので「焼きそば」とでも・・・と。
入所者の皆さんも鰻は羨望の食べ物なのでしょうね。叔母も肉は時々出て来るが鰻は出ないと。
家族が一緒に外出させての時間を持つということもそうはないでしょうし。
これは叔母のお頭がハッキリしつづけているが故できる事。
私と奥方の名をあげて「鰻はまだか」とそれは絶対に忘れることなく、ややもすれば「電話機を貸せ」と暴れんばかりの様。
おそらくその鰻こそが生きる希望になっているのかと。
痴呆になれば食べたい物も外出の件も口に出さなくなるでしょうから。ましてや私どもの名など言えるはずがありません。
その勢いを見倣って私どももそのあとに続けるよう気合を入れなくては。そうあれば仕合せ。
かつて幾度か記していますが、ご長寿により国からガッツリと年金をできるだけ長く積み上げて奪取してやりましょう。
政治屋さんでそれを心配する輩が時々出てきますが、何より先ず自分が死してそれをお示しいただくこと、見せて欲しい。
叔母はまさに「ダイ・ハード」婆です。
扨、昨日午後は史料館から長谷川氏が掛川からのお客さんを連れて来訪。本堂の見学が主旨ですが、掲示板用ポスターを持参されました。
先日掛川のホールで今井信郎の演劇についてのポスターを紹介しましたが、そのグループらしき団体の演劇の件。
相良のホール「い~ら」にて来年1月19日公演の演劇「田沼意次物語」の出演者オーディション(20名)を開催するとのこと。
地元から素人さんを集めて劇を作る・・・悪くない企画です。
②③④は叔母を送っての帰路の景色。
榛原から原に上がって平田寺に抜ける道を選択しました。
①は西の空②は東、駿河湾と伊豆半島が見えます。
③は南。今季刈り込んだ茶畑の左奥に2年ほど放置されている「茶林」、その左奥に5~6年かそれ以上放置されているであろう「茶森」の図。
各所で茶畑が茶林→茶森に変化(へんげ)しています。恐ろしい。
2024年
6月
19日
水
杉と龍(水)は相性ヨシ 室生龍穴(吉祥龍穴)
朝から夕刻まで土砂降り。
時折心配になって本堂、庫裏仏間と雨漏りの有無を見回りに行った次第。一時的ですがあたかも龍神の襲来を思ったほどです。
小雨になった夕方、まだ日があるうちにと先般東側墓地に設置した浸透ますの確認に。
鐘楼前からの通路が高くなっているためだとわかりましたが墓地南側のプール状態は解消されていませんでした。
ますを設置したのが墓地北側の端でしたが、低くなっている南側の地盤を上げるか南側にもそれを設置するかで対応するしかありません。やはりやるとなれば低コストの浸透ますの設置でしょうね。
しかし土砂降りのあと、スグにお参りに来られる方などそうはないでしょうからしばらくは様子見にします。
次回コンクリ屋さんが来られた時にでも一応追加料金について問い合わせはしてみますが。
コンクリを打てば水の逃げ場が無くなりますから排水の件配慮しなくてはなりません。
ちなみにその工事は祖父の代の仕事。コンクリートは雑草の繁茂を抑え歩行もしやすくなりますが・・・。
梅雨を心待ちにしている人もいれば毎度頭を痛めて忌み嫌うべき季節と感じる人がいます。
どちらかといえば私は後者。水には苦労させられています。
まぁその龍神さんからすれば「勝手な事を・・・」と人間がそれぞれの自己の都合だけで生きていることを嗤うでしょうね。
扨、先般室生寺五重塔の相輪の風鐸付きの九輪、その上の「八弁
受け花に乗った水瓶」について記しました。
水瓶(すいびょう)は八角形の傘蓋の形をしていていますが塔のトップに特異なものでした①。
これには室生寺に伝わる龍神伝説というものがあります。
室生寺創建に関わった修圓と弘法大師の「死ね死ね」呪詛合戦の一つでしょうか。
どちらが先に雨が降らすことができるのか、どちらの祈祷に軍配があがるかの勝負をしたそう。そのために修圓は日本中の龍神をこの五重塔の水瓶内に封じ込めて空海の祈祷を消失させようとしたという伝承。
現代人からすれば「しかし、まぁ~」という風に呆れてしまうようなお話です。お天気お姉さんのいない時代、当時の人々はその祈祷の成果(雨降りは龍神の差配で決まる)をただの「偶然」(今で言えば大気の流れあれこれ)によって褒めもされ貶されもされて・・・さぞかし大変だったでしょうね。
よって龍神さんの気まぐれで、雨が降らずに作物が枯れては困る人、大雨ですべてを失う人が出ること、その龍の仕業をただただ畏れていたのでした。ほどほどにしてほしい・・・とばかりに。
人智を超えた不都合の原因を実在しない龍に向けた素朴です。
ただ水が豊富でキレイな地といえば杉の成長が良いのでしょうね。毎度それには圧倒されます。
まさにスゴイ!!室生寺周辺の杉たち(→三本杉)。
画像①は龍神を閉じ込めたという水瓶(すいびょう)。
②~は龍穴神社、先日記した西ケ滝のトンネルを出てスグ(場所はこちら)。
掲示板には室生寺は龍穴神社の神宮寺との件。
室生寺は龍神信仰の寺でもあるわけですね。
「勧請杉」という木があり例祭時には勧請綱(龍綱)なるお飾りが龍穴神社前の杉と室生寺天神社の木に掛けられるとのこと。
拙寺の玄関脇の杉、あそこまで大きくなるには600~700年?
現代人の嫌われ者となった杉ですが、お調子にのっているとそのお友達の龍(天変地異の喩えとして)にきっとヤラれますね。
2024年
6月
18日
火
七曜紋の引き戸金物 何となく日々開け閉め 中止
夜間には大雨になるとの予報がありました。
それ以降「梅雨入り」の気配がありましたので、午前中にセメント打設作業を2か所ほど。
庫裏の中が暑すぎるせいか、外仕事は案外ラクなものでした。
途中砂が不足して購入に走ることになりましたが。
扨、先日は七曜紋の瓦についてのあれこれを記したのでしたがこのほどその七曜紋についての別のその存在について「まだあった~」と「ハッ」と気づいたものがありました。
日々そちらの襖を開け閉めしていますが、その襖の金物がそれです。
その件はずっと頭の中にあって、一応承知していたものですがあまりにも日常に埋没していたためどうしてやろうかなどという気は起こりませんでした。
金具もしっかりと襖に装着されていますからね。
私が生まれる以前からその金具が付いた襖はあって、何度も何度も私含め、人の手に触れられているのでしょうが、何故か現存する物は表面左右2枚のみ。表面とは旧玄関八畳間のことです。
元は4枚襖のすべてその取っ手金具装着されていて、襖の張替え等の際などに故意か錯誤か「消えた」説が。
代々当家の者のたれかが処分したのか、はたまた戦時中に陸軍により庫裏の本堂側と本堂が接収されていたこともあって、父も「何だかわからない」と言っていました。
ハナから2枚という説もありますがね。
また何故にしてそれが当家に伝わっているのか。
お城の廃却のドサクサで持ち込まれたのでしょうが・・・
それが普段使いの日用品として延々と使用され続けられていたのですからね。
どう見てもその出自はお城の殿中と推察するところですがその大切な遺すべき品という感覚はまったくナシでした。
まぁ当初はその手のものを「相良に遺すな」というのがお達しでしたから、さりげなく、何となく庫裏の取っ手と替えたということ、考えられます。
何故か先日、その存在にあらためて「ハッ」と気づいた私は、市販のそれを新たに買い求めて交換、その日用品扱いを今回中止させたのでした。
以前は金箔で仕上げられていたことがわかりますが今は摩耗が激しく地肌が見えています。爪が何度も当たって削られたようでもあります。
御門徒様の年配者の方でその存在をご存知の方がいます。
それを「金製の引き戸」と仰っていました。
「違います」と返してもまったく取り合ってくれませんでしたが。
中央に大き目の七曜紋、上下左右、合わせて5か所にそれが。
盂蘭盆会法要の際に皆さんに披露したいと思います。
他所のその存在、そしてその形状の比較をしてみたいものです。
いずれかの課題ですね。
縦110mm×横95mm 背面凸部 縦53mm×横42mm。
2024年
6月
17日
月
体に悪い食習慣 室生寺トンネル前 西ケ滝
午前の法要が始まる前には雨があがって涼しい風が。
一晩中だらだらと降っていましたからね。
施主は障子を開けっ放しにしていましたので、蚊の襲来が気がかりでしたが、大丈夫だったよう。
しかし庫裏に居てその不快はありました。
湿気と高温と蚊、最悪ですね。
特に夕方に西日の直射を受けた時・・・たまったものじゃない。
墓参は地代の山の上でしたから、そればかりは上々の出来。
この時期旬の私の好物にトウモロコシがあります。
特にこんがり焼いたそれを所望することもあって奥方はその購入をとても嫌います。
「どれだけの糖分を接種するつもりだ」と私の健康のことを気遣う風に面倒な焼きトウモロコシの「調理」を忌避したいという躰。
よって最近は以前ほどそれを購入しようという気にはなれなくなりましたね。
昨日のテレビで「食の単一化」と「超加工食品」繁盛の様を伝えていました。現在進行形の世界のリスクという感覚。
トウモロコシの糖分もそうですが、各調理そして特に世界に蔓延するスナック菓子の大繁盛。
そのトウモロコシの需要に応じるべく森林エリアの破壊も進んでいるよう。
そのトウモロコシ一辺倒の食物原材料使用とそれを使用した超加工食品がまた人の健康を蝕んでいるのでした。
トウモロコシは体に悪い・・・最近は奥方にそれを刷り込まれています。
メキシコの小学校にて、近いうちに2人に1人が肥満だといいます。よって将来糖尿病患者で溢れるとの危惧が。
私も中南米系の子供たち特有の体格としてそれを思っていましたが~それはかつていた横浜辺りのこと~まさに彼らの食生活が起因しているのでしょうね。
メキシコにはまともな食材・・・野菜・果物など~は豊富にあるそうですが輸出用に高騰した影響もあって国内でも1年前と比べて2倍になっているといいます。
すると手軽・カンタン・安価、そしてかねてから「美味しい」と脳に刷り込まれた単一食材を加工し超加工食品といわれるいろいろをMIXした食の生活をしざるを得なくなって健康を害してしまうというメカニズム。
私の食生活の改善テーマなるものは健在、まだ肥満体とまではいかないもののその「食生活改善」の語は耳が痛いところです。
脳内に刷り込まれた「美味しいもの」の類のうち、体に悪そうなもののオンパレード。
健康のためにどう自分の脳内意識と闘っていこうか・・・です。
食は生物が生きる上で必須の行為ですが、それだけに収まらず「できるだけ美味しいものをたくさん」そして「いつもいつも」の無制限煩悩。
番組に寄れば脳は「喰ってため込む」指令は出すが「喰うな」の指令は出さないと。
糖尿病になって苦しく煩わしい人生を送らなくてはならないと思えば、今一度それについて脳に任せきりにせずその本能に抗がうことができるかどうか・・・それが最大のテーマ。
アルコールもタバコの誘惑も同様でした。
扨、あの時は工事通行止めにより大野寺から室生寺へ辿る道は諦めて迂回しました。
室生寺トンネルの入り口右側 (場所はこちら)に小さいながらも滝が目に入りましたので車を停めしばし涼しい風を前に深呼吸。看板には西ケ滝(にしゃたき)と。
渓谷が山を刻み山系が連なりますから他にも複数の滝があるようです。
その直近、雨量はそれほどでもなかったため、おとなし(音無し)めの滝の感ありますが、場所が場所だけにかつては滝に打たれる行に使用されていたよう。
私にはそれはムリ。
かつて海上、海中で七転八倒したことがありましたが、それで十分です。
体にイイわけがない。だいたい体が冷えるでしょ。
2024年
6月
16日
日
教区主催のイベント落語会へ 掛川
昨日土曜の午前、法務の予定はありませんでした。
なぜならば掛川での教区主催の落語会の館内スタッフとしての集合が13時ということてで12時にはここを出立したかったからですね。
午前からパワー全開で動いていたら消耗することは必至、体力温存を図りました。
参加者は予想外に少なく、私どもの仕事はほとんどなし。
当初、心配されていた駐車場のキャパも「80台分の余裕」があったとのこと。
まぁ、どちらかといえば駐車スペースがなくなったので「お引き取りください」と言い放つよりは主催者としてはマシですがね。
200人程度の来場となったわけですが、まぁ落語の寄席という感覚では「そんなもの」と捉えることもできるでしょう。
私が会場で驚いたのは1階フロアから下方に見下げてステージがあるところ。イキナリ階段を降りていくワケですが、そういう全自由の席の場合はとにかく「前へ前(の席)へ~」と背中から声を掛けることは鉄則。
しかしその決して緩やかとは言えない、手摺も無い階段を年配者の背中を押すが如くそれをけしかけるのはイヤな感じでした。
私は「階段が急でゴメンね 気を付けて・・・」とも付け加えましたが・・・
年配者=足が覚束ない・・・よって転倒について気がかりではありましたがその時はどうにもならないことと諦め。そうなったらどうすんだよ~と心中思いながら。
年配者からすればその階段とステージはあたかも大球場スタジアムの2階席トップからフィールドを見下すような感覚ではないでしょうか。
怖がっている方もいらっしゃいました。
また私はタイトルの「教化」という語にどうも違和感がありますね。
まぁ以前からその語は使われ続けられていて、今更それを言ったとしても「ふん」という具合に流されることでしょうがその語にはどうしても「上から目線」を感じてしまいます。
昨日の私ではありませんが「無知な者に教えてやる」といったところか。
その文字が二つも入った看板・・・って・・・どうよ・・・ってところ。
そろそろ違う表現に変更すればいいのに・・・と思います。
良き方向に変化をもたらす「化」ならいいのですが「化かす」のイメージが先行すると、一般人がそれを見たら「何か洗脳でもされるのか・・・」とも受け取られるかも。
古いこといろいろを継承していくことは大切ですが自らも少しはいい方向に変化しなくちゃね。
勿論私も・・・
③は会場ホールで見かけたポスター。
時間が合えば行ってもイイかも・・・とは思いましたがその日曜日はまったく動けません。
気持ちとしてはイベントいろいろ、相良、拙寺直近のい~らを会場にしていただければラクなのですが。
地元御門徒さんも気軽に足を運べたでしょうね。
2024年
6月
15日
土
駿府浅間神社関わり各々 我が無知を知る 「踟」
予報はおかげさまで外れ気味。
それほど天気は悪くならないような。そうであったら有難いことです。
昨日もいいお天気。私は殆どエアコンの効いた室内に滞留、外気の夏の様とは隔絶されていました。
幾度かその辺りのことを記していますが、齢を重ねてあるべき姿というもの、持論を記せば「聞いて話して、できれば書く」を厚く心がけその習慣に自らを浸すことが肝要と考えていますが、それには基本、外に出て人の中に身を置く事が一番に手っ取り早いところ。
ところが外にも出られない事情にタイミングもあるワケですから、自宅にてでもその習慣を維持したいもの。
その聞く事と書くことは何とか独りで可能なことですが話すことは難しいものです。
話すとは思考しながら発声することですが、それを単独で行うことに最適なのが仏間での仏との対話ですね。
私は声を出しての正信偈の拝読を推奨しているワケですがまぁ何も経典の拝読だけでなく、好きな歌など口づさむことでもOKでしょう。
ある御門徒さんでは「カラオケ命」のような趣味生活をされている方がいらっしゃいますが、それも価値ある暢気生活ですね。
それによって唾の飲み込みの訓練にもなって誤嚥性肺炎の予防にも繋がるのですから、声出しは特にリタイア後の不可欠習慣。
扨、一昨日昨日と静岡市内の葬儀会場にお邪魔していました。
故人は相良出身の方で浅間社関りの活動で大いに動き回っていた方です。
私は以前その方から「木遣り」について語られていたことを思い出しましたがその何たるかについてまったく存じ上げませんでした。
昨日初めて知ったことですが故人はその浅間さんの木遣りの会の会長さんだったわけで、その団体組織の皆さんがおそろいの法被を着けてホールに登場、出棺の際その見送りに30人ほどの皆さんの合唱がホール内で響いたのでした。
繰り上げ初七日の法要までもいらっしゃったということです。最近ではあまり目にできない光景でとた。
その会は年配者方々の集合体でしたが、これこそリタイア後の「積極の姿」であると感じた次第。故人はそれを纏めかつ組織を大きくしていったといいます。
また「踟」の字について初めて出会いました。
「行きつもどりつする」・・・から「ねり」?
当流では二河白道を前にして「行け」と「来い」の声があってその躊躇はあり得ませんからね。易行道なるが故・・・信じて渡るのみ。
まったく別世界に入り込んだような式でした。
今回、私の知り得たことは「私の知らないこと たくさん」。
2024年
6月
14日
金
ご本尊のある生活を 本尊裏書の件
土日より天気が崩れるとの予報。
いよいよ梅雨入り・・・の感。できればカラ梅雨を希望しますが。
そして予報では晴れ間が広がるはずだったのですが昨日は殆ど曇りの一日でした。
というわけで、花ガラ袋満杯につきそれに雨が降り注ぐことは避けたいところですので朝一番に地頭方処理場へ。
帰宅してから他の雑務色々は我慢して夕刻にある法務の準備をして、14時には出立。
静岡にて17時の開式でしたが、施主家族とは今回の法務詳細についてお話することができなかったため早めの到着を目指しました。
終了後18時前には帰路につきましたが雨がポツポツ。
天気は結構に不安定ですね。梅雨間近ということか・・・
扨、処理場には色々な物を持ち込んで処分依頼をしているワケですが、これまでそちらに持ち込んだことのないもの・・・といえばお内仏。要は仏壇一式です。
お内仏の閉扉式とご本尊のお焚きあげを依頼され、ついでに外箱(仏壇)の処理まで頼まれたことがあります。
ごみ処理場にそちらを持ち込むこと自体憚られるところですし、処理場担当からも拒絶されそう。
そこは試したことがないのでわかりません。
その引き取りについて頼まれた場合、かつてはご本尊と一緒にお炊きあげしていましたが、実はそれを細かく破砕して火にくべること淡々と・・・とはいってもあまり気分のイイものではありません。特に大型のそれを壊すところなど人に見られたくありませんからね。
よって最近の私はそのストレスを私が買って出ることもなかろうと「仏具屋さんにお願いしましょう・・・」とお断りすることにしています。
仏具屋さんの引き取り費用はどのくらいか、知る由はありませんが、金仏壇の中古品は人気で輸出して高値で取引されていることもあるよう。
先日来、石屋さんの墓塔の新規建碑について少なくなっていることを記しましたがこの仏壇、お内仏を新規で求めようという家もかなり減っているのでしょうね。
どちらの家でも最近は邪魔もの扱い。置く場所がナイ・・・
ご本尊を新規に招くこともありますが、ハコは要らないということ多くお見受けします。
画像は本山東本願寺発行のパンフから。
ハコはともかくとしてご本尊に手をあわせる習慣、生活は捨ててはイケないでしょうね。
子、孫はその親たちの後ろ姿を見て成長します。
頭を下げる、師主知識への報恩謝徳の心を伝えてゆくこと、一番に大切なことでした。
本山発行のお軸には必ず「裏書」があります。
ちなみに当流では各寺院の本尊阿弥陀さん木仏にも裏書という認定証があります。
その「裏書」とはどちらも「本山が確かに承認しました、よってインチキではないよ~」という証に他なりませんが、仏像自体にはそれ的のものを記すことができませんので別途小型の軸としてそれを発行します。
勿論、それを本山にお願いする際はご依頼金がかかることになります。
一般家庭のお内仏をお軸から木仏に変更する際も新規導入する阿弥陀さんについて本山に「点検」を依頼して裏書を発行していただきます。
それを木仏点検といいました。
それも私はやったことがないので詳細については不明。
また、お東→お西またその逆など本山を変更したりする際にもその点検依頼は必須とも。
「本山門主の承認」がないものは本尊として認めない・・・というニュアンスもあったのでした。
2024年
6月
13日
木
岐阜タカシマヤ「みわ屋」から金華山
やらなければならない庫裏内での雑務各あって、外仕事の宿題はパスさせていただきました。
先般壊した墓と隣の墓との境界の処理もそうですが切りっぱなしの長い丸太の処理等です。すべて来週のお天気を見て、ということになります。
趣味のハイビスカスたちの植替えもそうですね。
昨年の秋に挿木したものが花を咲かせるまでに成長していて、本格的な夏を迎える前に一回り大きい「家」を提供しなくてはなりません。
扨、最近は当地でも「閉店します、長らくのご愛顧を感謝・・・」の如くの詞が店頭にてお目にかかることが増えています。
その件、枚挙に暇がありませんが、拙寺近隣のご門徒様お菓子屋さんもそうでした。和菓子8洋菓子2くらいのウェイトかと。
現状、それを惜しむ声が多数あったということから「今しばらく頑張ります」の貼紙に変わっていますが・・・。
また県内中堅クラスの相良大沢にあるお菓子屋さんの支店にも閉店の報せを記す書面が貼られていました。
先般榛原病院近くのその店が撤退したこともありますが、お菓子は今時振るわないのか・・・と。
要は健康ブームでしょうね。
一昨日のドックでの医師との面談で、タバコも酒もやらないのに「この数値は・・・」と追及されて私の甘いもの、お煎餅好きについてぶっちゃけたわけですが、夕食後にお菓子を食べるのは「命取り」になるとのご指摘がありました。
また、もし食べるなら昼か朝といいますがね。
そういった中、ケーキなど若い時分に食べた重ための洋風菓子などからは遠ざかっていました。
やはりそれなりに健康について気遣いがあったからですね。
ということで世間様も皆ケーキからは離れぎみになったのかも知れません。
若い子などには「ダイエット」の風も吹いているでしょうし。
よく聞く話ですが、坊さんは菓子を頂戴すること、お供物のお下がりにお菓子がつきものになっていますので「糖尿病」になりがちとも。
運動不足で甘いもの・・・それはかなりヤバい兆候なのでした。
ただし「あなたは血糖値については良好」とのお墨付きはもらいましたが。
いずれにせよ改善の余地がありますので何とかしなくては。
先日はまた、洋菓子店の倒産件数が増えているとのニュースがありました。その原因については、円安による原材料高騰があるといいますが、聞くところによると相良大沢のその店舗は賃貸借契約終了とその更新手続きで意見の相違があったということです。大家さんと店舗との関係がこじれるパターンもよく聞くところですね。
乃庄、大栄館の相次ぐ閉店で相良人が「寿司屋難民」といわれるようになってしばし、やはりこのほど大沢の寿司屋さんが店じまいするとのことですが、その理由もそれだとか。
この町の店の閉店ラッシュの件、全国的に見てもそう珍しいことではなさそうです。
先般、百貨店大手の岐阜タカシマヤが閉店(7月31日)とのニュースを聞きましたが、その手の地方の旗艦店が次々と姿を消していく様を見せつけられている昨今です。
そちらも賃貸借の問題があるようですが、それとは別につまるところ「頑張れば頑張るほど取り返しがつかないドツボにハマる」理論がその判断の背景にあるのでしょうね。
頑張り続けることがマイナスならば「さっさと諦める」が肝要という考え方ですが、本来日本人はその判断が超がつくほど苦手ですね。
まぁそれは戦時中の大本営の思考能力劣悪の数々から判るというものです。現在で言えば大阪万博でしょうかねぇ。
私の周囲ではどなたもそこへ行こうなどいう奇特な方は見えません。
奈良大阪方面にはまだまだ拝見したい墓石その他遺構はありますが、そこに行くこと、私は「100%無い」と断言できます。
バス遠足に入れる? ないない・・・。
画像は以前奥方とうろついた岐阜にある百貨店タカシマヤの食堂街からの図。
「みわ屋」という飛騨牛を食べさせる店のランチタイムでしたが、値段の割にボリュームもあって美味しくいただきました。
奥方と各所うろつく時はそういった時間は必ず持たなくてはなりません。
私独りの場合はまず、昼食ナシで時間を惜しんで歩き回りますが、そうでもしないと奥方は付いて来てくれませんからね。
ハカテラシロはNGながらデパ地下とランチがコースにあればそれなりに。
尚、タカシマヤが無くなっても他にも岐阜県内にそのお店がありますので、「今度また行こう」。
ホントは血尿が出るほどに歩くぐらいの気合が必要なのですがね。
みわ屋の窓際からは金華山岐阜城④と市街の様子が。
⑤は長良川対岸へ向かう橋の上からの岐阜城。
「奥の墓道」氏との「地獄の登攀」(または)が思いだされます。
この城を攻めあがるなど「どうかしている」と文句を言いながらただひたすら登りました。そしてあの時は山頂でぶっ倒れましたね。
岐阜には色々な思い出があります。
2024年
6月
12日
水
安静は体にワルい 「ハァハァ、ゼイゼイ」のすすめ
昨日4時に目が覚めて雑務いろいろ。
午前中には人間ドックの予定もありました。
榛原病院の8時10分からの受付開始に早い順番をゲットして早々に帰ることを毎度気にかけているのですが、昨日は、例の石塔を移動だけでも・・・と鐘楼下に運んだりしていたため、結局到着も遅くなって3番でした。
しかしよくよく考えてみるとそれはあまり意味がないような。
その日たまたまなのでしょうが「胃カメラの先生の出勤時間は〇時〇分頃」などと言われてただただ、ぼけ~っと外を眺めている時間がありましたので。
内視鏡受付に辿り着いても待ち時間多すぎ・・・
そちらでは皆さんのマスク装着の様を見て、そういえばまたコロナが繁盛していることを思いだしてハッとさせられました。
「こうなったらしかたがねぇや」の開き直り。
胃カメラの判定が一番気がかりでしたが、医師より「変わりない」との言葉を戴いて安堵させられた次第。
検査項目すべての結果は後日になりますが、最後の医師の所感の時間にはいつもの如く、「運動不足」の4文字を重ねて指摘されてしまいました。
初めてのご指摘でしたが心電図を見せられて、確か「T波」とのことだったかと思いますが「低すぎる」とのこと。
それが低いということは「心臓の血管が細くなる」とのことで心筋梗塞などのリスクが・・・との談。
心臓はある程度の負担がかからないと血管に血が流れなくなり自然と細くなるといいます。
ということで一日数分でも「ハァハァ、ゼイゼイ」しなさいと。
要は運動して時に血をたくさん血管に通せということです。
そういえば「安静」にしてのんびりしてばかりいた半年間でした。
殆どすべてのドックの項目におけるネガティブサインはその運動で解消できうるもののようです。
扨、11時30頃寺に戻ると石材屋さんが境内墓石墓じまいによる撤去工事が進行していました。
昨日ブログで記した墓塔とは別の墓ですが、墓じまいばかりで石屋さんは今、頭が痛いでしょうね。
逆にここ数年はそれだけを業にしても成り立ちそう。
石屋さんには仕事が終わったらユニックとオペレーターを兼ねて少々の時間をお付き合いしていただくことになっていました。
それは数年前に奥方と息子の三人で切り倒そうとした槙の枯れ木の処理。
その大失策、切断した木を落下させて墓石を欠けさせた経緯あるいわくつきの木です。
時間が経過してそれがまた倒れでもしたら・・・と思案していたのでした。
その機会を得たことで無理やり裏の道に4トン車を入れてもらったということです。
そのブームを繁茂した枝木の中に突っ込んでいただき木の上部をフックにひも懸け。
そして私のチェーンソー作業は難儀しました。
案の定、材は乾燥しきっていてカチカチ、思いのほかてこずってしまいました。チェーンソーは熱を持ちすぎてなまってしまったかも。
残りの下の部分も一気にやっつける予定でしたが、こちらは朽ちるを待つが正解と放置することにしました。これ以上のヤル気が失せました。
南側墓地に倒したきりになっている材はさすがに重たく、せめてあと一回は切らないとどうにも動かせませんね。
ひきづり出すだけでも大変な重たさでした。いずれの機会に。
終了後、ひと風呂浴びて、差し入れいただいたばかり、旬の「甲州の宝石」を頬張ってから遅い昼寝を。
筋トレ風の仕事はしているものの、「ハァハァ、ゼイゼイ」と肝心の心臓には負担(いい負担)にはなっていないのでした。
暢気そのものの生活という感もありますが。
①は榛原病院6階から西方を見た図。
2024年
6月
11日
火
毛原廃寺跡礎石 奈良の美品 円形と多様なカタチ
雨はあがって朝から青空が広がる気配。
私はその作業を、やっつけようと境内のある墓石の前で独り線香を添えて簡単なおつとめを。
墓石と言っても墓石の形をした供養塔。これまでありがとう・・・です。
それから大ハンマーを担いでその墓地へ戻りました。
竿と呼ばれる上部の主たる石塔とそのベースの石を私なりの方法で外したあと、その下2段のコンクリート型枠で作られた3段目と4段目の除去ハツリ作業。
コレはある相良地区の名士がおそらく使用人だった若者のために建碑した墓碑ですが建碑されて約80年を経ます。
遥か昔に無管理になってコンクリベース部は朽ちていくままに放置されている墓標です。
相良周辺では名の通ったその建碑者の娘さんが健在ということでその墓石墓じまいを打診するためにお会いしました。
一週間ほどまえのことです。
すると撤去工事について快諾いただきましたので、早速石屋さんを呼んでその工事着手について折衝したのでした。
事情が事情だけに他の拙寺の工事と抱き合わせにして格安の見積もりを頼むと「本来は20万円と言いたいところだが17万円で」と。
それでも先方に配慮して「もう一声」何とかして欲しいと図々しく頼み込むと15万円を割った金額の提示をいただきました。
考えてみれば墓じまいといえども私の代は勿論、父の代祖父の代まで運営費その他いろいろな経費について御依頼したことはありませんので、他の御門徒さんからすれば不満が出ても致し方無いところではあります。
その書面を持って先方宅に再度赴くと、「よく考えて子供たちに相談した結果お断りすることにした」と。
そして3回目に先方から呼ばれて伺った際はヘルプの年配の方二名が待機しておられ「支払いの必要はない」とまで断言されていました。
私の言い分としては「貴女のお父さんが墓石の建碑者です」ということだったのですが、これ以上の話し合いはムダ、もはやその主張は不要と判断しそのお宅を退去したのでした。
「トラブルは御免」というところでしょうか。
総代会、世話人会にその件を報告し、処分費について御門徒さんからの運営費で支出することに了解を得ることにします。
解体に関しては私がDIYで行いましたが、残材の処分費は業者さんに依頼する他はなし。
これから来られるコンクリ工事の業者さんに泣きついて何とか片付けてもらうことにしましょう。
その墓碑の主たる部分は当分の間は鐘楼のベース部分に寄っかからせて置いておくことにします。
実は竿部分を確りと立たせてそれとなく設置したのですが、奥方からそれでは「何かの墓と誤解される」「むしろ適当に~」との指摘がありました。
よって「墓標ではない」を主張すべく午後遅くにでもその作業に取り掛かることにします。
午前はやることいっぱいなのでした。
ちなみに、あの手の重量物の移動は先般の石垣いじり(50個以上)以来でしたがまだまだイケることを確信しました。
ただし石垣の石は25~30㎏程度ですが、墓石は80~100㎏はありそうです。
よってゴロゴロと転がして移動させる程度ですね。
大ハンマーを振り回したこともあって、関節各ミシミシ、両腕パンパン。
扨、毛原廃寺跡には想像を絶する空間が広がっています。
山の中のこのような地にかつての大伽藍の存在があった・・・それを考えるだけで不思議世界に埋没。
昨日も少々の礎石画像を示しましたが、その夥しい礎石の数にはまた圧巻です。
何しろデカイ。
私も本堂の礎石ほか「石」というものに馴染みがありますが、あの大きさから推測するその上物の大きさたるや如何に・・・
昨日の掲示板の如く、かつて昭和13年に売却されて行方知れずだった物があり、後年返却された・・・という経緯があったとのことですがそれにしてもこれだけの物をどういう権威があって売り払ってしまったのか・・・無管理という時代があったのでした。
私は元あった場所に正確に戻されたのか、そちらの方も心配になってしまいますが。
それにしてもこの重量物の移動について、もし私なら・・・を考えてしまいます。やはりこればかりは頭数が必要です。
ユニックなどがない時代ですからコロとロープを駆使する他はないでしょうね。
しかし、もしこれが一つ二つ庭にあったとしたら・・・最高の趣になることは必定。
「欲しい」という気持ちは大いにわかりますね。
まぁ趣味の問題ですが。
2024年
6月
10日
月
唐招提寺並みのスケール? 毛原廃寺跡 今は人家の間
昨日午後も境内にてご門徒さんご夫婦と歓談。
「昨日、ようやく退院できました」と軽トラの助手席から杖で台地をとらえつつ奥様が現れました。
その入院は右膝に人工関節を入れる手術です。
リハビリの末「何とかここまで・・・」との歓びの声がありました。
その施術についての決断は私どもも承知していましたが、その出現の図はまさに「痩せた」感。
当人も「寝ていたものだから、ほとんど筋肉がなくなった」と。
現状、施術した右足ではなく、ひたすらそれをかばって体を支えてきた左足の方に痛みを感じるとのこと。
よく聞くところです。
そして自宅に戻って食べた食事が「物凄く美味い」を感じたそう。病院食のコントロールされた食事の辛さについて仰っていました。
これからどんどん美味しいものを食べて筋肉を付けていきましょう・・・と私。焦って転ばないこと、そして今後のリハビリがまず大事ですね。
入院となれば、これはまた安楽な状態を維持することが主眼となりますが筋肉はガッツリ落ちることは確か。
寝ていれば動けませんので運動は不可能ですからね。
ただ筋肉の減少を手をこまねいて見ているだけ、何とかならないものでしょうかね。病院にいるのですから。
治療の反面不健康にさせられる・・・そんな思いも。
先日「ハイジ」、いわゆる昔アニメにあった「アルプスの少女~」の映画実写版をざっと視聴しました。
当方奥方がそのアニメの視聴者だったということからその内容について登場人物の名前から各知らされていましたが、やはりその劇のメッセージは確りと伝わってきました。
男子が観る番組に非ずという観念もあってそのストーリーすらも眼中になかったのですが案外感動的でした。
一言で親の固定観念こそが子の害になる・・・ということ、そして都会の喧騒から離れた自然環境と自由活発・・・。体の健常はそこからなのだな・・・と。
たまたまその晩に別のチャンネルで「マッドハイジ」なる(おばかパロディー)映画が流れていましたが、それは10分で視聴をやめました。
扨、ブログで以前、下笠間永仁阿弥陀磨崖仏に、また山添村毛原の「山辺の御井(みゐ)」について記しました。
そちらで毛原とは京原からの変異を示唆しているようだと匂わせましたがその街道は奈良と伊勢を結ぶ古道であって古代の往還道であったかも・・・を推測するところです。
今風にいえば名張から室生寺に向かう道。
それはその御井の存在が後押しする材料となりますし、その御井のある場所こそが奈良時代の毛原廃寺跡ということになります(場所はこちら)。
歴史資料に登場することはなく、歴史から消えている感ありますがそれでいて唐招提寺並みの伽藍があったその痕跡。
2024年
6月
09日
日
中古ドラム缶仕入れて 加工の蘊蓄
境内テラス前での作業中、お参りに来られた御門徒様としばし雑談。
久しぶりに近くでお話をさせていただいたのでしたが、手に震えがあったことはスグに気づきました。
その旨おうかがいした方がいいかと思っていればその方から「今度入院する」と。
どういうことかその理由を聞けば、パーキンソン病での処術だとのこと。その病の名を頻度高く聞くようになりましたから、同じ悩みを持つ方がたくさんいらっしゃるということですね。
3年ほど前にその診断が出たそうで原因不明「一生治癒しない」といわれるその病気の進行を遅らせるための入院処置だそうです。現状歩行に支障はなさそうですしお参りには自家用車で来られていますがいずれ車椅子・・・というのでは困ります。
ご主人が亡くなってからパートタイマーで家計を維持している方です。復帰に時間がかかることもそうですが、病気の進行については特に辛いことです。
そのご主人が亡くなってかなりの時間が経ちましたが、私が寺に入ったばかりの頃、境内作業をしいてる私に、気軽に「いつでも手伝いをするから声を掛けて・・・」と気にかけてくださいました。
親戚の葬儀でその家の菩提寺の住職が火葬場に来ないことを憂いて「ちょっとタノム」と拙寺に連絡してくるほど他者への面倒見のいい方でした。
その奥さんの他のいろいろな事情と難題を思うと、声を掛けずにいられません。
「病院から解放されたらまた元気にお会いしましょう・・・」と別れました。
その火葬場の件ですが、同じ宗派でよく存じ上げる寺の大御所住職ですからちょっぴり困惑しながらおどおどしつつ向かったことを覚えています。
要は越権行為ということで。
当流でも「火葬場に同行しない」という申し合わせが一部の寺の間で広がっているようですが・・・まぁ、私は私のやり方で。
昔ながらの葬場勤行、葬列の名残すら消えていく・・・
坊さんの手抜きの如く見られても仕方ないか・・・
扨、数日前、中古のドラム缶を購入しました。
長尺の木材等を整理するためですが、お炊き上げ用のドラム缶が錆びて朽ちつつあることと、「その時用にあった方がイイかも」と思われるドラム缶風呂に転用・・・ということでしょうか。
中古ドラム缶は多様な場所に出回っているのですが、その大きさから配送料金はかなりの金額になることは必定。
よって近場の出物を待つわけですがこのほど150号線沿線の自動車パーツ屋さんにそれを見つけました。
勿論、軽トラで取りに行くことになりますが、価格は2500円。
相手からすれば、処理料がかかる廃棄物をお金を貰って「処分」してくれるのですから悪い話ではないでしょう。
一般の家庭には大きくて無骨なそれは不要、あり得ない代物でしょうが、拙寺では焼き芋の窯の製作などドラム缶の用途はまだありますし置き場所も工夫すればもっとイケそう。
しかし一工夫は不可欠です。
大抵のドラム缶というものは上蓋の取り外しはできませんので、用途にもよりますがそれを取り除かなくてはなりません。
そしてその外し方は各あって、要はカンタンとはいうものの地道な手作業となります。
トータルの時間も要し、結構に準備と思案をしなくてはなりません。
私の外し方は大概世間で行われている①上蓋の外周の縁部分上部をグラインダーで削っていく、のではなく②上蓋の外周部分の内側の上蓋の天の外周をドリルで穴をあけていくもの。
①のグラインダーで上部を削っていく方法はあとあとの使用に(天の縁が残らないため)少々のバリ取りだけで済みます。
ハナからのグラインダー作業は微細な粉塵との戦いになるためそれはパスしました。
よって②を選択しましたが、それはそれで縁部分が残りその処理にグラインダー作業とひと手間かけなくてはなりませんでした。
尚、ドリルでの穴あけはハンドドリルでは数が多すぎておはなしになりませんので、卓上ボール盤のベース部分を取り外し、ドラム缶の高さに合わせて作業台に固定し適宜ドラム缶を廻しながらボーリングしていきます。
無数の穴が開いたあと、穴と穴の間にタガネとハンマーで開口部を繋いでいきます。
尚、ドリル切削は刃先の冷却のためにこまめにCRCを噴霧します。
また前述したように外周内側に「天の縁」が残ります。
グラインダーでの処理は行ったもののドラム缶風呂として利用するのは少々技が必要かも。
次回製作する際は①でやってみようか・・・。
蓋部分③も廃棄せず、縁部分を均して保存しておこうと思います。
焼き芋の窯に加工するにはそれは必要です。
2024年
6月
08日
土
人によって少々違う「マンダラ」「曼荼羅」
昨日ブログにて記しました東京から来訪された方は先日東京国立博物館の特別展「法然と極楽浄土」の遺物たちを拝観してきたと(今週日曜が最終日です)。
実は私もそれ目当てに東京方面に向かうタイミングを計っていたのですが、あっという間に私の一番の目当てだったそれが入れ替えとなってしまっての残念無念。
よって次の開催が予定されている京都国立博物館にその望みをつないでいるところです。
京都での開催は10月といいますので、そこは拙寺バス遠足の日程が組まれています。
今回のバス遠足は概略行先は指定していますが行程・時間・昼食等を旅行会社に投げてしまっていますのでその博物館行脚を差し込むことにムリがあるかも知れません。
ふざけた企画で直接奈良の一寺に寄ったあとは、京都の酒造見学、烏丸通のホテルに投宿し翌日朝一に大谷祖廟といういつもとは順序の違った段取りになっています。
これまでの感覚として皆さんは博物館見学等はお好きでないよう。興味がない方をお連れする事も私としては気が引けます。
昨年の南山城の「わらい仏に逢いに行く」ツアーで岩船寺から浄瑠璃寺まで皆さんを歩かせたことから「愚痴の少々」が聞こえてきましたので今回は私の趣向はほどほどに・・・と思っていましたが京都国立の企画がその期間にあることを知って、私は引率者としてバスは降りられませんが「あとは勝手にホテルまで・・・」の毎度の投げやり自由行動での博物館企画を差し込もうかとひらめいたところ。
まぁそれまでしてその「法然~展」に行きたいという方は不在かも知れませんが。一応打診することにします。
今年は桜咲くころに奈良の山間部を歩いたわけですがその中心部、奈良国立博物館では「空海 KŪKAI-密教のルーツとマンダラ世界」展(やはり日曜日まで)が開かれていて、非常に悩んだわけですが、奈良市内の混雑の状況が蘇ってパスした次第。
心中、奈良か東京どちらかの選択肢ならその今回の企画・・・空海と法然では「法然に決まっている」という気持ちが無きにしもあらず。
そういう時は、宗旨的判定が頭の中で幅を利かせますから。
ぶっちゃけ記せば真言密教か称名念仏ですからね、当然といえば当然の事。
しかし、私は日々五輪塔だの宝篋印塔だ大日如来だのと阿弥陀さんの物語とは真逆に近い流儀による遺美術について、のらりくらり綴っているわけで、その空海に関わる美的遺品に関しても大いに興味をそそられるのでした。
扨、その奈良国立博物館の「空海 KŪKAI-密教のルーツとマンダラ世界」のタイトルの「曼荼羅」を何故にしてカタカナにしたのか・・・などとあまり大したことではないようなギモンが湧きました。
「マンダラ」の感覚は一般的には「世界」とかサークル状に配したフラクタル幾何学的絵図を思いますね。
そして本来の意味はそもそもサンスクリットからであて字(円とか集会・・・今言う「サークル」に似たイメージ)そして漢字で記すことにこだわるのはあまり意味がないのですが・・・
まぁどちらでもいいか・・・
また伝来諸仏を中心に据えたストーリーの絵図を通称「〇〇曼荼羅」と言ったりします。
ところが真言密教(中心は大日如来)ではその曼荼羅は宗旨ならではの灌頂という儀式に切っても切れないアイテムで「悟り」に通じるものでした。
それは胎蔵界曼荼羅③と金剛界曼荼羅④とのセットですね。
片方だけというのは有りえないのでしょう。大抵そのセットになります。
室生寺では灌頂堂内陣の東西板壁に胎蔵-金剛と向って掛けられています。
詳細はその世界未熟者の私が記すより各お調べいただければと思いますが、私はただ見た目だけのことを。
中心に大日如来がいて放射状に各如来と菩薩諸仏が配されるという構図が胎蔵界曼荼羅。
そして金剛界曼荼羅もやはり大日如来が主役となりますが、構図は3×3の「9つの四角」で両曼荼羅の差別は一目瞭然です。
そして、私が目前で拝観したかった東京国立の出し物といえば門外不出だった當麻寺曼荼羅「阿弥陀浄土変相図」でした。
いわゆるホンモノです。
當麻寺でかつて私が見たものはコピーかつ格子の中でしたからね。
①がホンモノ。4m×4mの大作の刺繍ですが大きなガラス越しからの図でNHKで放映された画のキャプチャーです。
奈良時代に作られたものといいます。表に出てきたからには記憶に留めておきたいものです。
②は後世複製されたもの。
私はやはり阿弥陀さんが中心世界、サークルに生かされていますのでこちらの企画には参加しなくてはなりません。
ただし真宗の曼荼羅を敢えて言えば立ち姿の阿弥陀仏単体の絵図であってそちらから放射状に放たれる光の環をイメージするだけですが。
阿弥陀仏一佛で他の諸仏は割愛・・・シンプルでわかりやすい。
2024年
6月
07日
金
東大谷万灯会とご門徒さんビール工場飲み放題企画
東京からご門徒様がお参り。
コロナ中、アケ後それ以来のお久しぶりの対面でしたが、その間には「色々あった」とのこと。
何度かのうっかり転倒で痛い目を味わい、コロナに罹患したうえ続けざまにインフルエンザにも。すべて予後無事だとのことですが奥様は不調をきたして2カ月弱の入院。
ご当人のコロナ感染は奥様入院中のことだったそうでそのタイミングに関しては「良かった」と。奥様は相当の不調で免疫が落ちていたといいますので。今は回復とのことで一安心。
その方が仰っていたことは
①コロナとインフルとでは格段に後者の方の辛さ、特に喉の痛みがきつかった。
②コロナワクチンを接種したばかりで何故か鼻血が止まらないでいたが逆にコロナになった途端それが止まっていた。
③やはりコロナワクチンは「怪しい」としか思えず今後は打ちたくない。
とのことでした。
墓参のあとはお斎のお誘いを受けて鰻屋さんへ。
当初の予定にありませんでしたので、奥方にその旨「悪いねぇ~」という具合で連絡。
すると帰り際にお土産を「奥方さまにどうぞ」・・・。
図々しいお寺の夫婦ではあるものの「ごちそうさまでした」とお別れしました。
そのあと、京都のご本山と大谷祖廟をお参りされるとのことでした。良き天気が続いて本当に有難い。
大谷祖廟といえば数日前にそちらにて開催される現状ほぼメジャーとなったといえるイベントの「東大谷万灯会」の案内が届きました。お盆の風物詩として毎度NHKニュースで放映されるようになっているかと。
第63回ということですから案外と回を重ねていたのですね。
それにしてもこれまでずっとこういった案内は見た事がありませんでしたから、広く宣伝公開する方向性に舵をきったということでしょう。
奈良も京都も寺社拝観料の値上げラッシュと聞きます。
維持費人件費高騰がその理由といいますが、私ども宗旨の寺は観光を主にうたうものではありませんのでそもそも拝観料はナシ。
値上げのしようがありません。
しかしタダが物を言うのか、京都駅前の両本願寺には観光客が溢れていますね。よってあっちこっち歩き回る外国人観光客の対応やトイレの維持など経費は嵩むに決まっています。
当然に寺として「何かしなくちゃ・・・」の方向性は模索されるわけで。
私個人の感覚では、その時節「動けない ムリ」というのが本音。のんびり近隣ホテルに宿泊し、夕時、団扇片手に散策できるような身分になってから・・・の夢としましょう。
そして、ビール飲み放題は近隣拙寺ご門徒池田屋さんの企画になります。
他のご門徒様に報せて欲しいとのことでお寺の掲示板2カ所にその旨記しました。
池田屋の店主は拙寺寺楽市に毎度ご協力出店いただいていますが、牧之原ご当地ビールを製造販売するようになって今年で4周年。
コロナ前にかなりの設備投資を行っているご様子です。
あのコロナ期間のダメージは多少なりともあったろう思いますが、是非ともへこたれずに挽回していただきたいものです。
尚、お楽しみは店舗内にて。
2024年
6月
06日
木
北畠親房塔周辺墓域 多気北畠一統か 室生寺
良きお天気が続いて嬉しい限りです。
昨日は懸案だった拙寺境内に建つある墓石についてその継続か否かの方向性進捗がありました。
戦時中、南洋で戦死した方の墓碑ですが参詣・墓石管理者不在のまま数十年。
ただし、建碑者については判明していましたので、その旨今後の事をおうかがいさせていただきました。
拙寺御門徒さまではありませんので第一声「はじめまして」のイキナリ訪問の失礼だったわけですが、「そういうことならば・・・」とその方向性について検討いただけることになりました。
まずは「墓じまい」となるのでしょうが、どうしても、もやもや感が残ります。
若くして戦場で惨い亡くなり方をして、かつ無縁さんとなることなど当人も知らぬこと、まったく気の毒なことですが、そういう仏たちは世に無数にあります。
やるせないことですが、若き命を戦争に引きづり込んだ国の責任として亡くなったあと墓地の管理100年200年は面倒を見ようと気概を持っていただいても罰はあたらないでしょうよ。
彼の墓を抹消するということは戦争の歴史を消すということですからね。
昨日のニュースでやはり揉めていた「政治資金規正法の改正案」とやらが衆議院を通過する見通しであるとの報。
その内容については煙にまかれた感じが・・・
一番にインチキ臭いと思ったのが「政策活動費はすべての支出の領収書等10年後に公開」という件。
「10年後に公開」って・・・「?」マークしか出てきません。
素人の私だからなのでしょうか意味不明に陥ります。
一般に私どもの生活の中でそのインターバルは有り得ませんからね。商行為であれば「瞬時」に出されるものです。
私どもの立場としてご懇志またはご依頼について先方様より受取の証が必要であると申請されれば「披露状」という書面になりますが、その提出は遅れたとしてもせいぜい4~5日ですからね。
彼らの感覚はあまりにも我らのそれとケタ違いに飛んでいます。まぁ庶民の感覚としてはその件時効を期待する悪辣な発想があるのでは・・・などと考えてしまいます。
わるい事を散々やってバレたとしてもその証拠は10年後。
それでいて時効ともなればもはや訴えられる心配はナシ。
そもそも10年ひと昔、悪い事をして10年後にその者がギインさんの職など辞めているかも知れませんし生きている確証もナシ。生き恥をかく心配なし。しかし昨日記した呪詛の如く庶民大衆から恨みを買いますね。
まぁ改正とはいっても彼ら御一同のやりたい放題のママ、思うつぼなのでしょうね。
扨、室生寺本堂の南西の森の中、大き目五輪塔の影が見えます。
その左側には宝篋印塔とやはり五輪塔が立ちます。
右端にある大き目五輪塔は壇上区画にあって正面左右の角に小さな五輪塔。あまりそういったスタイルは御見受けしませんので、後世いつの頃かちょっとした演出、イタズラかも。
こちらが北畠親房の墓といわれている墓塔です。
正面石柱②の彼の名の上に小さく「伝」という文字が添えられていますが要は確証がないということ。
いずれにしろ多気国司の墓という説もありますので、北畠の一党の墓というのは違いないところかも。
先般記した織田信雄は北畠家の養嗣子となって北畠氏を称した時期がありましたね。
興味が沸くところは、大正五年にこの墓の発掘調査が行われたそうで骨壺の中に遺骨が出てきたということですね。
その主たる者は確定できなかったそうですが、この寺に直接埋葬されたということは余程の権威の持ち主だったということが推測できます。
また、五輪塔水輪部から木製五輪塔とその内部から水晶製の五輪塔が出てきたとのこと。
またお隣の宝篋印塔も相輪等欠損がありますが、良き形で、おそらく北畠家に関わる人の墓ではないでしょうか。
2024年
6月
05日
水
互いに死ね死ねと呪詛しけり 修圓と空海
そろそろ梅雨といった時節ですが、妙に好天が続きます。
ありがたいことです。ということで朝から境内雑用。
花ガラやゴミの処理のためにに地頭方処理場にも向かうことができました。
おかげさまでこの日の予定していた作業はスンナリと満了することができました。
お天気がイイのでご門徒様のお参りもあります。
息子さんとお住まいになっている年配の女性としばし立ち話。
以前、私が紹介した耐震ベッドの件、検討しているのだが~、と打診を受けた方です。
手伝いはできるが息子さんの手前、私がしゃしゃり出るのは・・・ということと設置場所が畳であることから「どうしようか・・・」と曖昧な返事をしていたわけですね。
昨日、私からその件窺うと「喉元過ぎれば~」ではないが、この齢になって家が潰れたとして死ぬのも仕方ないか・・・と考えが変わって来たと。
私は実はそれこそが真宗的(「おまかせするほかはなし」)ですと。しかしできるだけ生きながらえようと一所懸命に工夫して生きていくことも大事ですが・・・
どちらにしろまた気が変わったら声かけてください、と別れました。
扨、室生寺について観光の寺、多くの重文・国宝の整列から日本の仏教文化の深さと畏敬を感じるのですが、宗旨的にみれば真言宗ということで。
しかし室生寺弥勒堂の弥勒菩薩は奈良興福寺関りの遺物と記した通り、別の流れがあったことを示唆しています。
興福寺の「興福寺別当次第」なる資料等に弥勒堂は室生寺の堂塔建立に関わった修圓が興福寺別当の時、創説した伝法院を室生寺に移したことに由来するといいます。
そもそも室生寺は、奈良時代末、山部親王(桓武天皇)の病気平癒のために室生の地にて延寿法を修したところ回復したということで興福寺の法相宗の碩学、賢璟が朝廷の命でここに寺院を建てたことが始まりと。
何故にして興福寺法相から空海の真言系への変遷があったのか。本格的には江戸期桂昌院の意図、彼女のお墨付きがあってから現在のカタチに増幅されたのかとは思いますが、このお寺には古くから複雑な歴史が交錯していたようです。
興福寺の僧賢璟の弟子の修圓という僧がその後室生寺に入ったといいます。
それなのになぜにして・・・という思いが浮かぶのは当然の事。
何かのドサクサがあったに違いありません。
そこの経緯については不明ですが面白い話がありますので参考までに記します。
それが今昔物語巻14第40話 弘法大師挑修圓 から。
彼らの呪詛合戦と相互のフェイク泥仕合の件。
概略記せば
弘法大師と修圓が嵯峨天皇に仕えていた頃。
修圓が天皇の近くにいた時、生の栗があって天皇がそれを所望。
茹でて来るよう命じます。
修圓が「人が火を以て煮ないでも私の法力で出来あがりますよ」と。
するとその法力とやらが効いてでうまく煮えて食べられるようになっていたといいます。天皇もその法力の恩恵を喜んで食べていたようですが、それを聞いた弘法大師が、自分がその法力を隠れて見ているので今一度それをやらせてみてくれ・・・と。ということで天皇は就圓にその法力での栗の調理をやらせてみるとまったくそれが通じずに栗は煮立たない。
頃合いを見て、弘法大師が登場すると、就圓いわく、ああこの者が煮立たないよう陰で加持祈祷し足を引っ張っていたのねと。
以後二人は罵り合うようようになって互いに死ね死ねと呪詛しけり」の如く。
高僧たちの怨恨嫉妬の泥仕合は続き、弘法大師は「空海は死んだ」のフェイクニュースを弟子たちに流すよう命じます。
それを信じた修圓は「死ね」の呪詛をやめるわけですが、その呪詛攻撃のパワーがなくなったことを機に空海は一気に呪詛を集中させて、仕舞には修圓が亡くなってしまったというもの。
高僧たちの煩悩熾盛の様が記されている面白さと、呪詛合戦の子供じみた泥仕合、そしてその呪詛というヤツ、真に受ける人は多くいたのでした。
話変わって呪詛の極意とはその相手に「呪詛されていること」を何となく気づかせることといいます。
悪辣で醜い政治屋のみなさん、国民に呪詛されないようにね。
当然に裏金ギインさんなどは、呪詛の対象でしょうからそれぞれお体の具合には気を付けてくださいまし・・・。
今は呪詛は罪になりませんからね。
どなたでもお気軽にお呪いくだされ。
画像は室生寺の片隅にある修圓の廟。
私は当然の如くそちらの扉をオープンしてご挨拶。
背後から奥方のやれやれの目つきが刺さっていましたが私としては当たり前の事です。
開けてはいけない箇所には施錠がありますからね。
それが無いということは「ご自由にお参りください」ということ。拙寺の本堂と同じようなものです。
しかし室生寺創建にも関わる彼の墓としてはあまりにも貧弱な五輪塔。
廟の中で風雨から護られていることは確かですが、損傷も無く
キレイで新しめ。平安前期の方の墓とは思えません。
興福寺法相から真言の寺となった理由はその今昔物語に記された内容からとは断定できませんが、何かあったことは違いないところ。
空海の敵ではあっても室生寺の創建者。
しかし今は真言の寺。
まぁいろいろあった・・・そういうことなのでしょう。
2024年
6月
04日
火
久々頭から湯気が出た件 心の底から◎※×△~
天気が良くて気分も爽快。関東とは違って雨はナシ。
よって「宿題」だった切株のすべてを午前中いっぱいかけて気合を入れて引き抜きを完了しました。
こちらの土壌はどちらを掘っても砂地です。
大きな地震が来たら液状化するに違いないと掘っていて(かなり深堀しました・・・)思ったのでした。
当然のことながらこの地区は相良川(萩間川)の砂州だったというイメージはありましたが先般行った地盤調査の際、採取したサンプル土壌の中から貝殻が出てきましたので海岸線が後退したかつての砂浜ということ大いに考えられます。「波津」という地名の通り。
どちらにしろ新築建造物の基礎については「ベタ基礎」だろうと思っていれば建築士は「布基礎」で・・・と。
やはり経費の節減の問題からその発想が出たかと思いますが当方納得ができていませんのでその件は再度問い合わせをするつもりです。
まぁそもそも建築確認(接道義務)が下りないとのことを言われていますが・・・
寺として昔からある建造物の新造。以前あったものを解体し再建するのですが、別の御門徒さんに聞けば、これまでは「接道義務」には地元ならではのテクニックがあったとのこと。
ところが今回の建築士は世話人さんの紹介の方で、相良のことにあまり精通していないような。
また来年の1月からはじまる相良のイベント用に合わせて外トイレを造作するという意図もありますので、お役所仕事には本当にくさくささせられます。
これで総務省から届いたアンケートの件も、無視してやろうと腹積もり。
突然郵送されてきた書面ですが一応回答を試みましたが、サッパリわからない・・・字が細かすぎて読みにくいということもあってこれではどうでもイイという気持ちにもなるというものです。
時間をかけることだけでもバカバカしい。
接道に関しては県の言い分でしょうが昨日夕刻、市の方のやり方にもそれ以上に不満に残る事案がありました。
昨日は午後から静波墓園に出向いて先般の伐採作業の片付け整理し劣化した物置を撤去しました。
軽トラの荷台にはさすがに私一人では積込み不可だったため奥方に付き合ってもらいました。
ヘロヘロになって帰宅、ひとっ風呂浴びていると史跡研究会の会長より電話が、折り返してみると「唖然呆然の報せ」がありました。
会長は役人の事なかれ主義で、何かをやってみようという工夫もパワーもまったく感じられないとお怒りでしたが、私も数日前に御門徒さんのある方に史料館2階のショップの運営について声を掛け法的・技術的提案と企画書の作成をお願いしていたのでした。
それをイキナリ市の担当者から「もう決めちゃいましたから・・・」と会長に連絡があったとのことでした。
どういう経緯でそうなったかなど私にはサッパリわからないところですが、どうやら史料館2階のお土産スペースのショップを仕切るに静鉄関係の大手に「決めてしまった」ということですね。
当初からそちらは地元の商店が仕切ってみんなで頭を廻してアイデアを募ろうという「手作り」ショップという流れがありましたからその急転直下の判断に言葉がありませんでした。
要は役人根性というやつ。
自分に責任が回らないよう信頼と実績のある有名大手に「全部投げる」というオチ。
ネガティブキャンペーンでも展開してやろうか・・・ついつい敵対意識が芽生えました。
その担当者とやらは長谷川氏が超繁忙の為、限界点に達していたことから抜擢されたようですが。
「気が小さいくせに、そうカッカすんな」と奥方から肩を叩かれましたが久々頭から湯気が出そうな思いをしました。
寺には観光客を招いてやるので「ただトイレの用意と堂内で小話でもしてやれ・・・」ということなら大きな間違い。
少なくとも私はそう受け取りました。
こっちはヤル気があっても役所仕事というヤツがどうもギモンですね。
父親が日ごろ呟いていた言葉が思い出されます。
「うちは観光寺じゃあない」。
事なかれ主義から脱却せよ。
冒険してみやがれ・・・若いんだから・・・ばかもん!!!
一応はそれを記してスッキリしました。
いや、あと一言「覚えてろよぉ~!」
次の世話人会でボヤくこと間違いなし。
②画像は大中特小を引き抜いてあとは小を残すのみの図。
③が今回の掘り起こした根っこたち。
業者にまかせたら処理費も嵩むでしょうね。
④は静波から運んできた物置。
2024年
6月
03日
月
織田信雄 巡り巡って宇陀へ 信雄五輪塔 室生寺
爽やかな梅雨入り前の侯。本堂内の空気のことですが昨日は朝早めの時間帯は陽光が注いでいましたが昼前頃には曇が広がり出して2時前にはぽつぽつ。
午前は法事がありましたがその雨降りの怪しくなった頃、吉田の墓園での納骨の勤行がありましたので「タノム~」の気持ちで少々早め現地に向かいました。
すると雨は消えてうまいことお勤めは終了。
ありがたいことです。
その後も予報に反して大きな降りはありませんでした。
息子は久々横浜での法務に向かっていました。
横浜辺りの縁が切れないで続けさせていただいていることは有難いことですが、東名高速往復料金+燃料費+走行のリスクについて勘案すると「ちょっとね・・・」というところ。
そして息子の浮かれた話。
先般神奈川県内の法務でご縁のあった御家の施主さんから「是非とも次も今井先生を」なるご指名があった・・・と。
奥方と「じょうだんじゃぁない」と吹き出しましたが、煽てられて天狗の図。何せ27歳の小僧ですからね。
どうしてそうなってこうなったのか親としても理解不能ですが、私自身はその「先生」付けの尊称が大嫌い。
そんな呼ばれ方をされた時はいちいち「それヤメテ!!」などと注文を付けるところです。半分コケにされているようでもあり・・・
「先生」とは当流で言う「善知識」のことですから、その言葉を歓んでいれば救いようのないバカということかも知れません。
ただのバカ(愚-悪人)というのが一番になごみますからね。それだけはゴメンです。
私も息子もおエライさん、センセーでは無いのです。皆さんと同じですからね。
またその称を歓ぶ類とは違うからです。
私どもの歓ぶ称といえばただ一つ「南無阿弥陀仏」の称名です。
学校の先生には勿論、本当の敬う気持ちがありますのでその「先生」を付けて呼びますがね。
扨、室生寺の桂昌院五輪塔のあるエリアとは違う段になりますがやはり五輪塔が並ぶ場所があります。
そちらの真ん中の大きい五輪塔が織田信雄の墓。
彼の墓も御多分に漏れず他所にも存在しますが、こちらには分骨とはいえ遺骨があるようです②③。
やはり「どうしてそうなってこうなった」のか、彼の不運かタイミングの悪さか時の流れか、はたまた世にいう無能の武将だったのかわかりませんが、流転して宇陀という地に収まったのでした。やはり室生寺にとって「有徳なる人」だったのでしょう。
詳細はWikipediaでも開いていただければと。
まぁ豊臣親子の滅亡のことを考えればつまるところ「うまいことやった」の目出度しの感。
生きて残って最期の寿命を迎えることほど仕合せはありませんね。
2024年
6月
02日
日
ぼちぼち継続 伐根作業
午前の法要のあとは、史跡研究会の会長さんが大いに動いて実現間近となった相良の新しい名物「田沼意次」なる清酒(720㎖)の販売方法について御門徒さんの酒店の店主に御足労いただいて会長さんと本堂にてミーティング。
そのお酒は現状3店舗の取り扱い指定が決まっていますがそのうちの2店が拙寺御門徒さんです。
各店舗での販売については問題がありませんが、テーマは史料館2階の大河ドラマ関係の展示場に併設することが決まった相良名産品の集まる場のお酒含めて運営の件。
アルコール類は税務所の許可申請が必要ですが、仮設常設はともかく責任者の常駐が必要か任意の店員さんで販売ができるのか・・・法的な部分と実際にどう人が動き動かせるのか・・・人件費は・・・で課題は多そう。
もし可能ならば拙寺婦人部で手を挙げちゃおうかな・・・・としても、どこからかちゃちゃが入るかもとの思いも。
一同で「お店屋さん」を廻すことなど拙寺みなさんの得意技ですからね。
扨、私は神奈川県の小田原生まれ。母の実家とその菩提寺があります。中二までそこに暮らし、中三から父の実家相良へ。
大学卒業後は各所転居の連続はありましたが結局小田原に舞い戻ってそちらでの生活が長くありました。
私はその母方実家とはそこに入った嫁と息子が統一教会に入信したあと、無茶苦茶ヤラれたことから縁切りして音信不通になりましたが、菩提寺墓参には時折向かっています。
またその墓参りの折にもう一か寺「おばさん」のお寺の墓地に顔をだすことがお決まりになっています。
先日、小田原の古くからの知り合いから連絡がありました。
母も私もずっと世話になっていたその「おばさん」の縁者からでそのお宅の稼業は町の鮮魚店です。
するとこの1~2年のうちに店を閉めます・・・とのことでした。
以前相良の閉店する寿司屋の板前さんがボヤいていた「市場に魚がいない」ことが原因なのかとそれを伺えば「客数が激減した」とのこと。
ひどく驚かされましたが、これも時代の流れなのでしょうね。
大型S.C.の賑わいの半面街区の商店街、小売店舗のシャッター街化、弱小資本が淘汰される時代のことです。
昔ながらの顧客も少しずつ世を去り、魚を選んで包丁を入れていただく間、世間話をしながら待つという時間の使い方が無くなっていったということでしょうか。
この流れは国の施策なのでしょうね。
大手資本を優遇し他の淘汰されるべき小店舗としては「サラリーマンでもヤレ」ということなのでしょう。農業もしかり。
相良の薬局、酒店の御門徒さんから耳にしたことがありますが
スーパーマーケットで酒や薬を売れるように規制を解かれるにつれてこれまでの営業継続の不安を吐露されていますからね。就業の継続ができないということは将来、未来の自己の存在に疑問符が・・・
画像は午後のミーティングのあと、切株堀りの続きの図。
「大」の切株に難儀していましたが、本体は何とか引き抜けました。ただし派生する根が多方にわたって、それらがビクともしません。
またのんびりつづけることにします。+αと小と特小。
2024年
6月
01日
土
禁足如意山納経塔 室生寺桂昌院五輪塔の隣3基
台風一号は早々に熱帯低気圧に勢力を落とし、遠く南の海上を通り過ぎていきました。
とはいえ殆ど雨の時間が多い一日でした。
午後は会館工事の図面を新たに持参いただいて問題点の抽出。
どうやら接道義務の問題で建築確認がスンナリ通らなそう。
対応の方法はあるようですが、今のところ提案されたそれ(壁あるいは土塁のセットバック)は私としてもまったく受け入れられない件でありお手上げ状態。
ただ「何とかうまいことやってください」と言うだけでした。
扨、室生寺の七重塔は目の前10mのところで立入禁止、残念の思いをしたことを記しましたが、それ以上に残念なのは如意山の禁足の件です。
もしかして・・・こっそりとでも登れるかと思いましたが。
何とかうまいこといけば、奥方に「車で待ってて~」と別れて単独で登ることも考えましたがムリでしたね。
そもそもどちらから上っていいかわからないことと(だいたいの場所はわかりますが)、真顔でその辿る道をお寺に伺ったとしても一笑に付されるだけですからね。何故なら禁足の山ということを知っていたからです。
私の目的はその山のトップに立つ二重塔いわゆる納経塔(重要文化財指定)でした。
まぁムリな物はムリ、こちらも笑って帰路に尽きましたが、心残りであったことは確か。
如意山は空海が如意宝珠を埋めたと伝える山でその二重塔がその在処と伝わっています。
以下奈良県史より。
平安時代後期 高さ132㎝ 安山岩
「基礎は壇上積式で二区に分け、軸部は初重も二重目も長めに作り、屋根は真反りで降棟を刻み出し、軒裏は屋根勾配に応じて傾斜し軸部をはめ込む作り出しがある。
こういう各部の工作は鎌倉時代以後のものとは違い外観ものびやかである。各重の軸部は円筒形にくり抜いて、中に木製の経筒が入っていた。
昭和二十一年に塔下を調査された結果、径約3㎝の水晶の玉が発見された。これが如意宝珠ではないかといわれた。
その他に小観音像、古銭などもあった」
最後の画像(奈良県史)がそれです。
他は昨日の桂昌院五輪塔のお隣三基。
2024年
5月
31日
金
室生寺にもあった桂昌院五輪塔
境内作業は思いのほか時間を要しました。
午前は雑多な仕事に午後からは新会館用地の墓地側にある切株をボチボチ取ろうと穴掘り開始。
切株はイヌマキの生垣のもので大木ではありませんが切株の掘り起こしはそうカンタンな仕事ではありません。
どうせユンボが入るのだから業者に任せれば・・・という指摘もありましたが、これは私の宿題とこの4本の切株の撤去のタイミングを計っていたのでした。工数が減れば請求書の項目がなくなって減額にも繋がるでしょう。
大・中・小・特小の切株のうち、まず中サイズからやっつけましたが大は根の張り具合が複雑で難儀しました。
仕事先の、あるいは他人様のチェーンソーであれば根切りはその登場で何とかなるなどの発想が起こるところですが、Myチェーンソーの刃は先般新品に交換したばかり。
よって手切りで対応しましたが、今のところ本体も根の先端もビクともしていません。
上空の様子が怪しくなったので夕刻前に撤収しました。
来週またぼちぼちとやっていこうかと。
チェーンソーは土・砂のついた木を伐れば一発で伐れ味が落ちること必定。石を切るのと同じ・・・です。
そして切れ味の落ちた刃を使用していればチェーンソー本体の劣化を早めますからね。
まぁこれが私が他人様にチェーンソーを貸さない理由になります。チェーンソー仕事なら「私がヤル」に行きつくのでした。
根切り作業を日常的にされている方などは根切り専門のチェーンソーを一台用意しているくらいです。
根切りは刃に焼きが入りやすく本体に負荷がかかりすぎるのとキャブレターへの砂の吸い込みもあってエンジン不調に陥りますので大抵は電動のチェーンソーを用意していることが多いですね。
扨、以前拙ブログにて善峯寺のいろいろを記しましたが、その中で「桂昌院とけいしょう殿」(またはこちら)とありました。
その桂昌院(玉さん)は徳川家光の側室、五代将軍綱吉の母で各寺院復興支援のために動いた人でした。
室生寺(昨日ブログ)にも彼女への報恩感謝のために建碑された石塔がありました。
国宝の本堂-灌頂堂-の近くの五輪塔になります。
こちらは顕彰碑としての五輪塔になり遺骨、遺髪の類の埋葬はなしか。
宝永二年六月弐拾弐日没。
2024年
5月
30日
木
室生寺奥之院 立ち入り禁止 七重塔
昨日は新会館建設予定地に依然としてあったコンクリート敷設とその下の旧浄化槽を撤去。これでまったくの更地となったわけでようやく工事が進んでいく気配です。
あとは新しい図面ができるのを待つのみです。
ちょっぴり頭が痛いこと。
地盤調査に関しては調査資料をそのまま移行してもらうことができましたが、以前何度も改作いただいていた図面がゼロとなったためその製作についての費用がどうなるのか・・・
また、地盤調査した業者とパイル打ち業者について、当初は同一業者とのことでしたが、新しい設計士はそれは止めた方がいいとのご指摘がありました。
意向としては当方の主張が通るわけですが、わからないこと多多あって、結局はプロの言う通りになりそう。
バカバカしいとも思える調整に頭を捻るのも・・・やはりアホらしい。
見積もりが出ず、遅延が続いて、一向に着手できないでいたままになっていた工事について、業を煮やした世話人さんの手筋で新しい設計事務所に依頼。このほど工事が動き出したのですが、これでは旧設計士のメンツは丸潰れでしょうね。
しかし3年も進捗がなかったことからこうなったワケですので、私どもにも主張するところは多分にあって、先方のすべてを承服するという寛容さは持ち合わせていません。
出来るだけトラブルは起こしたくないという気持ちで待ち続けましたが、3年経って何も動いていないというのではね。
とにかく来年初めまでにお参りの皆さん用の外トイレの完成が至上命題となっていましたので。はやくはやくの気持ちが。
扨、先日記した室生寺奥之院。最後の階段を登りきると左前方に御影堂(みえいどう)=大師堂-重要文化財-が目に入ります。
木造ですが屋根中央には石の路盤と宝珠が・・・
そして私の一番の残念はその建屋に隣接した「諸仏出現岩」と呼ばれる小山。
そのトップには石造七重塔が立っていますが、歩道状の道の底部には立入禁止の札が。
奥之院とはいえ観光客は比較的多い寺で案外とそちらまで上る人がいます。
年配者も多く、その崖の如くある山にお気軽に上がられるのは気が気ではないでしょうからね。
安全面からの規制線ということですが、私からすれば興ざめでした。
「閑散としていて管理者不在の様ならばお前は(札の意趣を無視して)登るだろ・・・」との奥方の指摘。私は無言でニヤけているだけ。
こちらは平安期とも推測される層塔で、この塔の下の穴から諸仏が湧き出てくるとの言い伝えが。
その「穴」とやらも見て見たいものでした。
2024年
5月
29日
水
QRコード注文 スマホが無いと話にならない世の中?
昨日午前は、御門徒さん宅のお内仏(他宗でいう仏壇)の閉扉式。
転居の為とのことでしたが、そのお内仏はここでお役御免だとのこと。
要は廃棄処分されるということですが新居にスペース的余裕がないことからその断腸たる結論に至ったようです。そのお内仏は昔ながらの大き目サイズ、購入した際は今でいう軽自動車一台分以上の金額にはなったであろう代物です。
そうせざるを得ないご家族の心情と、そのお内仏そのものに対しての気の毒と申し訳なさを思いました。
尚、新居にはごく小さなお内仏を設けるとのこと。
また朝食時に今年春、静岡の歯科医で処置してもらった奥歯の被せ物が脱落したため、昼前に急遽静岡へ。
予約はありませんが、「急患」を主張して午前の診療時間ギリに無理やり入れて頂きました。
静岡に向かうとデパート・食品売り場を歩き回って散財しますから抑制ぎみにしようとは思いますが、一旦あの繁華街に足を踏み入れればついつい節約意識を忘れさせ、余計な「おいしそうな物」を所望してしまいます。
奥方は特に「デパ地下命」の如く歩き回りますので、私は歩き疲れて「駐車場で待ってる!!」と言い残して雑踏を離れるのが常。
ハカ・テラ・シロ歩きの場合と真逆の展開になります。
扨、今私は盂蘭盆会法要の配布用に毎度「雑感」と称して何やら思いつきレベルのことをぐたぐたと記していますが、今年のテーマは「痴呆」です。
病の種はさまざまありますが、うまいことその病をすり抜けることができたとして長寿の果実をゲットしても「脳の老化」ともいえる「痴呆」からは逃れにくいものがあります。
よってできるだけその老化-痴呆の進行を遅らせるかがこれから私どもに突き付けられた課題ですが、私はそれには「脳を回転させ続けること」だと結論づけました。
小学校低学年の学習指導要綱の如く、「聞く・話す・読む・書く」の意識を持ちそれを持続するということです。
まぁだいたいその件、仲間と外に出て遊ぶことでクリアできるものですね。
孤独死という語がやたらと聞こえる時節ですが、友達を作って「何かやらかそう」の気概でしょう。
仕舞いには「まかせる」ほかは無いのですが・・・
画像は昨日の朝、雨が上がったタイミング。今年初のユリが咲きました。
そして②は昨日のランチに入った店と③は毎度おなじみ島田の格安外食の定番のファミレスのテーブル脇。
テーブルごとに設置されたQRコードから店のメニューと注文ページに入るシステムになります。
義母は友達と外食する際「絶対に対人での注文しかしない」と豪語しています。
よってこれは年配者、スマホ非所有者を排除する流れか・・・とは思いつつも、これからは高齢につき「ついていけない」ではなくてがむしゃらに頭の回転を効かせてついていかなくてはならないのかと。
といいながら私はいつも「面倒だからやって・・・」と逃げています。
機械に指令し・・・対人対応を避ける店の傾向はやはりコロナから。
そのシステムを売る人たちはコロナが絶好の商売の機会だったわけで。給仕ロボットも全盛です。コロナ様様でしょうね。
2024年
5月
28日
火
宮崎莉緒さん現る 投票の帰途 小堤山遊具損傷の件
昨日午前は、世話人、総代が新たに指名された建築士が寺に。
遅延している会館新築工事について説明、早急に新しい図面を起こしていただくことをお願いしました。
会館の解体工事以来丸3年、更地にしてから思わず時間が経ってしまいましたがこれでいよいよ最大懸案(新築工事)が始まる見通し。
今度は来年1月までに・・・という期限の約束をいただきました。
午後は土砂降りの中、夏の演出なのでしょう、浴衣姿のミス・ユニバース宮崎莉緒さん(共立女子大 牧之原市出身)が撮影その他クルーを引き連れて拙寺を訪れました。
さすがに雨天の撮影行脚は気の毒でしたね。
拙寺の前に平田寺、般若寺での撮影が(引率・タイムキーパーは牧之原市の史料館学芸員の長谷川氏)あって、思いのほか時間をとったとのことで拙寺での撮影は1カットのみ。
正面如来さんの前に私と宮崎さんが立ったカットになったのは長谷川氏が推奨した拙寺の丸尾月嶂の襖絵と般若寺で撮影した木襖が「かぶる」と先方ご担当のご指摘があって急遽、阿弥陀さんをバックにした構図が採用されました。
本堂下の相良城残材を推測できるほぞ穴のある木材についても浴衣姿の彼女に床下へ潜ってもらって「ハイ、ポーズというのはちょっと・・・」と。
長身の彼女と並んで私もその1ショットに登場することになりましたが、画の採用可否はともかくとして、その身長差はかなり目立ちそう。
扨、その前日の日曜日は青空が広がっていましたから、この日の酷い雨は恨めしいものがありましたね。
私は庫裏に居っぱなしでどうってことはないのですが、来訪諸氏の難儀についてそれを思います。
そしてまた特に長谷川氏の奮闘には一層のこと。
何故なら彼は日曜の選挙管理委員会の一員として投票所に詰めていたからですね。
他にも知った顔がそちらに並んでいましたが奥方と「あれじゃあ、休みなしでかわいそう・・・」などと言っていたばかりでした。
まぁ私もサラリーマン時代には休日出勤は当たり前のようにありましたからね。
画像は投票の帰りに寄った小堤山。
噂の新しく設置されたばかりの遊具に上がってみました。
少々高い場所になりますので景色を楽しもうと。適当にグルっと撮影。
すると明らかに「頭に来ているぞ!!」の警告掲示が目に入りました。
まぁ、スケボー小僧の仕業であることが窺えます。
彼らからすれば絶妙な滑走スロープになるでしょう。
2024年
5月
27日
月
室生寺奥の院 懸造りの位牌堂―金剛殿
午前の法要は東京から来られた施主ご家族。
来年には「墓終い」・・・の語が法要終了後のお墓参りのあと聞かれました。寂しいことですが、致し方なし。
牧之原市は「消滅可能性自治体」の名のりをあげていますが、この町の将来について覚悟が必要になったようです。
それとは別に最近耳にするようになったのは「義務教育学校」なる語です。
何のことはない世にいう「小中一貫校」のことですね。
その手の学校はかつて私どもが居た沖縄の島しょ部にある学校で見てきましたが、子供たちがいない中、できるだけ集約して効率化をあげようというものです。校舎の耐震の問題がありますからね。
各単位で新築・改築を行うよりも大きめの校舎を新規に建てた方がベスト。子供たちのことよりもすべて管理側の都合でしょうね。教師の成り手も不在のようで。
多くの子供たち・友達に囲まれて育った方がより良い成長が見込まれると承認後付け講釈がされていますが、それはどうだかわかりはしませんね。
だいたい子供たちは自宅の部屋に籠って端末をいじっているだけのようですから。
榛原地区に1校で4学級制、相良地区は1校3学級制になるようですが、問題はこれまで通学していた学校が閉鎖されたとき・・・ですね。
小中学校というものはそもそも自宅直近で5分からせいぜい15分というのが一般的な通学時間でしょう。
それが30分以上という生徒がまたぞろ発生しそう。
親たちの心配の増幅・・・学校教育というものは行政サービスの一つであってよりコンビニエンスでなくてはね。
世も末か・・・。
扨、室生寺奥の院を目指して上り詰めると懸造りの堂々の姿が目に入ってきます。
しかし不安定な崖の淵によくもまぁとは思いますが、だからこそそこに堂を建てるのでしょう。懸造りのプロがうずうずしながら受注したことでしょう。
この建物は位牌堂で別名金剛殿。
2024年
5月
26日
日
室生寺奥の院へ 杉の生命力に空気 そして墓塔たち
「このほど 運動会に行ってきた!」という拙寺世話人様からその件窺いました。
父兄としてではなく来賓としてですがそれまた大変なお役です。それを労うと「午前だけだよ・・・」と。
「何しろ運動会は変わっている・・・」ようです。その開催時節も?でしたが。
私の運動会のイメージとしては小学校時代なら母や祖母などが待つ父兄席にてお昼ご飯を食べることが思い浮かびますが、今はそのお昼ご飯に親たちが来ることができない子供たちへの配慮か「昼にて解散終了」となっているよう。
共働きの家庭では会社を休んでまで子供の運動会に参加しようなどと思う奇特は無くなったということでしょう。
内容も個人の優劣を決めるものではなく、団体の競技、演技が主だといいます。
それではハッスルする子供たちの様を見ることができませんので面白くなさそう。そういう時代であるとはいえ、子供たちもそれでいいのでしょうかね。
運動競技の優劣をすべて他者の排除、弱い者いじめ的弊害として結びつけてしまうのは少々やりすぎの感。
ハードな競技を無くしてしまえば子供たちの怪我防止にもなりますから、管理者(学校・先生方)としてはその方がラクなのかも知れませんが。
私個人の運動会の思いといえば、前日に眠れなくなるほどハイテンションになったものです。
短距離徒競走もそうですが、高校時代は100、400、リレー、1500などありったけの競争に出させてもらって、悦に入ったものです。
大学時代も、社会人になってからも地区の運動会には顔を出すなど秋のお楽しみの一つでしたがそれが無くなっているというのは「つまらねぇ~」の一言でしょうね。
まぁ、当時から運動会、スポーツなど大嫌いという子供達がいましたから、そういう人たちからすれば「ああよかった~」なのでしょうが。
何がいいのかわからない・・・
扨、昨日記した室生寺奥の院の階段を見て、よくもまぁ奥方が淡々と登っていたものだと感心させられましたが(そのあとの長谷寺の上りには文句が出ていました・・・)やはりそちらまで行ってこその室生寺です。
やはり杉の大木の威風とその空気の良さ、行ってみなくてはわからない。途中ここかしこに見える五輪塔ほか石塔に注目しつつ。
①画像奥に見える五輪塔と②③は同じ。
大木といえば杉ですね。
松は短命、杉の偉大さを目の当たりにします。
2024年
5月
25日
土
室生寺奥の院への階段 隣家依頼の樹木は伐採
昨日は郵便料金の値上げ(10月から)についてボヤかせていただいたのですが、その世間に蔓延している「値上げー物価上昇」の数々、昨日の報道によれば多くは企業収益、政府が大風呂敷を広げた賃金の上昇には「ほとんど回っていない」と。
企業はこの機会に便乗値上げして、ガッツリ稼いだということですね。善人面さらして、まったくもって結構にあくどいものです。経団連の会長が自分の会社(住友化学)の赤字垂れ流し状態を「さておいて・・・」全国給料あげろ・・・よって物価あげあげ致し方なし・・・の躰はウソ八百もいいところか。
昨日は、お隣の奥さんに依頼されていた木を1本伐採。
交換したばかりのチェーンソーを持ち出して殆どぶった切り。
「棒切れにしてイイ」とのお墨付きがありましたので・・・
ちまちま剪定などやっていられませんからね。
「棒切れ」は有難い。快く承ったのでした。
しかしまた新品チェーンソー替え刃は切っていて清々しいことこの上なし。
4~5年間、研ぎと清掃でゴマ化していましたが替刃は経年で徐々に焼きが入ってしまいますので切れ味は劣化します。
交換して良かった・・・と呟くと「ケチケチしないで早く交換しとけ!!」と奥方から。
ストレスなくスパスパ仕事が進みますから、その件もっともなことです。ちなみに交換用ソーチェーンは3000円程度。
伐採材の地頭方処理場への搬入費は250円でした。
伐採樹木を細かく切って指定ゴミ袋に入れれば処理費はタダ(袋代金に含まれます)ですがあれだけの物を袋詰めするのは面倒なこと。
以前は母が花ガラ含め、袋詰めしたり焼却炉で焼いていましたが(父はその仕事をしません)私の代で焼却炉は解体処分、焼却の煙でクレームが来たこともあり、軽トラ搬出一本に変えています。
扨、室生寺、五重塔を見送ったら奥の院へ進みますが、あの目前にある上り階段を見て断念する方はいらっしゃるでしょうね。
そちらに上がってこそのテラ行脚、行かないでどうする・・・ですので私どもは階段をぼちぼちと。
すると階段にはところどころ何か彫られている箇所が。
墓石には見えませんが・・・
長い間多くの人々の足元を支えてきたのでしょうね。
2024年
5月
24日
金
境内東側墓地コンクリ壁 部分撤去工事
値上げラッシュのご時節、10月に郵便料金が値上げされるとのこと。なんだそりゃぁ~・・・です。
普通郵便が84円から110円、はがきも63円から85円に。
情報伝達手段として郵便は極力やめて、メール中心にシフトしていくべきですね。
しかし、困りました。当面は相良の町中への世話人様への伝達は車と足でダイレクト投函に。
扨、半世紀以上前、祖父の時代に増設された境内東墓地の北側と東側半分のコンクリ壁を撤去しました。
クラックだらけで、何時倒壊しても不思議が無いくらいに劣化しており、いつものコンクリ屋さんに依頼。
私と奥方二人でもできそうな工事ですが、撤去後のコンクリガラの処理に、以前とは違って個人の受け入れにうるさくなった(マニュフェスト伝票等必需)ことと、その後の型枠工も手掛けていただくこともあって丸投げさせていただきました。
ついでに墓地の排水対策として浸透桝の設置も依頼しました。
それも以前からの懸案事項で「いつかオレがやるから」と延び延びになっていましたが、ここで一所にお願いしてしまいました。
見積額は撤去工事だけで昨日浮いた分の1.5倍。
浸透桝追加工事がありますので+αです。
またそれには型枠工の分は入っていません。
そしてお隣の家主の奥さんに撤去のために業者さんの車を入れる許諾をいただきましたが、その際、そちらの敷地の木を一本枝払いすること承りました。30分もあればやっつけられる仕事です。
2024年
5月
23日
木
カイズカの剪定(伐採)静波墓園 私のとりあえず
昨日拙寺に来られた方といえば、転居前の旧宅での御内仏の閉扉式の際、コロナワクチンを接種して脳溢血になることを恐れて、それは周囲に若くして脳溢血で倒れた人たちが多かったからですが、「接種しない宣言」している人がいるといった話をしていました。
お会いした際、あの時はそんな話になってしばらく、「私が脳出血になっちゃった・・・」と仰っていたのでした。
世の中には未だそのワクチンの後遺症と闘っている人たちがいて、国はワクチン接種は大奨励。
何がホントか「わからない」のですがただ私の場合、コロナもインフルも予防接種などヤル気にはなれません。
また、ウソかホントか酒に弱い人がそうでない人に比べて5倍もコロナに罹らない・・・なる論文がありました。
佐賀大学の研究だそうで飲酒で顔が赤くなる人は「コロナにかかりにくい」というもの。インフルもその傾向があるようです。
私も奥方もまさにそれ。
だとしたら下戸にとって喜ぶべきことですね。
扨、4月から始めた静波墓園の外周のボサボサカイズカのやっつけ作業はここでひとまず終了。
その件、体裁などはお構いなしです。剪定というかぶった切り。
チェーンソーをブン廻してバサバサと切りました。
ポイントは成長の早いその樹木をここで一気に・・・というところですが、この課題を息子にブン投げるのは酷ですから小さくするというのが主旨。
基本手に負えなくなったら根元から・・・が合言葉。
こんな厄介な植栽、私が植えたものではありませんし。
そして何より防犯の問題。
住宅地の中に閉鎖的空間を作るのは良くないですからね。
防犯ということは勿論、墓地がゴミ捨て場にもなりかねません。
昨日は奥方に積み込みを手伝ってもらい、地頭方処理場の処理費は710円でした。トータル6回で4880円。
工数は一人工4回二人工2回。
もっとも大抵は半日仕事でした。
業者さんに依頼したとしたら一人工×4日として4×日当2.5万円。
処理費用は業者価格×2で1万円弱、搬送費含めてそれにどのくらい吹っ掛けられるかで差が出ましょうが最低でも10万円以上の節約になりました。
奥方は浮いたお金でさわやかで「ステーキ+ハンバーグ」と「かっぱ寿司」を喰わせろと。
息子はどう手配するかわかりませんが、シルバーさんに依頼したとしても皆様方大挙しておしゃべり会、何日かかるのか・・・そして請求がいくらになるのか・・・
もっとも痒いところに手が届かない仕事だろう・・・というのが最大のネックですが。
年配者をバカにするつもりはありませんがね。
少々の材は大晦日に暖をとるための薪用にする予定、まだ周囲にゴロゴロっと置いてありますので、いずれ回収に向かうことにします。
チェーンソーの清掃後、用意していた新品のソーチェーンに交換、次の仕事はスパスパっという具合に捗るでしょう。
石屋さんがユニックで訪れた際、墓地の枯れた槙(以前その上部を伐った際、下にいる奥方と息子のロープワークがヘマって墓石壊しました)を吊るしてもらいながら伐採しようと思います。
2024年
5月
22日
水
小型ながら優美 自然の中に映える室生寺五重塔
午前8時すぎに拙寺庫裏の呼び鈴が鳴りました。
その手の時間での来訪は「急な要件」というのがこれまでの経験則でしたが、それは違いました。
二年ほど前に相良から東北に転居された方の来訪で、午前4時に到着して旧家の片付けをして時間を見て来られたとのこと。
車の運転は息子さんでした。
その方は私より3つほど若かったと記憶していますが、先般脳出血で倒れたとのことでした。
一見してまったく変化はなく、意気軒高の感。
その病は死を免れたとしても重篤な後遺症が残ることを承知していますので私も「?」の躰となってその方を再度見上げてしまいました。
「何も不便の様は感じ取れませんが・・・」と窺えば、奇跡的に何事も無く退院できたとのことでした。
思わず私は「よりよきご縁でしたね~」と高いトーンで感服の声をあげていました。そういうこともあるのですね。
人生は縁、機縁・・・チャンスとその見逃しの連続。そしてそのベースに宿業(親鸞さんの意は悪業)という「私」の積み重ねた因縁果の複合的組み合わせで今があるといいますが、その健康という果実をたまたま得た奇特を歓びました。
そして今は食生活と運動を心がけるように自身変化したそう。
「拾った命」への感謝を強く仰っていました。
※歎異抄13 宿業
「善き心のおこるも宿善のもよおすゆえなり
悪事の思われせらるるも悪業の計らうゆえなり
故聖人の仰せには『卯毛・羊毛のさきにいる塵ばかりも
つくる罪の宿業にあらずということなしと知るべし』
と候いき」
先日も「わからない」について記しましたが、まぁ人間世界、すべてのことが「わからない」ことだらけ。
「こうである」が如くの物知り顔の輩は・・・やはり虚仮不実・・・
そう思いますがね・・・
扨、室生寺といえば・・・というくらい人々がその歩を向けるのが五重塔ですね。
昨日の灌頂堂のすぐ脇の階段上にあってあたかも「早く上がってこい」と促されているよう。
平安初期800年頃の創建で屋外に建つ、日本で一番小さい五重塔になります。
先日は三宝杉の一本が倒れた件を記しましたが、1998年の台風7号での倒木によって破損しています。
木々、それも大木だらけに良き雰囲気を感じる室生寺ですが、それはそれで風が吹けば冷や冷やものとなるわけで。
相輪は風鐸付きの九輪、その上に八弁の受け花に乗った水瓶、さらにその上に風鐸付きの八角の天蓋、龍舎、そして宝珠をいただくといったカタチ。他にない特異な形式になるようです。
画像ではよく見えませんが。
それにしても800年からこれまでよくもまぁ立ち続けているか、まさに奇特な出会い。勿論国宝指定になります。
2024年
5月
21日
火
室生寺灌頂堂(本堂) 如意輪観音 法輪
昨夜のテレビ小僧は東大寺再建の重源さんとカラシニコフの憂鬱(1億丁出回ったといわれるベストセラー銃)について視聴。
昼間は日曜の法事時間中に放映された「日曜美術館」(法然と来迎図)の録画を再生。こちらは今週の日曜の大河のウラで再放送があります。
そろそろ東京国立に「行くぞ~」と気合を入れての視聴でしたが、どうやら私が興味ある逸品たちは既に公開が終わっていて、九州、京都への巡回の準備に入っているとのこと。
奥方に「じゃあ京都へ」と言うと「勝手に行きやがれ~」でした。これは私のいつも吐き散らかす「勝手にしやがれ~」の変型。
どこかの政治屋さんではありませんが「行かない(産まない)でどうする・・・」ですね。
そして昨日は来年のイベント用冊子作成のための取材の予定がありましたが、先週末あたりの天気の悪化予報から中止順延が決まっていました。
平田寺、般若寺そして拙寺ほか相良のいろいろを見て回るものでしたが。
ところが朝方は雨が残ったもののあっという間に雨はあがって度P感の陽射しが。
また雲がかかる時間もありましたが撮影にはまったく問題ありませんでした。勿体ない一日でした。
またゼロから予定を組み直さなければならなくなった史料館の長谷川氏に同情してしまいます。
扨、昨日の室生寺弥勒堂に続いて灌頂堂-かんじょうどう。
灌頂とは密教(真言系)の儀式の遂行のことで要はその中心的伽藍であるということ。一般的に言う本堂の事ですね。
勿論国宝指定、鎌倉期の建物といいます。
①悉地院なる扁額が見えますが、もとは鐘楼近くにあった伽藍の一つの名称でそちらにあった如意輪観音を移設したためにその院名が残っているとのこと。
この如意輪観音は日本三如意輪の一つで他の二つは大阪観心寺、神戸神呪寺(かんのうじ) ということになります。
本堂に鎮座しているということでたくさんの仏像たちがある中、この如意輪観音が室生寺の本尊ということになります。
平安期の仏像で重文指定になっていますがこの仏像が何故にして国宝指定になっていないのか不思議なこと。
如意輪観音のスタイルは半跏思惟、そして如意とは思うがままに、法輪とは煩悩を壊す・・・といった大雑把な意味がありますが、ちなみに拙寺先代である父の院号にこの法輪を命名したのは私。しかしその意は「煩悩を破する」にあらず。
開祖の御和讃「弥陀成仏のこの方は~」から引っ張って来たものでした。
「弥陀成仏のこのかたは
いまに十劫をへたまわり
法身の光輪きわもなく
世の盲瞑をてらすなり」
「法身の光輪」の法+輪。
阿弥陀さんのはたらきからでした。
当流は「煩悩そのまま、ありのまま」というのが本でありますから。
2024年
5月
20日
月
一番許せてないのは自分やで 室生寺弥勒菩薩
藤沢在住の妹の夫が手術入院したと。
今は無事退院しているようですが緑内障の治療を行っているなか、今度の診断にて眼圧が急上昇していることが判明。
「このままでは失明」と宣告されて、急ぎ施術したとのこと。
その病は遺伝とのことで先方家代々その病の出現により苦しめていたそうですがこの寺に居ると皆さんの多種多様の病のそれも親から引き継いだ「遺伝」について聞こえてきます。
仏教では宿業だとか因果とかの語をしばしば使いますが、それって科学的生物的因果なの?などと考えてしまいます。
ゲノム解析が進んでいる中、その悪さをする遺伝子を特定し改変する薬が出来ても不思議ではない時代です。
多くの皆さんの苦しみから解放してあげたいものです。
それにしてもその夫は私の同年代ではありますが、今彼は緑内障以外、心臓などの不安を抱えています。心臓疾患即、障がい者手帳を持つことになったといいます。
年相応という言葉があって「承らなくてはならない」ところ、あることはわかりますが、人によっては一気に各所にそれが出現しますので、許容というものの限界を超えてしまいます。
人として生まれたという「楽」の第一を享受したからにはその逆作用(老病死)も背負って立たなくてはなりませんね。それも皆同じです。
また夜間、御門徒さんから電話がありました。
基本、大谷祖廟への分骨の流れについての確認だったのですが、最近のお互いの体調についての話に及びました。
するとその方は先般不調をきたして、医師のもとに駆け込んだとのこと。
診断は初期の癌が見つかって1週間ほどの入院で「処理」したそう。小さいものだったそうでラッキーと。
御当人は「気が小さいのでスグに医者に行ったおかげ」と。
「よかった、よかった 私も気が小さいので我慢しませ~ん」と言うと、いろいろ私へのご心配とボヤキ多数のお見舞いの言葉をいただきました。
ありがたいことです。
弱気な一人間として、他者から優しい言葉など投げかけられるとこれほど「ほんわか」するものか・・・、言葉の力は案外「病に抗う免疫力」をアップさせるのでしょうね。
それも一つの「養生」 (病気にさせないための)~昨日 東洋医学を科学するNHK~なのでしょうね。
扨、メディア各局、各紙いろいろ唖然とさせられるような事件・事故を報じています。
そんな中、被害者がいて加害者がある場合など聞こえてくる言葉がまず「許せない」なる語です。
当流では以前から「既に許されている身」という考え方があって他者をあげつらうことなどはよくないことであって、そもそもお前さんに「許さない」なる大層な言葉が吐けるのか・・・という疑問が出てきます。それほどの権威も力量も立場もありませんし、それでは・・・どうするんだ・・・ということになりますね。
よって人を許す許さないは仏の仕事であると。
室生寺から駐車場への途上、面白い看板を見かけました。
客観的に他者の逸脱した行為に対して、了見し、許容、時に眼をつぶるがヨシなどとは思ってはいるものの、他者のその行為が自身や家族に及んだ時、人は大抵その語を吐き散らかします。
ごくつまらないことに対しても・・・
それが、みんな一番自分が偉いんだな~と思う時ですね。
看板の絵は室生寺の重文弥勒堂と堂内の同じく重文弥勒菩薩。
小ぶりながら奈良から平安初期の作だそう。
奈良興福寺関りの遺物です。
2024年
5月
19日
日
相良城太鼓櫓(矢倉)の位置 田沼七曜紋の瓦
「まるでカリフォルニアみたいな・・・」などとここのところの寒かったり暑かったり、半袖か長袖かなど着るものに配慮が必要であることをその天気に喩えて言うと、「何を調子こいたことを・・・」と奥方に呆れられましたが、要は「油断がならない」ということですね。
数日前、拙寺の庫裏の台所兼居間のエアコン(4年目)について初めて専門の業者によるクリーニング依頼をしました。
あれだけはプロに頼んだ方がイイとかねてから思っていましたし、奥方もその方向を去年から主張していました。
昨年は奥方が気合を入れて脚立の上に立ち悪戦苦闘していましたが、結局は「消化不良」のまま諦めていました。
要は気休め程度(市販のクリーナー)の清掃ではまったくキレイになっていないのでした。
よって試しに・・・ということでプロに任せることに。
すると時間は2時間弱と案外とかかったようですが、奥方はその清掃の一部始終に立ち会っていたらしく(私は外出)、そのプロの仕事に感服していました。
「素人にはムリ」そして「ドロドロまっ黒の排水」がみるみるうちに設置されたタンクに溜まっていったといいます。
あのまっ黒でおぞましい~おそらく黒カビ+ホコリ~の堆積した機械の中を通過する空気を吸うなど「あり得ない!!」とその成果を誇っていました。
作業の方にその施術についての頻度を聞いたそうですが「2年に1度」を推奨されたそう。奥方はあのまっ黒の液体を見たら1年に一度でもやりたくなったと。
まだ請求は届いていませんが2.5万円程度と聞いています。
あの機械にはこの夏フルに働いてもらいましょう。
これで気楽にエアコンのスイッチをオンにできるというものです。
扨、昨日は午前の法要後に史料館の史跡調査会の会合へ。
相良小学校グラウンドの隣が史料館(相良城本丸址)になりますが、ご存知小学校グラウンドのお隣といった場所。
そして小学校正門入口の土塁が二の丸土塁。
会合の時間の15分ほど前にブラついて拙寺の太鼓のあった櫓の位置を実地で眺めてみることにしました。
入口③を入って左側には小島蕉園先生の名が記された標柱が⑥。
先日記した拙寺本堂に吊るされた刻(とき)太鼓のあった太鼓櫓の位置について現地の様子④。
その日は少年野球(男女混成)の試合がありましたがだいたい左中間あたり松が並ぶ右手、いやセンター辺りか・・・に太鼓櫓があったかと。
小学校グラウンドの正門を入って左右の道は堀が巡った位置になります。
⑤に暗渠がありますが、これが堀の址でしょうね。
史料館ではこのほど展開する相良田沼関りのイベント用に七曜紋のデザインの検討をしていましたが、そのカタチについては「承知しているものの現物を見てみたい」という若手お二人の意見がありましたので、急遽自宅に戻って2つの瓦を持参した次第➆⑧。
長谷川氏にこの瓦の出所について投げかけると、推論だが、相良城の遺物だと七曜それぞれの〇の大きさが少々小さく、後期田沼は大き目とのこと。
画像は如何にも大き目。
後期田沼の可能性もありますが、まぁ田沼七曜紋であることに違いなし。
2024年
5月
18日
土
悲しみ苦しみ悩み痛み だけでなし 楽しみの味も
昨日は、「そろそろ父がヤバい」 (昨日ブログ)に続いて今度は「自分自身が~」という方が境内に。
亡き母の墓参りとのことで花を抱えていました。
2年前に「5年生存率80%」なる病を宣告され、「何とかこれで2年経った」とのことでした。
日々自身の「その時」のことを考えながら時間を過ごして来たそうですが他家に嫁いだために実家の墓に入りたいとは口に出せないようで、かつ嫁ぎ先の墓には入らないとのこと。
よって拙寺の一所墓にはいることのみの選択肢のなか、あとはその時の葬儀費用から納骨までの出費について不安色々を吐露されていました。娘に負担をかけたくないと。
「なるようにしかならないのでケセラセラでしょう? 阿弥陀さんにまかせる他はナシ」と私が返すと、「それはお寺(・・・私)にまかせたい」とかなり現実的。
まぁ、その件日々考えていたら頭の中を不安がぐるぐる回っているだけ。
自分の死、その時の事を考えるのは悪いことではありませんが、ネガティブ思考だけで繰り返し思い悩めば精神的によくないですし治るべき病もその機会を逸します。
よって私はいつものように「放っておけ」でした。
それが「自然」というもの。
私としては人間なんて何時亡くなるかなど絶対にわからないものですし、突然、あっという間に亡くなる方もまたぞろいる中、「5年」の提示など悪くないのでは・・・?でしたが、逆にその期間の提示されることこそが日々のもやもやの原因であるとのことでした。
私だったらどうでしょう。
その病のみが私の終末の原因になるとは限りません。
人は多くの宿業と時々の縁、機会の組み合わせによって計り知れない「果」を得ますから。その偶然を予測するなど無意味。
とにかく「その時」まで生にこだわって生かされていく他はありませんね。
扨、画像は東本願寺の掲示板からですが、②の「み」の連続を見ると息子の幼少期のどもりを思い出します。
その語は今は放送禁止用語で、「吃音」がただしい呼び名になっていますが、彼は自分の名を発音する際に、名前の頭の「み」を連続して発音していました。
「みー、みー、みー、み~~・・・」というのが常で、保育園の友達から「セミ」と呼ばれていました。
それには親としてどうかとは思いますがその時私どもはただただ面白がって爆笑していました。
このまま成長したら、おつとめの発声等その他いろいろ、しんどいだろうな~とは思ったことはありましたが、放ったらかしにしたまま。
忘れたころ気づけばなぜかうまい具合に治っていたのでした。
なんでもかんでも「勝手にしやがれ」が合言葉。
いい方向に向かうこともあります。おかげさま。
2024年
5月
17日
金
分陀利華 高原の陸地には 蓮華を生ぜず
先日、ご門徒さんから「そろそろ父がヤバい」と。
以前は拙寺バス遠足にも参加いただいている方で、よく存じ上げていますが、高齢にも関わらず(90代)愛車の軽トラでいろいろ出没、拙寺にも気軽にひょいと訪れることしばしばでした。
最近はお顔を拝見することが無くなったのは例の「免許証返上」を行ったからです。
その方の娘さんはその父親から車を取り上げた事によるやる気と筋力の衰えを惹起させたことについて悔いていました。
私は免許証の返上流行りの世間の流れは大反対。
本人の意志に反して免許証を取り上げるというのが今の社会の流れではありますが、それによって健康長寿までも返上することになるということを皆さんご理解いただけないようで。
それを言うと奥方は「自分の免許証保持」についてそれをただ家族に肯定させるための偽りの言葉であろう・・などと一笑に付しますがそれは大違いです。
私は年配者の起こす交通事故についてことさら例のアクセルとブレーキの踏み間違い等あげつらい、あたかも心身機能の老化とその事故を結び付けて年配者に自動車を運転させることはけしからんということ、いかにも短絡的であると。
では事故を起こして他人様を傷つけたらどうするの?と反論されてしまいました。
それはどなたであっても同じこと、当然事故は御免ですし避けるべきものです。
しかし、ミスを犯すということは人間だからどうしようもないこと。よってそのまさかの坂の痛みを補填するために保険というシステムが社会の潤滑油として機能しているのだと。
それで世の中が回っているのですから。
そしてそもそも、事故を起こすことは、年配者だけではないということ。
いたずらに右に倣えでお爺お婆から車を奪うことなかれ。
返納は個人の意思に任せるべき。
私の知りうる限り、返納した年配者は、その途端に体力、耐力、精神力・・・心身の急激な下り坂の躰の発現について見聞きしています。
どなたでもタイミング次第では事故に遭遇するものです。
嫌悪すべきことですが仕方がありません。
ある意味、割り切りというものが必要かも知れません。
扨、画像は先日の白州遠足の帰り途。
私が運転すれば「躑躅ケ崎」方面と言うも、それに賛同する方は不在、どなたかの運転でこちらにて休憩することになりました。
清泉寮でアイスクリームというものです。
私は一口だけ奥方のそれをいただきましたがそれだけで結構。
それよりこの地で私が想ったのは念仏者「分陀利華」 (白蓮華)のこと。
そしてその尊い蓮華の育つ場所についての件を。
「高原の陸地(ろくじ)には 蓮華を生ぜず
卑湿の淤泥 いまし蓮華を生ず」
蓮華の五徳の一です。
こういった爽やかで清々しい場所に念仏は育たないのだな・・・
などと。
雑多でドロドロ、人々の中にそれは生まれるのでしょうね。
ちょっとばかし極論でしょうか。
2024年
5月
16日
木
人生に正解なし 人生すべて無駄なし 本山標語から
生の水はよくない・・・と同行していた方から御注進いただきましたので流石の白州の水といえどもその意見に敬意を表して、一旦沸かしてから飲むことにしました。
昨日は正信偈の拝読2回を含め色々な場所でおしゃべりをしまくりましたので、夕刻には喉の擦り減らし感がありました。
よって奥方にポットに入れたそのお湯でのミルクティーを所望したのでした。
やはり「美味い」と感じましたが、かの地で比較的お高めの価格で販売されていた「白州の米」が地元昼食屋さんで提供され、奥方他ご一同「美味い」と絶賛されていましたが、私にはよくわからない・・・というのが本当のところ。よって私の味覚などまったくアテにできるものではなしです。
ただ南アルプス系の水は癖もなく、喉をすんなり柔らかに通り過ぎる感があることは確か。それを「美味い」というのでしょうね。
扨、奥方から「最近御前(おまえ)はお寺の掲示板を更新しないようだね!!」とのご指摘。
「アレはみんなそれぞれの境遇で眺めてそれぞれ何かヒントにするものであって、それサボること×!!」と続けて。
まったくその通りです。
ブログの更新はすれどもそれはブログを見る人だけ、むしろお寺としてはネット環境のない人に向けた掲示板こそが大切であり寺・宗旨のメッセージは掲示板へ・・・が正解ということですね。
ここのところ、各所に記されたメッセージを記していましたが、それをそのままプリントアウトしてもいいのですがね。
掲示板放ったらかしになってしばらく、大した時間をとるでもありません。今一度見直していかなくては・・・
真宗本廟東本願寺、烏丸通に面して立つ標語たち。
表記は先日記した「善か悪か・・・わからない」に通じるものがあります。
2024年
5月
15日
水
草原の空気 道の駅はくしゅう 目には青葉
やるべきこと山積の中、昨日は以前から予定を入れていた山梨へ「水」関わりテーマの遠足に向かいました。
10人乗りのワンボックスを借りて。
この日に向かうことは確定していたため、荒天であったとしてもその覚悟はしていましたがまさかこれほど晴れてくれるとは・・・
スカッとした晴れ間に空気の美味さというものを思う存分噛み締めました。
欲を言えば一人でのんびり昼寝などできたら・・・などと思いましたが帰りに出張った清里高原では10分程度で鼻声になってしまうほどの涼しさ。
半袖であのまま昼寝をしたとすれば間違いなく風邪をひいたことでしょう。
画像は北杜市白州町の「道の駅 はくしゅう」から。
空のペットボトルを持参してこの施設にある水汲み場から注水キープ。
こちらには山口素堂(1642~1716)のかの有名な句の石碑が建てられていました。
「目には青葉 山ほととぎす 初かつお」
5月~6月頃の季節感満載の句ですね。要は今。
山口はこちら白州の出身ということで、この句はきっとこの地域の人々の宝物なのでしょう。
その羅列を見ただけでもみずみずしさを感じます。
⑦は「お土産」とはあるものの遠州から訪れた者の土産にはなりません。
吉田町の木村飲料のいろいろですからね。それは最近各地で見かけるようになりました。
私は以前、岐阜でその手の飲料水を土産として購入、あとで気づいて苦笑いした経験がありました。
⑧画像は昨日の富士山。
以前の春先のものと比べてもその違いがわかります。
2024年
5月
14日
火
お前は善人 ?悪人 ?・・・「わからない」 OH 真宗的 !
昨日は拙ブログで「教員は自分の時間が持てなくて気の毒」のようなことを記していましたがこのほど文科省の中教審の部会の教員の働き方改革と処遇改善についての議論がまとまったと昨晩のニュースでありました。
何やら残業代を払わない代わりに支払う上乗せ分に関して月給の「4%→10%以上にすべき」とのものだそうですが、これまでの「定額働かせ放題」なる「残業ずるずるだらだら無制限」の悪慣例は残るとのこと。
ニュースでは教職志望という方がインタビューを受けていましたが「それなら、やっぱやめた~」の気持ちを吐露されていました。
以前もその件ブログにて記していますが、御門徒さんの若者で教職員志望などと聞けば私は必ず「およしなさい」などと持論を展開して違う方向性、検討を促していますがその結論は当たり前というか自然です。
「自分を殺す」仕事に敢えて就くという気概があるのなら別ですが。
「教職員は最高」と誇れる抜本的処遇改革が文科省から提起されるまではまずおよしなさい。それが身のため。さもないと後悔することになります。
扨、「丘の上の本屋さん」なるユニセフとイタリアの共同制作の映画がありました。私は2回視聴しましたが。
その古本屋の老主人「リベロ」 (「自由」の意 レモ・ジローネ)の容貌と言葉が醸し出す知的な優しさが忘れられないでいたのですが、最近のハリウッド映画(「イコライザー THE FINAL」)にその姿を見ることができました。
主人公がやっつけたマフィアのボスの子供に後ろから撃たれて負傷、医師の元に運び込まれ、その時医師(レモ・ジローネ)が彼に声を掛けた言葉が表記「お前は善人か、それとも悪人か」の問いでした。
彼は少々の間をおいて「わからない・・・」と。
映画の後半で彼が「あの時何故私を」助けたのか問うと医師は「わからないと応えたからだ」と。
私はついつい閻魔さんと玻璃の鏡のエピソードを思い出しました。その閻魔さんの問いとは「お前は嘘をついたことがあるか」でその状況とは違いますが、まず人はその嘘の件、我こそ助かりたい(地獄は御免だ)の欲から「生涯、嘘などついたことはありません」の大ハッタリの言を吐き結果、地獄に堕ちることになるのでした。
そこでの私のそのシチュエーションにおける正解を示せば「嘘ばかりの人生で愚かな私に為すすべはありません」などと正直に応えるに限ると~地獄は一定すみかぞかし(歎異抄)~いうのが皆さんへのおススメでした。
その医師が阿弥陀さんの化身と考え、「善人-悪人」の問いの応えとしてその「わからない」はベストであってそれこそが真宗的であると感動した次第。
一言で「悪人正機」(歎異抄三条)ではありますが、
歎異抄十三条には宿業(因縁果の無数の組み合わせ)の結果、善悪というものは自身では選べないといいます。
「よきこころのをこるも 宿業のもよほすゆへなり
悪事のおもはれせらるるも 悪業のはからふゆへなり」
確か以前も記したかと思いますが夏目漱石の「こころ」の一節に「先生」が主人公に語った悪人についての名言がありました。
「君は今 君の親戚なぞの中に これといって悪い人間はいないようだといいましたね しかし悪い人間という一種の人間が世の中にあると君は思っているんですか
そんな鋳型に入れたような悪人は 世の中にあるはずがありませんよ 平生はみんな善人なんです 少なくともみんな普通の人間なんです
それがいざという間際に 急に悪人に変わるんだから 恐ろしいのです」
善悪の物差し、正義の物差しが人によって違い心の中にある「スケール」そのものに限界があるということでしょう。
矛盾と思い込み、煩悩熾盛の私があるからこそなのですが、映画の主人公が医師に問われて「わからない」と応えるのはまさにそれが真宗的だと。
医師(私からすれば阿弥陀)は主人公のそれ(わからないこと)への気づきを評価して治療を施した(助けた)ということです。
画像は以前横浜で息子がお世話になったお寺の標語から。
2024年
5月
13日
月
本山東本願寺回廊の掲示板 人という鏡で己を
一昨日の夕刻、狛江から来られたN氏と初めての対面。
元々静岡県人で縁あってその地に生活の場を移されているそうでした。
その日は別件相良のお寺で法事があり、帰宅前に立ち寄ったということだそうで私の携帯に直接電話がありました。
たまたまその時、大した理由もなく別の場所にいましたので20分ほどお待ちいただき合流しました。
当家のルーツと元は同じを感じ取っての来訪、少しの時間でしたが、楽しく会話が進みました。
別れ際に狛江からと聞いていましたので、これからの帰宅は大変・・・ということと、私も学生時代に喜多見(小田急線の狛江の隣)に住んでいたことを懐かしがって話すと、では学校はという件になりました。
知る人ぞ知る・・・小さな学校ですからその名を示すと「それなら住職の後輩です!!」と高ぶった声で。
驚きましたね。何たる奇遇でしょう。
学生数が少ない学校で静岡県内でそこの卒業生と遭遇することはまずないと思っていましたので。
ちなみに彼は静岡高校出身とのこと。
今は無き当時のレストランやら麻雀店、今はマンションとなったテニスコートの名称が飛び出て感激しました。
再会を期し別れましたが藤枝・相良に縁者がいてちょくちょくこの辺りにも来られているそう。
そして昨日は甲府からのお客さんが。
母親が3人の子供達を連れて来られたのですが数日前に電話があってちょっとしたお話を。
「いずれ伺いま~す―いつでもお気軽にど~ぞ」といった感じで電話を切ったのでしたが、まさかこんなに早く登場されるとは。
「子供達も楽しみにしていました」とあまりにも光栄なことを、仰る。よって本堂でしばしの時間を。
拙寺とはまったく関係がないわけではないご一家(本家筋は相良に)ですが、今一番お母さんが思うことは子供の教育の件なのでした。
教師に毎度怒られまくっている・・・のようなことをお母さんが。
「それなら私とおんなじ」「息子もおんなじ」・・・みんなおなじ。中には大人しくて怒らることとは縁のない子もいますが、それと比較すること全く非ず。
「個性ですね・・・」でした。
今、教師は大変です。
自分の時間というものが無いのとたくさんの生徒を観なくてはならないというプレッシャーがあって、余裕というものがなくなって「カリカリする・・・」。よって「むしろ先生に同情してあげれば ?・・・」と。可哀想な仕事をされている・・・
最後に「けせらせら」・・・なるようにしかならない・・・山あり谷あり痛みいろいろは自分で感じて・・・「感謝しながら、楽しみながら おまかせしよう・・・」です。
受験勉強の苦難は今の時期だけ気合を入れろということ。
先祖に仏に「試されてる・・・」と考えましょう・・・。
海の近くに来たのですから、おいしいものを食べて帰ってね・・・また来てね・・・と別れました。
またも「聞く」ではなく「おしゃべり」にウェイトが行ってしまいました。「猛省せよ!!オレ」。
画像は先般歩いた真宗本廟(東本願寺)御影堂へ繋がる回廊に掛けられた掲示板。
「本当に自分を知るには
やはり人という鏡が なくてはならない」
聞く機会があることは格別です。
2024年
5月
12日
日
撮影OKの太っ腹 室生寺金堂特別企画 釈迦如来
私は朝からフリー。
息子は磯子で葬儀ということで動いていました。
前日から大和市の彼の祖母の家に。お天気で何より、雨天の高速道路と比べれば断然我らの気分が違うというもの。
葬儀終了後にそのまま帰路につくかと思いきや一旦大和の義母宅に戻っから東名高速綾瀬(ETC)から浜松に向かったとのこと。
私なら磯子から16号で北上、横浜インターだな・・・と奥方に。
すると彼は法衣から普段着に着替えのために戻るのが習慣だと。着替えをしなくては気が済まないようでした。
しかし私の場合?
どちらかの公園かSAの駐車場の車の陰で・・・、というのがいつものことです。よって彼のその習性を「妙に律儀」と感じるばかり。
法衣を確りと畳んでバックに仕舞うところもそう。
私は後ろの席に放り込むだけですから。
奥方の性格もそのようなものですから、どこからその几帳面の風が伝わったのか不明中の不明です。
扨、昨日の金堂のお内陣を。
平安当初とは微妙にその並びには変更があるようですが現状三尊形式。中央の本尊は榧の一木釈迦如来。
向かって右が薬師如来、左が文殊菩薩です。
脇の両仏像(重文指定)の「身長」が違うところからやはり何らかの変更があったことがうかがわれます。
三尊を囲むように薬師如来の従者といわれる十二神将のうちの子神・丑神・午神・申神・戌神・亥神の六体(重文)が。
本尊の後ろにはさらに二つの国宝があります。
国宝の釈迦如来の光背単体⑨とさらにその背後の壁面に嵌め込まれた帝釈天曼荼羅の板絵⑩がそれ。
仏像はともかくとしてその舟形光背までも国宝指定というのにはこの寺の強烈な古さと半端ない偉大さ、奥深さ感じます。
⑦⑧は鰐口の図。
本来寺社御堂の正面上部に吊るされる金物で、ひも状の打ち物で音をだし祈願するというのがそのお参りの流れ。それが今は堂内にあるというところ。
これが昨日記した屋根の改修の名残です。
最後の画像の通り、スマホ撮影OKというのは面白い企画です。
「撮影禁止」をうたうお寺が数あるなかとても斬新です。
特別拝観の限定的企画ではありますが、観光で来られた皆さんには何とも楽しいサプライズ。
ただし「一眼レフはダメ」とのことでした。
2024年
5月
11日
土
仁王門 大日如来の梵字の池 鎧坂から金堂へ 室生寺
朝一は墓前あげ経ののち作業スタイルに着替えて静波墓園へ。
好天につき連休明けの初仕事でした。
未回収の伐採材がまだ残っていますが墓域三面あるうちの二面(南と西)はバッチリやっつけました。
東面は2年前にそちらだけ手掛けていますので今回はそれをどうしようか迷っています。
というのもそちらの面は隣接する民家の畑の境界ですのでスカスカに伐ったとしたらそちらが丸見えになってしまいます。
まぁ気にすることはないといえばないのですが、それに手を入れればさらに1~2日余計に時間がかかるでしょうね。
のんびりこつこつでいいのですがね。
昨日の処理費は1120円でした。
扨、先日記した室生寺仁王門を潜れば左手に池がありましたが(その時の画像⑥⑦) 、梵字の名の記された掲示がありました。
「バン」の文字ですがそれは真言系では広く崇拝の対象となる大日如来のことですね。
池そのもののカタチがその文字であるとのこと。
もと弁財天の社があったそうでちなみに水天も同じ梵字。
このバンの文字=大日如来というのが通常ですが・・・。
その池を左手にして進めば目前には鎧坂なる階段が。
鎧の草摺のイメージから鎧坂という名になったそう。
歩を進めれば金堂の屋根から段々と全景が。
こちらが平安初期の建立となる金堂で勿論国宝指定になります。
江戸時代に手が加えられて杮葺きの屋根を追加で張り出させて(縋る破風-「すがる破風」)外陣を作り段を下げ柱を伸ばして懸造りにしています。それに伴って廻り縁もめぐらしています。
②梵字は当真宗系にはまったく縁がありませんのでどうでもいいことではありますが、古い墓にはこの梵字がつきもの。
参考までに。
真言系は前述したように大日如来が宇宙の中心という発想ですので、我らがトップの阿弥陀さんは出てくるには出てきますがウェイトが低いようで。
ただし大日如来の像は曼荼羅としてはお目に掛かることが多く仏像としてはそうではありませんね。
2024年
5月
10日
金
耳を傾ければその声が 「聞十方」
春先に、なかなか動きだそうとしない大工さんに(会館)工事開始について伺ったところ「建築確認が降りてから」ということでしたがしばらくして「確認は下りなかった・・・」と。
図面を書き直して再申請といわれたのが春の法要の世話人会の前日のこと(3月)。
今、今年の盂蘭盆会法要の世話人会について参考にしようと昨年の資料を見回すとその第一の議題に「会館新築工事の遅延について」とあってため息が。
今年は「さらなる遅延」と書き換えておきました。
しかし、申請が下りる前に「やれることはあるはず」と一緒に依頼していた墓地の外周補修やら、門の壁を1/3ほど除去する工事について指摘していましたが「そろそろやります」と言ったっきりその動向なし。
ホントはその世話人会で総代が皆さんの前でその話をしてから大工さんに「直電する」と息巻いていたのを制止した私がイケなかったのでしょうか。
あくまでも奥方主導の工事ですから私はできるだけ口を出さないようにしていましたが、「それが悪いのだ」と奥方より。
来年一月の完成はムリであると1月の段階で言っていましたからそれから3か月以上。
このままでは来年の完成も怪しいところです。
コロナ前に発注してこの様。まったくもって複雑怪奇。
御門徒さんということもあって私どもの主張のトーンは低くなりがちですが、彼は現状これまで副業だった趣味の漁労の成功(新聞紙上に写真入りで名が出るほど)によってそれどころではない・・・というところでしょうが、それならそれで「や~めた~」と言ってくれた方が私どもとしてはまだラクなのでした。
まぁ普通ではありえないことですがね。
「まかせる」しかありません。それが私どものスタンスですから。
しかし、以前も記しましたように外トイレの完成が遅れるのは非常に厳しく、先日は本堂隣接の庫裏の客用女子トイレを和便から洋便への工事をしたばかりでした。
来年は大河ドラマ期待で大いに人を招こうと目論んでいるというのに・・・。外トイレが無いのは辛すぎる。
扨、オエライお役人さんというものは人の話を聞かないというのが常ですね(環境省の水俣病「マイクオフ」の件)。
まぁあの手の連中もそうですが私たち人間という生き物は殆どその件、嫌いです。アレほど悪辣ではありませんが。
それがわかっているから当流は「聞け、聞け」・・・「聞法」一大事などと重ねて言い聞かせているワケで。
聞くことによって気づき、智慧となる・・・お話ができないと聞くことなどできませんから、率先して話す。あくまでも聞くことに重点を置いて・・・
画像は本堂側の庫裏の客用トイレ前の図。
半年くらい前に玄関やら仏間に散らかっていたいろいろをこちらに掛けてみました。
まったく無脈略、一貫性ない提示でかつ、ゴチャゴチャ感満載。
その中にあるのが真宗大谷派の善智識、金子大栄の「聞十方」。
毎日何度もコレを目にする私。
それでも聞き切れていない。
④は正信偈から。10句目にその件が。
2024年
5月
09日
木
仁王門の青と赤は昭和の遺構 それより赤とピンク
母親に連れられて「念のため」と医師の元に。
御門徒さんの息子さんが、通勤途中に東名高速のトンネル内でスピンして愛車がクラッシュしたといいます。
身の毛もよだつシチュエーション。
話を聞いていてよくそれで済んだものだと感心したのでしたが、どういう経緯か彼は事故後当初会社に入ったとのこと。
報告を受けた母親が「それはマズイ」とばかりに彼の身を回収に出向き診察に同行。
彼は私の息子より3歳ほど若いのですが車好きで、私からすれば気が遠くなるほどのお金を車にかけていたようです。
原因はウィンカーもナシに前に割り込んで来た車を避けたためだといいますが、その車は後方の事故をよそにその場を立ち去ってしまったと。
そのあとのことは知りませんが、いずれは色々判明するかと。
とにかく、ケガがなくて良かった。
扨、室生寺の三宝杉ならぬ二本杉を過ぎて仁王門を潜り境内へ。
先般は長谷寺に奥方を案内したのは突然のひらめきだったわけで、本来はパスするつもりでした。
長谷寺のあの階段を見て不機嫌になり、最近は特に「奈良には一人で行け」と突き放すようになってしまったのですが、実はその長谷寺行脚の直前にこちらの室生寺を上り下りしていたのでした。
そちらで一番高い場所、奥の院まで往復していました。
案外と観光客も多く、それで疲れるところもありますが、知る人ぞ知る、あの奥の院の道のりの階段続きの様は、もし遠足に皆さんを引率したとすればやはり長谷寺以上にクレームが出るところでしょう。
結構な頻度でありますが「ムリ!!」と仰る方に「バスで待っててください」「下で待っててください」というのは私も辛い。
しかし、この手の山岳信仰の寺で階段のない古刹などないでしょうからね。
室生寺の晩春といえば石楠花ですが、私どもが歩いた頃はそれには少しばかり早かったようです。
仁王門は昭和四十年の再建、令和になる前までは檜皮葺だったとのこと。現在は銅葺。
お楽しみはさらに上です。
2024年
5月
08日
水
嘘かホントか歩いてみなくちゃ気が済まない 猫ケ城
先日の法要の参加者で私と同年代の男性が、転んで顔を強打して前歯を2本折ってしまい散々の思いをしたとのこと。
その奥さんは「どうして手で防げなかったのか…」と強く指摘していましたが、タイミング次第では上手くその防御姿勢(受身)など取れるはずもなく。
私も先日、本堂裏で真っ平らの石の上、~自然石ですから多少の高低はありますが・・・そこで躓いて転びました。勿論スニーカーを履いていました。
一段低くなった土の上にダイブしたようなカタチになりましたが真っ先に右腕が出てただ擦りむいた程度で済みました。
近くにいたお参りの方たちの方が驚いていたくらいです。
ちょっぴり恥ずかしかったですが。
私は常々阿弥陀仏、念仏世界に傾倒した良寛さん(曹洞宗)の
「災難に逢う時節には 災難に逢うがよく候
死ぬ時節には死ぬがよく候
これはこれ災難をのがるる 妙法にて候」
ではありませんが、①高い場所にいれば落ちる、②跳ねれば転ぶ、そして③ただ歩けば躓く・・・ものと頭にいれてはいるもののその最後の③は、ふつうは「年のせい」と承認してしまいます。
それは筋力が落ちているからに相違ありません。
要は躓く理由としてふくらはぎの筋肉が落ちて踵があがっていないということですね。
普段転ばない場所で転んだら・・・筋力低下を疑え・・・でしょうか。
扨、宇陀の山中、一応は街道筋(吉野室生寺針線)とはいえましょうが室生寺より南下、殆ど「山でしょ」と思わせる室生川の支流胎の川と名称が変わってしばらく「猫ケ城跡」の関標が目に入りました⑤画像(場所はこちら)。
通常は城址を顕彰する掲示板があるものですが、あるのはこの石標のみでまさに半信半疑。
聞いたことも無いそして、興味のある名であるとして勝手に感動しました。
ということで奥方を助手席に残し「ちょっとね・・・」とその指す道にとりつきました。
こういう場所を平チャラで進むものですからダニにやられるのですが。
谷筋に小さな小川が流れていてそれに沿って上がると削平された台地に突き当たりました。途中石垣の崩れたと見受けられる箇所があったり、段丘上になってその石垣が目に付いたり・・・
そしてどうやら他人様の家の裏手に出てしまったよう。
さらにその先に段丘がありましたが、これ以上進むと通報レベルになりますので断念。
「何のこっちゃあねぇ、来るんじゃなかった・・・」などとぶつくさ独り言をいいながら降りているとその小川を超えるときに大いに躓きました。
両手がしっかり出てケガはなかったのですが、首に掛けていたNIKONが岩に激突。①の如く変形しフィルター部分が不動となりました。
私はあのカメラを守るために何度も痛い目にあっていますが、急坂山道はスマホで十分でした。
尚、カメラは以降何事もなかったように使用できていますが奥方に「新しいのを・・」と試しに振ってみると即却下。
大ヘマをやらかしたのでしたがこれで済んで良かったと思いましょう。
「猫ケ城」についていつもの城郭大系をめくってみましたがその名は無し。ネット上どちらにも見当たりませんでした。
宇陀市にはかなりの数の城址が伝わっていますので、何らかの城砦であったことは大いに推測できますが、城郭には城の各曲輪たちとともに家臣団屋敷を「根古屋」 (こちらほか多数-サイトマップにて検索を)と呼ぶことがありますがその辺りから「根古がネコ」に化けたのかも知れません。
ぱっと見ただの「山」、こじつければ曲輪・・・、確証なし。
2024年
5月
07日
火
寺の倒木 近隣に多大な被害を 室生寺太鼓橋から
昨日は御年102歳というご長寿の方のお弔いへ。
世間でよくいわれる痴呆症などは一切なし。90代後半までお店に出て会計の仕事に携わっていたといいます。
最近は叔母の入所する施設にいらして姉貴分として叔母も大層お世話になっていたかと。相良出身者コミュニティができていたといいます。
やはり体力の衰えのきっかけは骨折から。
それも2度目の骨折が悪かったよう。
私の知るところ叔母も母の場合もそうでしたが、骨折して歩けなくなってしまうと心身ともに一気に衰えてしまいます。
かといって「骨折しないように」などとは言えません。
「歩くな」というのと同じですからね。
骨折しないように歩く、転ばないように歩く・・などなどと口で言うことはカンタンですが真っ平らなところで毎度転んでその不思議に首を傾げている私、それは不可能としかいいようがありません。
寂しがるはずです。叔母にはその話を伝えるのはやめましょう。施設で「ウナギ食わせろ ウナギはどうなっているんだ」と私を呼びつけるよう言っているそうですが。
扨、大野寺の摩崖仏を見たあとは近くの室生寺へ。
道路の通行止め箇所があって迂回させられましたが大した時間ではありませんでした。
室生川に架かる太鼓橋(場所はこちら)を渡ってすぐ樹齢100年以上といわれる杉が三本・・・ということで「三宝杉」なる看板がありましたが何故か今は二本なのでした。
その並び立つ姿はさぞかし凛々しいものがあったでしょうがそのうちの一本が2022年6月18日に室生川側に倒れてしまったとのことでした(報道記事)。
こちらに限らず、杉の大木はここかしこに聳え立つお寺ですからそのうちの1本が倒れてなくなったとしても大したことはないのでしょうが、やはり恐ろしいのは他人様を傷つけたり、物を壊してしまう事。
それならば残り二本も切り倒したら・・・という意見も必ず出てくるのでしょうが自然倒木ならば気持ちの落としどころはありますが、伐採となると心穏やかではないですね。
川の縁だけに根の張りが弱いということでそれは仕方ないのでしょうが。
拙寺も倒木と枝の落下についていつも冷や冷やさせられていますが、本堂を壊しあるいは周辺民家を潰すこともありうる話で室生寺のその件知った時まさに他人事とは思えぬ・・・と保険対応可能か・・・などと考えた次第。
やはりまったく不十分。
夜逃げレベルの問題だけに日ごろから樹木の様子、診断目視は必要です。
そういえば先日も清水寺近くの土産物通の坂でサクラの古木が倒れて歩行者が怪我を負っていましたね。
2024年
5月
06日
月
史料館前の松 境内の手負いのヤマバト
昨日も続いて好天に恵まれました。
やるべきことは山積で何事も無ければ真っ黒に日焼けして汗だくになってへろへろになるのもヨシなのですが、夕刻から法縁があったため大人しくただ静かに過ごしました。
多少の植木と土いじりは行いましたが・・・
GWが終わると天気は雨といいますが、それはまた困りますね・・・
連休中の墓参りで花ガラの袋は三袋に。
袋の中に雨が溜まことは避けたいところで、降雨前に屋根下には移動しますがそもそも雨降りでは処理場に持ちこむことができません。
詮無きこととはいえ希望を言えばGW中は多少天気が悪くてもそれが明けた時、バッチリ晴れてくれればよかったのに~
そう都合よくいくかボケ・・・と父親に笑われそう。
5月6日は先代(父)の命日。
あの時分の色々な事、まるで昨日のことのように感じます。
11年も経ってしまいました。嘘のよう・・・
昨晩は日曜美術館(再)で富岡鉄斎を流し見。
一休と蓮如のエピソードが描かれた絵も紹介されていました。
蓮如さんを訪ねてきた一休さんが不在の蓮如さんをよそに本尊の阿弥陀さんを倒して枕に。
昼寝をしているところに蓮如さんが帰って来たというシチュエーションです。
一休さんの破天荒振りと蓮如さんの一休さんへの敬意とユニークさがわかのます。
昨晩の法縁のお話もいつもながら蓮如さんの御文からでした。
扨、画像は先日伺った史跡調査会会合の際目に入った松。
剪定されたことがわかります。
②は先般発行された相良御殿についてのパンフの表紙ですが、時間的都合から松はボサボサのままでした。
これから色々なところから相良に人がやってくることを見込んでキレイにされたよう。
松も生きていますからスグに成長繁茂しますからね。管理は大変です。
③④は左足が欠損した本堂前のヤマバト。
昨日初めて彼のその状況を知りました。
拙寺には現状つがいが2組、単独が2種ほどいますが、そのうちの誰なのかはわかりません。
人を怖がりませんので古株でしょうね。
自然の中の事とはいえ彼らの生活は厳しい。卵をカラスにさらわれたり・・・何とか見守ってあげたい。
左の足が悪いので左の翼で時に体を支えながら餌をついばんでいました。
本堂大棟の上でカラスが待機している様を見て、「コラっ」と大きい声を出しているところにお参りの方が来られて「どうしたの・・・? 」と声を掛けられてしまいました。
見上げるとカラスも屋根の上から「こっちも生きてるぞ」と主張していましたね。
2024年
5月
05日
日
巨岩の弥勒菩薩 宇陀大野寺
べらぼうに良き天気で空気もうまいし言うことなし。
私は久々「自宅法要」のご縁で原の鬼女新田に向かいました。
尚、回忌法要は施主の希望により主として①自宅お内仏に私がお邪魔して簡単なお勤めとご挨拶②本堂に一同参集して本法要③墓前という流れになりますが、昨日は①ご自宅で本法要②墓③本堂で簡単なお勤めとご挨拶という順序段取りとなりました。
原ということで五月の風と青空に鶯の鳴き声と心が洗われる心地。
ご自宅裏の墓碑には「倶会一処」。
三つ折り本尊を中央に置いてお勤めと焼香タイム。
ついつい余計なおしゃべりをして、その大切な本尊を石塔前に置き忘れご指摘を受ける始末。
以前からそれをやらかして墓前まで取りに戻ることしばしば。
不始末の経験が生きてきませんね。
自宅法要が終わって仏前で着替えをしますが、自坊に帰って衣を脱いだ際、ひょっとして裏返しに着ていたかも・・・という不安に襲われました。それさえもよくわからない・・・
まったくアホ丸出しで・・・
昨日も記しましたがどうであっても、おまかせしてありますから・・・変な開き直り。
扨、大野寺はシダレでも名のあるお寺ですが門前を流れる宇陀川の向こう岸に弥勒摩崖仏があり、こちらの方もなかなか有名。
私はサクラよりもこちらが本来の目的でした。
笠置山のアレを倣ったようですね。
こちらにも弥勒浄土が・・・と感動したいところですが、私の老化している眼にはなかなか判別できず、隣にいる奥方に「見えないのか・・・」とバカにされました。老眼は近いところが見えにくいというのがお決まりなのに・・・
奥の駐車場に入る前に道路通過中、右手の岸の崖に「何かある」というのはわかりましたが・・・入館料を払って境内に入って初めてそれがそれだと判った次第。またもマヌケ。
私は阿弥陀さんがわかればそれでヨシ。
「愚かなる 身こそなかなか うれしけれ
弥陀の誓ひに あふと思えば」(良寛)
蛇足・・・良寛さんは真宗(浄土系)の坊さんではありません。
2024年
5月
04日
土
宇陀大野寺 桜まつりの終わり頃 おまかせ でまかせ
5月3日からの連休後半、5日ころまでのお天気は最高との予想。昨日、あまりの好天に恵まれた法事のあと「それにしても良かったですね」と施主さんに振ると「ごめんなさ~い」と。
「こんな日に法事を入れた・・・」と皮肉を言われたとでも思われたのでしょうね。
いやいやまったく・・・そんなことはないない・・・法要後テレビをつけると一昨日滞留した小田原の様子が映し出されていました。超絶の人混みで私もこれまであのような様を見たことがないくらい。くわばらくわばら。
イベントが開催されていたようですが、基本そういうものの見物の場には足を踏み入れないというのが心情ですからその一日のズレに安堵しました。何という仕合せでしょう。
知らなかったとはいえもし遭遇していたら・・・地団太モノ、己の軽率を呪うでしょうね。
私の希望は今度またどちらかの好天に恵まれた日に人のいない場所(墓・寺・城)をただブラつくだけです。
昨日の法縁後のご挨拶では、人間とは「同じで違う」また「違っていてまた同じ・・・」。
人は皆同じ(四苦八苦ほか・・・)でありながら性質ほか違うことだらけ。そして当流宗旨キャンペーンは「違っていて それでいい」です。
同一も異質も人それぞれ色々あってヨシ。
自分の「思い込み」によって他者を評価し排除しようとする心が生まれるのもその異質を心底承認できないからですね。
それが国同士でエスカレートする戦争でした。
まぁそれを歎異抄から良法借りれば「業報にさしまかせ」 (13条)でしょうか。
拙ブログで私が結構に記させていただいている「おまかせ」の (強調の)「さし」付きの件。
まかせるのは阿弥陀さんですので私は「計らない」。
最近口癖のように言うようになった「どうでもイイ」の他者が聞けば投げやりに聞こえる言葉がありますが要はそれ「他力」の真髄。
まかせてあるからどうでもいい・・・のですが、それでいてその通りの完全「おまかせ」とは程遠い大矛盾の私があります。
奥方の指摘によればただの「でまかせ」の類と。
扨、既にサクラのシーズンは終わってしまいましたが宇陀大野寺のシダレです(場所はこちら)。
宇陀のサクラといえば数年前にやはり奥方と訪れた又兵衛桜(こちらも)がありました。
案外バスで来られる方がいて驚かされましたね。
昨日も小田原駅発の元箱根行きのバスの大混雑について記しましたが耐え切れない苦痛になる場合あるかと。時間調整もそう。
私は車載のナビに入力すればどちにらでも連れて行ってもらえるお気軽もあって車は手放せません。
今やどうやってバスに乗っていいのか・・・わかりませんし。
その車を私から奪うという動きは息子と奥方からボチボチ出てきていますがそれこそ地獄行き。
2024年
5月
03日
金
しんらんさまめぐり いつかは歩いてみたい
朝6時20分に家を出て義母宅に向かいました。
数日前に「テレビが壊れた」との報があって、何とか予定をここに突っ込んだという次第。
予め用意していたブツを搬送、何とかうまいこと設置することができました。
問題は地上波ほか衛星放送もアンテナがないいわゆるケーブルテレビだったこと。
何度かチャレンジし、同じケーブルテレビ会社だという「奥の墓道」氏にアドバイスを受けるなどしてその難題をのりきったのですが、それは機材の裏に明示されたサーピスセンターに電話して聞く事。
ご指示通りにステップを踏むとすべて改善していました。
ケーブルテレビ会社のリモコンと持参したテレビの互換性が無かったこともその原因でした。
昨日は連休の谷間ということもあって高速道路ほか一般道もまた空いていました。
目に留まったのは行きがけ2台、帰路2台の故障車の件。
自分がその立場だったとしたら「酷い災難」と横目にして通過。
うち3台は古そうな車でただの整備の問題かとも思いましたが箱根新道の七曲直前での突然の渋滞の先にあったのは新しめ高価そうな東京ナンバーの家族連れワンボックス車でした。
家族サービスは台無しですね。
運転手のお父さんは携帯電話と睨めっこ。
依頼したレッカー屋によっては何処に降りることになるのかわかりませんから。
パトカーのお巡りさんが片側車線規制を行っていましたがそれはまた大変。
渋滞に巻き込まれた皆さんもお巡りさんがいなければ罵声をあげたくなるところでしょうね。
部外者としてはやはり腹が立つのは当たり前。こちら(7.7キロ標識付近)で渋滞することは冬場の降雪・凍結以外あまり見たことがありませんし。あと少し上がればチェーン装着場がありますから、あの段階で不動に陥ってしまったのでしょう。
新旧関係なく、車も故障しますね。人間もそれ、老若関係ありませんし。
また、小田原経由での帰宅でしたが、小田原駅前のバス乗車場、特に元箱根行きの外国人の列は見たことも無いような有様でした。円安で大挙来日、お気楽温泉観光は悪くないでしょうね。
ただしバス内はぎゅうぎゅう詰めの試練。
奥方が「白タクやったら儲かるかも」とポツリ。
扨、画像は本山で見かけた「しんらんさまめぐり」のポスター。
何故か漏れがありますが、それは私のポカでしょうね。
いつかは行ってみたい御開祖関りの旧跡。特に越後・関東行脚ははご開祖の基本。父母も何回かに分けて向かっている場所ですし。
2024年
5月
02日
木
聚楽第の碑→名和長年討死地は一条天皇里内裏 一条院
「相良は寿司屋難民になっちゃった」との弁。
あるご門徒さんの嘆きを聞きました。
相良でも古い料理屋、乃庄さんの閉店に続いて大栄館の閉店が続けざまにあったからです。
双方とも色々と事情が重なったということでしょうが、いつもその豪勢な味にお世話になっていた私どもの放言としてもその言葉にはここ相良住民の想いが伝わっているかと。
先日は大栄館の板前さんと立ち話しましたが、「それにしても
最近は市場に行っても魚がない」とのこと。
各閉店の事情以前に「魚」の不在はお話になりませんね。
気候がオカシイから・・・とはいいますが輸入食材は高騰、生活の困難さがクローズアップされつつあって、日本人の食の基本、漁業の衰退となればいよいよ危機的状況に陥るのでは。
人も居なくなり、残った人が生活できないとなるとやはりこの地は廃墟になってしまうのか・・・
扨、昨日の名和長年の戦死地と指定されている公園には一条天皇の「里内裏」の掲示があります。
一条天皇の御所跡でもあったわけすね。紫式部の言う内裏とはこちらのことのよう。
一条天皇といえばネコ好きで有名。
私は今節大河ドラマは一切視聴していませんが、それ(ネコ)以外は私の趣向と異にするからです。
①画像は昨日の①画像の逆。
奥に聚楽第石標のある交差点が見えます。
京都は遺跡遺構伝承が交錯する場。
どちらを掘っても調査の手が入るわけですね。
2024年
5月
01日
水
聚楽第の碑直近 名和長年討死の地
昨日、本堂の裏側で柱の最下部からシロアリの羽ばたきの図を目の当たりにして呆然。
来客中でしたのでスグに対応できませんでしたことが口惜しい。その後、退治グッズを持って現場に駆け付けると既に「散会」したあと。
根元には薬剤を撒いておきましたが気休めでしょうね。
驚かれたのは彼らの発生か早かったこと。
いつもの感覚からすれば「5月5日」以降なのですが・・・
4月末に羽アリの浮遊を視たのは初めてのこと。
まったく気候の変異は異常。
ぼちぼち床下に生石灰を撒いていこうか・・・最近それをしていなかったが故に発生したに違いありませんので。
扨、昨日は大山町鈑戸の地について記しましたが、伯耆の国とい
えば鳥取県民ならどなたでも知っている名和長年という人があります。
元弘の乱(太平記)で後醍醐天皇は笠置山(こちらも)で捕縛され、謀反人として隠岐に流されますがそちらからの脱出行、船上山での挙兵そして都へ復帰してからさらに鎌倉へ、北条氏を滅亡させました。名和長年はその功によって伯耆守に任じられます。
しかしその後後醍醐天皇は足利尊氏との関係が悪化して吉野に逃げ南北朝の混乱期に突入するわけで名和長年はじめ一統は後醍醐天皇方として奮戦しますが彼は討死とあいなります。
京都在住の頃の息子の寮が聚楽第址の例の碑の近くにあってその碑のある信号機のある四つ角がランドマークになっていましたが、その角を右折して殆どスグの場所、民家の間に挟まれて小さな児童公園があります。
そちらに「贈正一位名和長年公殉節之所」なる石碑が建っています。彼の討死の地との伝承です。
明治以降、足利尊氏が逆賊と貶められ、逆に高評価に奉られたのがこの名和長年でした。
名和一統は当初は伯耆でも地頭だったといいますが、伯耆守となって短期間ながら天皇復帰の功労者として「新政」の中枢にまで上ります。
その際、天皇から下賜されたのがあの帆掛け船の紋章。
当然にまた彼らが朝鮮半島から日本海の海運にもともと従事していて、その財力によってかなりの勢力を保っていたかと推測できます。
①聚楽第石標のある四つ角をハローワーク側から見た図。右側奥に木々の見える場所がその公園。
2024年
4月
30日
火
鈑戸(たたらど)の両墓制 鳥取県大山町 NHK番組から
昨日は鶯餅の発祥について記しましたが古来伝承に鶯王なる名が登場するようで、それに因んだ地があります。
以前拙ブログで仁徳天皇の別名「大鷦鷯天皇」とあるように鷦
鷯=ミソサザイなど、鳥は鳥でも怪鳥巨鳥ではなくごく小さなカワイイ鳥の類の名をつけていますから、その鶯王も「ふ~ん」と唸らされるところです。
強そうよりも賢そう美しい・・・がその名の選択する際のウェイトが強かったのでしょう。
信長の自称「第六天魔王」などのマヌケな名とは違いました。
鳥取県松江市法吉町(ほっきちょう)に法吉神社なる社がありますが、その名称が鶯の鳴き声に由来するという説、鳥取の旧国名が「伯耆」=「ほうき」でその名称自体がその音であるというもの。なるほど、いわれてみればそれで納得。
また伝説の一つにヤマタノオロチから喰われまいと山に逃げこんだ娘が「母来ませ~」と祈ったその「母来」から国名となったともありますが、ウグイスの鳴き声の方が面白い・・・。
前述の鶯王の件、その人は孝霊天皇の息子だといいます。
まぁその名は天皇の名もそうですが伝説の域を出ません・・・まぁそれはそれとして。
では何故にして天皇や天皇の息子がこの地にその伝承を残したか、想像したくなります。
孝霊天皇・・・高麗天皇・・・などの変化を考慮すると明らかに渡来系の示唆を感じますね。
古来からその渡来系の人々の文化移入と混血が無ければこの国の形成と成長はなかったというのは誰しもが認めるところですが鳥取県西伯郡(伯耆の国の西)大山町には高麗村という名がありました。まぁ日本の近江以西にはその手の渡来人をイメージする地がありました。
何故にこちら大山に・・・というところですが日本海側にあるということが重大な地勢。
朝鮮半島からの窓口、物流の拠点だったではないかとの連想です。
それは青銅器から鉄へ・・・という過渡期、勢力争い混沌の時、鉄を得た者こそが世を統べるというのは必定です。
農耕に使用すれば効率アップ、武器としても超ハイテク兵器であったわけですね。世の中を激変させるような・・・
特にその大山町にはその鉄製品加工を推することができる鈑戸なる地があります。
ついついこじつけたくなりますが「鈩」(たたら)とは一言で鉄材のこと。
その鉄材が流入する門戸でありこちら周辺で渡来人が技術を引っ提げて渡来、加工所を作って一大鉄製品流通の拠点になっていたと。
今はその面影を窺うことができませんがそれこそが歴史の移り変わりです。
扨、昨日は秀長の供養塔の件を記しました。
遺骸遺骨を実際に納める墓を本墓とすればその供養塔形式(遺物なし)のダブルあるいはそれ以上の複数の墓塔は信長など超有名人に多いものです。
その人の名を資源と目論む例もあったりするでしょうが、純粋な畏敬の念を表す場としてそのお気軽な場所にある供養塔は今風に言えばコンビニエンス。
拙ブログでは「埋め墓・詣り墓」(またはこちら)そして参考までに奈良の受取地蔵(またはこちら こちらも)など土葬墓繁盛時代の遺構と民の考え方を記してきました。
土葬墓とは別に故人の親族一同手を合わせる場として供養墓を建てるという風習の地域がありました。
その供養墓とは地域住民すべての縁者故人への思いを代表する墓塔ですね。
よって実際に故人を埋葬した場に足を運ぶことはなかったのでした。そちらを禁忌として足を踏み入れないよう伝承する倣いもあったようです。
以前その「鈑戸の両墓制」がサラっと登場したNHKの番組がありました。
「にっぽん縦断こころ旅」の鳥取編、2014年10月10日に放送されたものです。
画像は番組内のカットで、番組キャプチャーお借りしました。
私もいつもは流し見している番組ではありますが鳥取大山の両墓と聞いて、その件わくわくしながら録画したものです。
またこちらで面白いと思ったのは彼岸と此岸の連想。
鈑戸川を隔てた川向うの集落に供養墓(⑤⑥) 対岸に埋め墓というカタチ。
ただし、その供養墓にはよく聞くそれとは違って故人の爪・髪などを入れること。
今は橋が架かっていて気軽にこの埋め墓に来ることはできるようですが・・・
埋葬墓は画像ではそれを感じられませんが、基本的に埋葬場は河原であり納めた棺の上に河原石を積み上げるというもので墓標はナシ。よって縁者しかわからない。時間とともに消えていく・・・そんな感じのものだったよう。
時間の経過で棺は石の重さで崩れ、時に川の流れによって遺体は自然に帰っていくというものですね。
良き景色で感動しました。
そいえば親鸞さんも「賀茂川に流せ」と言っていました。
2024年
4月
29日
月
大納言秀長供養塔 長谷寺歴代能化墓所
本堂内陣と庫裏の温度は26℃、夜遅くまで蒸し暑さが続きました。
蝉の大音声は聞こえずともまさに夏、耳を澄ませばウグイスの声が、真っ青な空に響いていました。
嬉しくなるような良き天気でそんなお日和の遠乗りドライブは楽しかったでしょうね。
私は法事でしたが、施主さまたちは東京調布から。
さぞかし環八に世田谷通りは・・・と混雑を連想したのでしたが、その二つの幹線道路は通常時でも使用しないよう。
うまいこと裏道を駆使して東名高速で来られたとのことですが「案外スンナリ」の様。タイミングが絶妙だったのでしょう。
扨、ウグイスといえば和菓子の「鶯餅」。
私は好みではありませんが(粉だらけになって食べにくい!!)
この菓子の発祥が豊臣秀長ですね。
「アニキ」の接待のために大和郡山城主の秀長がその菓子を考案させ茶会に供したというものですね。
その城を歩き回ったことがありますが、今でもあるといわれるその菓子屋さんには気づきませんでした。
城の周囲を歩くことがなかったからですが。
再来年の大河ドラマが「豊臣兄弟 !」で豊臣秀長にスポットが当たるとのことですが、その鶯餅のエピソードの演出は大和郡山城とともに外せないところでしょうね。
当然に大和郡山市には大河ドラマ館などが建つのでしょう。
先般はその大河ドラマの報に「興味の外」くらいの小憎らしい雑言を吐いたわけです。
それは本願寺側から見た信長・秀吉嫌いからのものですが、もし秀長が秀吉より長生きしていたとしたらまた歴史はややこしくなって徳川の時代はなかったかも・・・と考えられるからですね。
本願寺顕如さんとの問題もどうなっていたかまったく未知数です。
尚、NHKBS 4月29日(月) 午後9:00〜午後10:00「英雄たちの選択」は長嶋一向一揆です。
画像①~③は長谷寺観光では最も著名な所ですがこれらより更に奥まった地に歴代能化墓所が。
そちらに秀長の供養塔があります。
この長谷寺復興の有徳人といえば豊臣秀長の名があがりますからね。
2024年
4月
28日
日
墓石たちの声は・・一所懸命に生き、人生楽しめ 長谷寺
昨日土曜GW初日に法事なし。
円安はどんどん進んで158円40銭、お人よし日本人の海外旅行に合わせたような・・・
私どもは所要で午前早くから浜松方面に向かいました。
菅山から原に上がり小笠方面に降りるのはいつものコースですが、数日前まではあったあの宮沢クンのポスターが剥がされていました。
ヤケクソになって引っ剥がされたのか、支柱と板はそのままのもの、支柱ごと破壊されたものを見かけて、「そりゃそうだ・・・」と地元有権者の怒りのようなものを感じました。
それでいて市内方向に向かうとまだポスターがそのまま掲示されている場所もあって、統一性まったくなし。
結局組織だった撤去ではなく、掲示板の立つ地元の皆さんが任意で撤去しているのかと思った次第。
残された看板を見て奥方がまるで「晒し首」・・・とボソッと。
あれだけ威勢よく顔を売った御仁、次の仕事はお笑い芸人が最適か?
なんば花月で自虐ネタはきっとウケるでしょうね。
「ワシこれで(小指をたて)ギインをやめたんや こわいでぇ」
当分はそれで喰っていける・・・かも。
それとも裏金をガッツリ貯めこんで悠々自適?
扨、好きな事をやってその時まで生き延びること、すばらしいことです。
他者の評価など気にせず一気に突っ走り時間が来たらさっさと姿を消す・・・など、なかなかできないことで、ある意味感心させられます。
概して人が一所懸命に生きる姿は人々の感動を誘いますね。
特に古い墓地の無縁となった墓石たちの集合の図は圧巻。
亡き人それぞれの楽しかった意気軒高の時間の存在を想います。
それらの前に佇む私に向かって「お前も大いに楽しめ」などと聞こえてくるのです。
2024年
4月
27日
土
よきひと(善知識)のおおせ歎異抄 初瀬與喜山 長谷寺
昨日は奥方は事務仕事。
よってヘルプ無しで静波墓園、連休前の一仕事です。休日は処理場が稼働しませんからね。
一日1回戦が限界・・・は当然、伐採しての積込みの一人仕事は結構に体力が消耗して途中ヤル気が失せました。
積載物は大きく伐ったものを積み込んだのち荷台に上がって、さらに適当な大きさに。
これは受け入れ側の伐採物の長さに制限があることと、ある程度枝端を落として小さくしておかないと空間ができてしまい効率よく積み込むことができないという理由があります。
途中荷台三方にコンパネのアオリを設けますがそれは荷台への乗り降りのストレスになります。
奥方がいれば私が荷台に乗ったまま、下から伐採物を引き揚げて作業するだけですからそれは何とラクなことか。
結局効率の悪い仕事でした。尚、処理場代金は1020円。
処理場から帰ってがらチェーンソーの手入れ、シャワーから出て面白いニュースを奥方から聞きました。
GWの海外旅行者の件、繁盛とのこといわれていますが、この円安(156円後半-36年振り)で「よくもまぁ・・・」と。
海外旅行に行けるような身分、余裕が無い者の嫌味の類ですが、ある家族四人が「ホテルの気の利いた朝食」を愉しんだあとの会計の件、「3万~4万かかった」という嗤えない話でした。
あまりに高額と思えるサービスに日本を発つ際おにぎりやカップ麺を持参するなどの例もあるとのこと。
植栽の伐採の方が余程「ストレスは軽い」とニヤニヤ。
「よくもまぁ・・・」と私もまた呆れたところ。
それでも円安世界に行くのは自由、良きご旅行を。
表記「よきひと」といえば当流では親鸞さんから見た法然さんのこと、あるいは「善知識」ですね。
そこのところ特に歎異抄2条の記述が有名です。
「~親鸞におきては、ただ念仏して弥陀にたすけられまいらすべしと、よきひとのおおせをかぶりて、信ずるほかに別の子細なきなり。
~いづれの行もおよびがたき身となれば、とても地獄は一定すみ
かぞかし~
~詮ずるところ、愚身の信心におきてはかくのごとし。
このうへは、念仏をとりて信じたてまつらんと、またすてんとも、面々の御はからひなりと 云々」
宗教二世なる語があの路上事案以来聞かれるようになりました。いろいろ「因果」というものについて示唆されているように思わされるところです。
しかしながら親が傾倒している何かに子もそれに倣うことを強制するのはたまったものではないでしょうね。
私であっても「冗談じゃあない!!」とやはりそっぽを向きたくなるでしょうね。
とその言葉を言い放つ「宗教十五世」の私がいます。
息子は当然にその十六世ですが、まったく違和感なくその親鸞さんの「よきひと」への傾倒は代々同様に繋いでいるということ。
あの変てこな宗教の信仰心とは違うところがその歎異抄2条「よきひと」の段に記されています。
特に「地獄」については脅しの語として使用するようですが、親鸞さんはそれ平チャラです。当然私どもも。
最後の部分、「信じたてまつらんと、またすてんとも、面々の御は
からひなり」はおおらかさを思います。
「よきひと」との出遭いによってその人に「信」を抱こうが拒否して捨てようが「皆さんの自由」と仰っているところですね。
「信」についても選択権を提供しているのです。
人は何事も他者に強制されることは無い(自然・・・自由)・・・それですね。
扨、画像①②は長谷寺の宗宝蔵の廊下からの図。
長谷寺はこの「与(與)喜山」とセットというのが古来からの信仰です。
初瀬(出雲)の地は菅原道真の祖先の発祥地だということで彼がこちら長谷寺を訪れたなどの伝承が残ります。
彼を祭神とする天満宮、全国数ある中、こちら與喜天満神社は最古級のものだそう。
私はこの山までは歩いていませんが長谷寺山門のごく近くに與
喜天満神社に関わる標が。画像は梅咲く頃のものです。
どうやらこの「與喜」とは神となった菅原道真が「良き地」
「良き山」と語ったことからだといいます。
尚、その初瀬「出雲」の位置関係についてはかつての拙ブログで初瀬流れの件で熊本大学堆積学の松田博貴先生にご教示いただ
いたことを記していましたが、そちらで記した地図にも記してあります。
その松田先生の出逢い、鈴木一久氏の存在もまた「良き人」「善知識」であったこと思い出されます。
「よきひと」との出逢いがあってこその人生です。
それも「面々の御はからひ」で。
2024年
4月
26日
金
本長谷寺と一切経蔵 長谷寺
オオタニサンのその日3本目の二塁打を見てから静波墓園へ。
途中から奥方が合流し区画三面のうち長い方、道路側の植栽をやっつけました。
地頭方処理場の搬入費は1170円。先日より少ないはず(荷台の2/3)なのに少々お高め。計量もあまりアテになりませんね。
清算時に入力ミスがあったそうで待たされましたから。
あと東西二面と積載しきれなかった残材の搬出で3~4日はかかるでしょうね。早くそちらから解放されたい。
奥方はイイ加減くさくさする・・・とボヤきますが致し方なし。
旧光正寺から墓地の管理を継承(寄進)したのですから。
顔と両腕は日焼け。また檀家さんから「海行って遊んでる・・・」とご指摘を受けるわけで。
まごまごしていると蜂が巣を作りだして厄介なことになります。
扨、長谷寺の景色、あの五重塔の上から。
こう連日長谷寺を記していると、遠足で皆さんをお連れしたとして、簡単なガイドくらいはできるでしょうね。
あの階段は見た目圧倒されますが、他所の山寺たちの中では歩きやすい方です。奥方のご意見はさて置いて、今後のバス遠足の候補地として悪くないかも・・・などとだんだん熟成してきたくらい。
十一面観音の堂が「今長谷寺」としてこちらが本長谷寺の堂。
時代の古さが伝わります。
階段を上がって一切経蔵。
そちらからの景色が⑧⑨。⑨の門が⑩になります。
永禄四年 牧野備後の件、不詳。
2024年
4月
25日
木
枝垂れ→御衣黄→牡丹 長谷寺宗宝蔵
仏の臺・台(うてな)に生まれ自身思うままに生かされて「それ」を自由に任せてそれを選択した結果、蓮の台から落下して(地獄に堕ちる)もそれもまたヨシ。
先達が同様の末路を辿ったところを目の当たりにし、十二分にその件承知していても自身の煩悩を「自在のまま」に貪ろうとすればそうなることはわかっているのに。
先般アベハなるグループの人たちが裏金の件で曝され世の政治不信に拍車をかけたところでしたが、あの時「アベハを介錯する」と息巻いていた彼が切腹するハメになったようで皮肉というか殆ど苦笑させられる出来事でした。
あの御仁が初めて立候補する際、たまたま私が居合わせた袋井での刀剣愛好家の試し切りの会に現れ「挨拶を」と初々しさ満点で登場したことを思い出します。
一同に名刺を配りまくっていました。
その場でどなたかが「浜岡原発はどう?」という問いかけをするとそれまでの弁舌の滑らかさに反して一瞬口ごもっていたことが印象的でした。その件、触れてもらっては困る・・・といった感じでした。
私には地盤違いで投票権はありませんし、目の前の御馳走の方が気がかりでしたのでどうでもいい時間でしたが、それにしても立候補するたびに看板の髪が濃くなる様を見て「変なこだわりがあるのだな・・・」とも。
というワケで「そこかぁ・・・」と文春の記事で納得した次第。
昨日は菊川方面に所要で向かいましたが、まだ各所に彼の顔がアップされた写真が立っていました。
報道では事務所では色々撤去されているとのことでしたが、取り残されている各所に存在するそれを見て三尺上の獄門台を連想しました。
まぁそれも御当人が選んだ自由なのですから。
扨、先日は奈良長谷寺のシダレは散り始めの満開、十分に楽しめたのにも関わらず翌日の京都醍醐寺のシダレは殆どゼロといった件を記しました。
当家でもオオシマーソメイヨシノーシダレー八重といった感じの季節変化を見ていますが、その順序は大概のところは同じでしょうね。
長谷寺の八重も満開の木を見つけたのは例の長階段の途中右にある宗宝蔵の門内です。
八重桜の種類でも御衣黄(ギョイコウ)という名。
何となく品の良さが漂いますが、遠目から見たら盛りの過ぎた葉桜のようにも見えます。
③④は宗宝蔵。③画像に限りサイトから。
この収蔵館は特別に拝観料が必要ないのとたまたま係りの人が呼び込みの如く声を掛けていましたので人々が足をとめていました。
⑤⑥⑦が御衣黄。
①と⑧~が長谷寺の別名「花の御寺」の通り一番のウリかと思われるボタンにバトンが繋がります。
2024年
4月
24日
水
慶長期徳川家康の天守に迫る 加藤理文氏
曇天ながら雨域の広がりは夜遅くからとの予報でしたので静波墓園の伐採作業に。
奥方のヘルプも入りましたのでチェーンソーを振り回して効率よく仕事が進みました。
ただし何せ軽トラです。積込みのヘルプはラクですが、積込み容量に限界があります。
積み切れない伐採材は墓地の隅に放置してそのまま処理場へ。
軽トラ背後のアオリに設置するコンパネを忘れて来たため(押さえはロープのみ)処理場へのコースは150号線を使用しない山越と旧道コースでした。
二回戦も考えましたが帰宅してチェーンソーの清掃と整備に
約1時間。15時を過ぎていました。
先日は奈良行脚に久々一日2万歩オーバーを出していましたが
疲労度は昨日の方が断然上。へろへろになりました。
尚、処理費は1170円でした。
扨、画像は「徳川みらい学会」第1回講演会( 加藤理文氏 )資料「慶長期徳川家康の天守に迫る」です。
現状、駿府城天守についておさらいです。
静岡の秋野氏から提供いただきました。
2024年
4月
23日
火
奈良山間と京都の差 長谷寺歓喜院能阿弥顕彰碑と辞世
一昨晩からの雨はあがりましたが朝は強風から始まりました。
残っていた八重桜の桜吹雪は可哀想な気も起こりましたが・・・
しかし10時前には風も収まって四十九日の法要を修めることができました。
当家のご都合が月曜日と言うことで昨日になりました。
故人は拙寺近隣の住まいながら藤枝の病院にて逝去。
ご長男が藤枝の葬儀社と知り合いとのことでそちらで葬儀が執り行われ地元のお知り合いたちはその逝去も葬儀式についても知らなかったとのこと。
よってせめて四十九日法要と墓前にお参りしたいということで生前、お付き合いのあった皆さんが堂内に集まりいつもとは違った空間になりました。
とにかく天候が穏やか、滞りなく法縁を結ぶことができました。
扨、昨日は奈良長谷寺の景色、桜の咲き具合など見ながら下山したことを記しましたが、ざっと奈良の桜はその4月15日の段階でまだ名残がありました。
てっきり咲き終わっていたかと思っていましたので意外、思わず楽しむことができました。
ということで翌日の京都も十分イケると踏んだワケで、本山へ辿る前に急遽寄り道をすることにしたのでした。
奥方が同行していなければ絶対に寄っていこうなどいう気は起こらない桜の名所、醍醐寺です。
平日ながら人少なし。それは都合よきことですが、もしやと思い、駐車場に車を停めたあと(今回はコインパーキング)、三宝院近くの総門前から出てきたご夫婦に桜の状況を聞くと苦笑いしながら「ゼロで~す」と。
唯一残っているのはこの総門前のものだけ・・・とのことでした。
以前未練の残った三宝院の拝観チケット売場前で奥方に「二人で3000円、サクラあってこそだがどうする?」と問えば「帰路へ」と。
よって仁王門まで歩いて反転した次第、パーキング代は100円でした。
画像①~④は長谷寺仁王門入ってスグ歓喜院の門前のシダレと能阿弥顕彰碑そして辞世。能阿弥は長谷寺で亡くなっているとのこと。
建碑は今年の3月。ピカピカです(茶会→こちら)。
⑤~⑦は唯一残っていた醍醐寺の総門前のシダレと仁王門前の図。お天気具合が怪しくなっています。
目を凝らせば微かに・・・この門を潜り金堂方向に行くには拝観料が発生します。
奈良山間部と京都盆地でこれほど差が出るとは・・・
2024年
4月
22日
月
長谷寺本坊と閼伽井 井戸は建屋に
午前・午後と法事がありました。
両方ともポツポツ程度の時間はありましたが何とかセーフ。心配無用でした。おかげさまです。
昨日、午後に来られた世話人さんから。
御当人も脊柱管狭窄症について指摘を受けているそうですが知り合いの方がこのほど手術に踏み切ったとのこと。
これ以上の痛みからおさらばしたいというところです。
この地域ではその手術に対して結果好評だという病院(西部)があるそうですが、そちらはあまりにも人気があってスグには手術ができないとのことで別の病院(中部)にて施術。
ところが退院後、歩行困難に陥ってしまったとのこと。
手術が失敗なのか何なのか原因はわかりませんが、そのような状態に陥るなど本来のその方の希望(痛みの解消)とは真逆。
却って悪化させてしまうのですからね。歩けないなんて・・・
他者で施術後全快して軽やかに歩ける人がいるなか、それも個体差ということで片付けられるものか、と考えさせられます。
医者は失敗とは言わないでしょうし。
失敗したとしても手術前に誓約書に署名していますからね。
余程のミス以外責任追及はムリ。
そんな話を聞くと、私は頸椎の不具合と手術についてかねてから「どうしようか」ともじもじしながらここまで過ごしていますので、やはりそんな出会いは御免です。やはりやらないのが正解か・・・の思い。
我慢が効くならこのままでいた方がいいですね。
しかしながら歩行ができなくなったとして、その時にはその時の人生があるとでも開き直る私がいるでしょうが。
庫裏通路・トイレ・風呂そして本堂内の改築をしなければならないのは困ります。小さな庵でも作ってもらおうかな。
まぁ完全に引退して息子にまかせればいい。
「草庵」「隠遁」などその言葉は案外かっこいい。
しかし外に出られないと・・・痴呆が進みます。それは困りもの。
扨、長谷寺への奥方を連れての行脚はおかげさまで無事に終了したのでしたが、一般客の動向を傍観していると、まず大抵はあの階段を登り切り、巨大十一面観音を拝観、満足してしまうのかそこから反転して元来た階段を降りていく姿が多いような。
あの階段に恐怖を感じる年配者は多いでしょう。
その手のインパクトある行脚がこれからも続く事は誰でも連想するところですからね。
よって一足伸ばして歩くとしてもせいぜい昨日記した五重塔くらいまででしょうか。
「突き当り」を思わせる本坊まで向かう方は相当少ないでしょうね。
ところがその本坊の位置は既にこの山を降りつつある場所にあり、そのまま入門、階段コースに戻らずにそのまま下山できる位置にあります。
仁王門のスグ脇に出られますので、トップから同じ道を戻るのではなくそのまま降りる一周コースがお薦めになります。
画像は以前の2月頃の図と桜の終わりの図がごちゃ混ぜになっています。
以前と変わったのは閼伽井(またはこちら)に覆いの建屋ができていたこと。
奈良市内の名所と違って比較的人少なし。穴場でしょうね。
2024年
4月
21日
日
長谷寺三重塔址礎石と五重塔 ベンチにて佇む
朝一は静波のご門徒さん宅でのお内仏閉扉式に向かいました。
ご両親の逝去以来その家は10年近くの間、空家のままでしたがこのほど空家専門の仲介業者のサイトに登録したところ、早々に買い手が見つかったといいます。
買い方は私がこれまでそういったケースで承知している市外遠方の方ではなく近くに住まわれている方のよう。
リフォームしてどなたかに住まわせるそうですが施主としてはとにかく懸案の問題が解消して安堵していると。
上等そうな家財道具がありましたが、シルバー(人材センター)さんに搬出依頼するとのこと。
他の書籍などの搬出によって腰を痛めてしまったそうで、外注に頼るほかはなかったのでしょうね。
「軽トラを貸しますのでお気軽に・・・」と言って退出しました。
尚、一旦閉めたお内仏は別宅に収めるとのこと。
その際の開扉法要を承りました。
扨、昨日記したN君の早逝の報せ以来、ここのところ私どもの家の中は心の底からの朗らかな気分は消えています。
息子には「どうにもならないことにつき、もう考えるのはやめよう、いろいろ推測するのはやめよう」と言って聞かせてはいるものの私も奥方も頭の隅にそのもやもやが滞留したきりになっています。
息子同様私も仕事がらそういった「別れ」の場には立ちあっているものの息子と私どものその思いには違いがあり特に懇意にしていた息子の彼への思いと突然の感情コントロールの件当然に深いものがありますからね。
また息子は先般中学生の逝去の件、葬儀依頼を受けその家族と向き合う時間を持っていましたが、私でも尻込みしたくなる事案でした。
辛すぎる現実を目の当たりにし経験を重ね、成長させてもらっているようです。
扨、長谷寺には圧倒される遺物が各あるわけですが、寺の外観景色として目を引くのが五重塔。
ただしこちらは本来の姿は三重。
焼失後なぜか「三→五」というわけですね。
各掲示板は以前のものから新調されていました。
それぞれ前の画像を並べてみましたが読みやすい。
着眼は今は無き三重塔の礎石たち。
周囲にはローソク屋さんの銘のあるベンチが並んでいますが、そちらでも奥方は頭を抱えて座り込んでいました。
2024年
4月
20日
土
苔と土と森に同化 消えていく墓石たち 初瀬墓地
朝方の庫裏内の気温は19℃。
20℃割れはシャツ一枚はきついものがあります。
しかし外はスカ晴れ。
トレーナーを脱ぎ軽トラに伐採道具を積んで静波の墓地へ向かいました。今回はガッツリ外周植栽(カイズカ)をやっつけようという算段です。
取りあえず挨拶代わり。
様子窺い感覚でチェーンソーを枝払いにと振り回しましたがスグにチェーンが脱落。最初に小枝払いに使ってのこと。大枝をぶった伐るつもりでしたが。
久々の出動であったこと修繕用小道具を持参して来なかった凡ミスが重なって以降作業は手作業。
よってまともな仕事とはなりませんでした。
来週は雨続きの予報があり、これではいつ仕上がるのか・・・まぁ勝手にしやがれの心境。
半日分の処理費は710円でした。
これから地頭方に何往復して処理代がどれくらい嵩むのか・・・
扨、先日は本山両堂で念入りに手を合わせたと記しましたが、その「念入り」とは、やはりそのような真摯な気持ちになったからということ。
その真摯なる語は大抵の場合、最近はその真摯とは程遠い真逆の人間がこぞって使いたがる言葉となった感がありますが、どちらかというとその語には私どもの反省にも似たやりきれない回顧があったからでした。
最近はお気楽気分のノー天気、阿呆丸出しの如く生き生かされている私があったわけですが、その報せは膝が崩れるほどに歩みが止まり、絶句させられました。
息子からの連絡。
「N君が亡くなった」というのです。
N君は息子より年下ですが仲良くしてもらっていて2018年の夏休みの終わり、彼は1週間ばかり拙寺に逗留して息子が色々な場所を案内、私どもも焼き肉屋で一緒に夕食をとるなどしていました。学校では彼の友達の中では一番に付き合いが深かったと。
拙ブログにも記していますが、土蔵の掃除を手伝ってもらった彼です。
昨日は「天職」などいう語を記しましたが、彼もまた真宗大谷派の教師資格があります。
ただし次男ということ。兄は既に住職として寺に入り、別のお寺でその道のいろいろについて学んでいたといいますが、それは拙寺の息子と同様です。
しかしN君はスグに、おそらく一般的に言うその4、5月の頃だと思いますが寺の仕事を辞めてしまったといいます。
そしてそれから、某携帯電話会社の店の店長として働いていたことなど息子から聞いていました。
息子の「ショック」は手に取るようにわかりました。
私どもはその報を奈良で聞き、本山での「念入り」となったわけですが、私どもが帰宅後も幾たびかの息子の溜息と「何故・・・」という言葉を耳にしました。
息子の後悔は最近連絡を取り合っていなかったということ。
「まさかの坂」を転がる思いをさせられました。
「若いのに・・・」奥方と私も溜息。
詳細については不明ということで納骨が済んだら皆でお参りに行くと。
車で向かうのはやめて欲しい。
彼の地は東北地方の「上の方」だといいますから。
画像は、その思いがあったからか奥方も付き合ってくれた長谷寺奥の初瀬墓地。
日頃「墓と城はムリ」とのことですからね。
昨日は人は亡くなれば、誰も忘れられていく・・・ようなことを記しましたが、遺物としての墓石もこの山では時間とともに自然と同化していきます。
中には土の中から顔を僅かに出しているようなものも①。
判読不明ですが何か記されていました。
読みたい気持ちもありますが、ご挨拶して別れました。
これら画像の中、②の姿が首を傾げているように見えて思わず
にっこりと反応。
一つ一つの墓石たちはその人の人生を表しているようですが、みんな同じように朽ちていきます。
その人生がどうであったにしろ、みな亡くなってかつ同様の朽ち果てる様がここにありました。
また若き人の墓標が目に留まればついつい立ち止まってしまうのはいつものこと。
私は南無阿弥陀仏としか口称できませんが。
しかし・・・しかし・・・独りで結論を出さないで・・・。
選択肢はまだまだたくさんあります。
2024年
4月
19日
金
長谷寺の山 初瀬墓地再訪 天職とは・・・
予定では静波の墓地の整備に向かうつもりでしたが、雨の時間があるとの予報でヤメにしました。
よって奥方に言いつけられた大工仕事と先日購入した角材の残りを加工、寝床の部屋の梁の下にかましました。
まぁ気休めの部類ですが・・・。
少しは違ってくるかも知れません。まぁその時、その耐力を確認する場合ではないでしょう。
角材は梁と床の間のサイズ原寸より2mmほど長めに切りましたがソフトハンマーで叩いても入りきれませんでした。よって急きょジャッキをかまして沈んでいた梁を数ミリ上げて設置完了。午後はそれを固定する金物を求めに・・・
4月も中旬すぎて、新卒者の退職が増える頃。
今や退職代行業なるサービスがあって今は繁忙期と。
会社を辞めるのもお気軽ということですね。
「ダメ」の結論を出すということですがダメを無理して継続、自身を痛めつけるよりもさっさと退職、新天地に希望を抱いた方がマシですからね。
「レボリューショナリー・ロード」なる映画の中で、これから会社を辞めてパリに行くという主人公にその同僚が「パリには天職があるのかい?」という単純な質問に対し彼は「少なからずここにはない」といった台詞がありました。
世の中でそれこそ天職であると誇れる仕事に巡り合える人はそうはいないでしょうね。
要は「天職」の存在を夢見ていたら・・・人生は終わってしまうだろうから。
ちなみに私や息子など寺に生まれたことから選択肢は他にありません。そういう意味からして今の仕事は必然であり自然。
よって天職なのかもしれません。
私は「天」といえば浄土世界をイメージしますからそれは「阿弥陀さんのお仕事」でよろしいかと。
扨、先日は奈良長谷寺を奥方を連れて歩きました。
長谷寺といえば長躯399階段とその先の巨大な十一面観音です。
京都の貴族たちもこちらへのお参りを欠かさなかったこと、広範囲にわたって派生造立、影響を及ぼしたその観音のスタイルは私としても今一度お目にかかりたいということもありましたが、そちらを奥方にご紹介すること、また拙寺遠足にこちらは如何?とその感想を聞き検討するという意味もありました。
しかしながら私の本当の目的はあの観音堂より更に奥、初瀬墓地の墓域をただ歩くこと。
また墓域の最も奥から観音堂の背後に廻りこみ、屋根越しの景色を望みたいとも考えましたが、それは木々の繁茂があって眺望は不可でした。
道も途中で消え、奥方は携帯電話を取り出して息子や義母に「こんな酷い目に遭わされている」とボヤキ出しましたのでもはや無理と引き返しました。
奥方の意見
「遠足はまずあの階段のストレートを見ただけで皆さんは怒り出すだろう」と。そして二度と遠足には来てくれなくなるかも・・・ということでした。
初瀬墓地で私が一番に印章深く頭に残っている洪水墓碑(こちらも)への案内など絶対に拒絶されるでしょう。
以前もこの初瀬墓地散策の魅力について記しましたが、現代の新しい墓地も奥にあって、お参り用グッズが収められた小屋が六地蔵堂の並びに設けられています。
そちらの最近建碑されたであろう墓地群墓域の荒れ具合も酷いもので草ぼうぼうです。この時節その様ですからこれからもっと酷くなりそうな気が。
また夏場等はこちらに立ち入る酔狂は有りえないかも。
その奥の墓域には昭和・平成から令和まで新し目の墓が勢揃いしていますが、最近お参りに来られたような形跡はナシ。
奥方との会話。
人が死ぬと「あっという間に忘れられる」ものであるとの確認。それは仕方ないことかも。
縁者たちは皆今生きることに必死だから。
故人たちの想いも「別れの悲しみを忘れて前に向かって生きなさい」それ一つでしょう。
何よりこちらの墓地は気軽に行きにくい山の中腹です。
そういう場所に静岡からやってくるというのはかなりの変わり者夫婦なのかも。
ちなみにその「レボリューショナリー・ロード」は夫婦の問題
を描いた真面目な映画です。
あの「タイタニック」のコンビが夫婦役。その映画の続編でも何でもありませんが・・・言い争いなどないように、心がけよう。
最後の画像が初瀬墓地に上がる道で出会ったイタチ ?の夫婦。
その姿に癒されたか続けて奥方は山道に歩を進めてくれました。